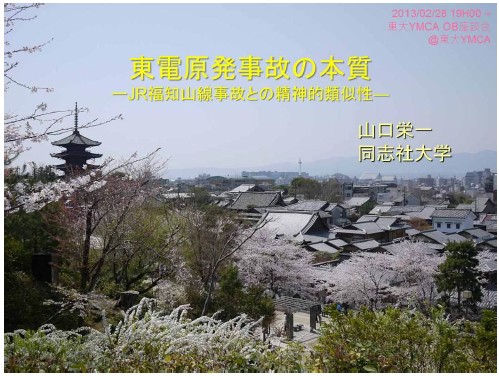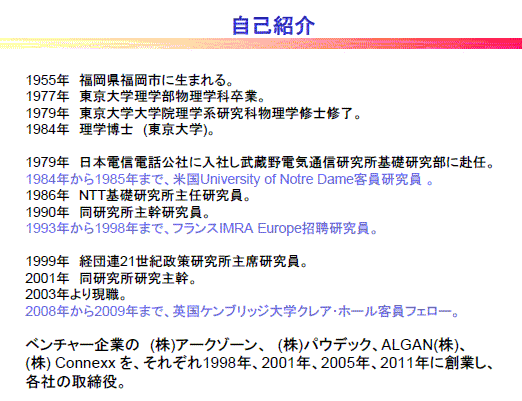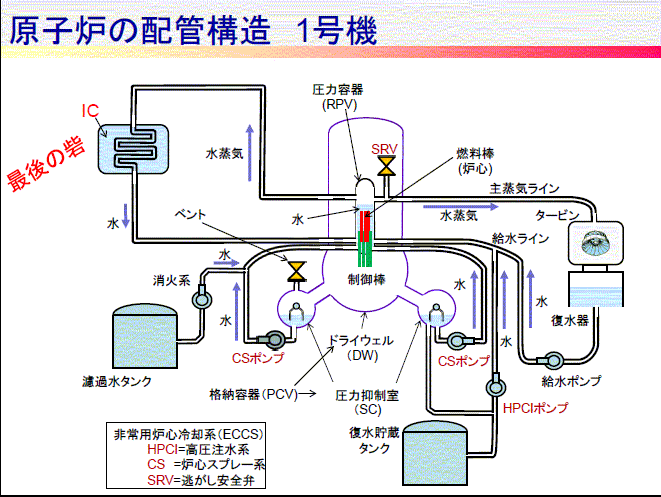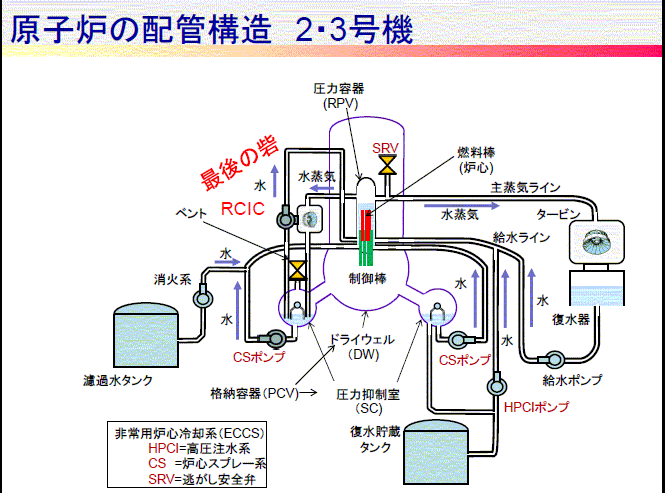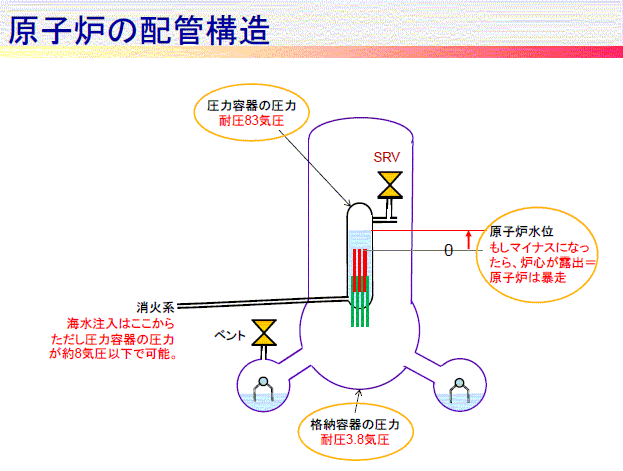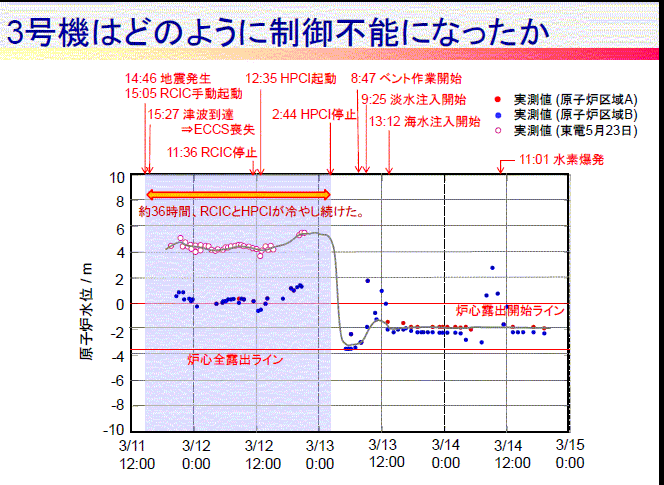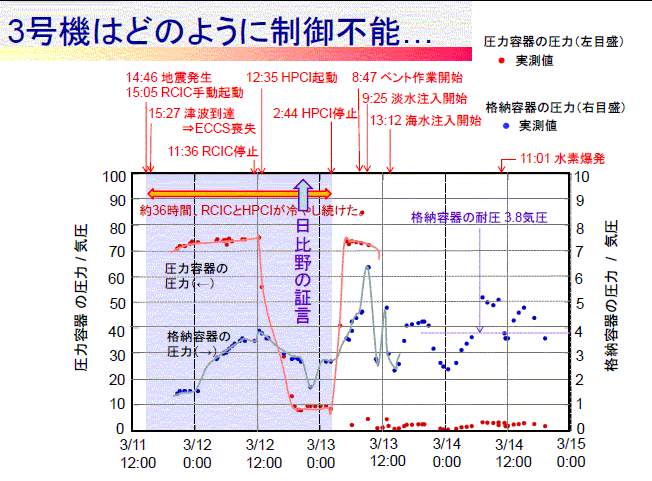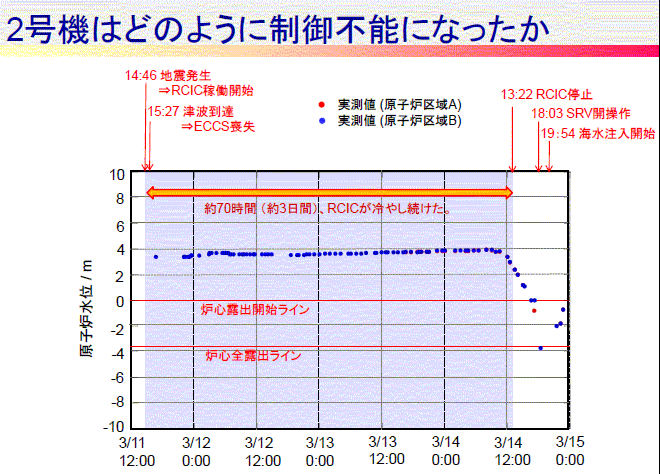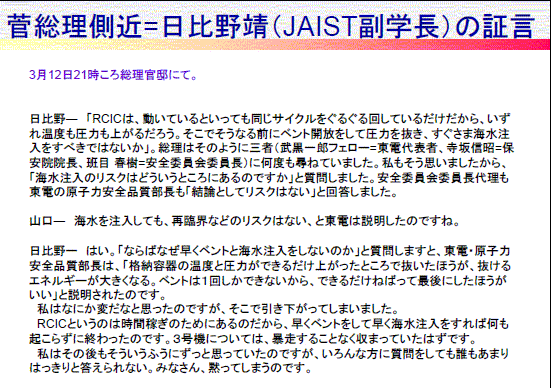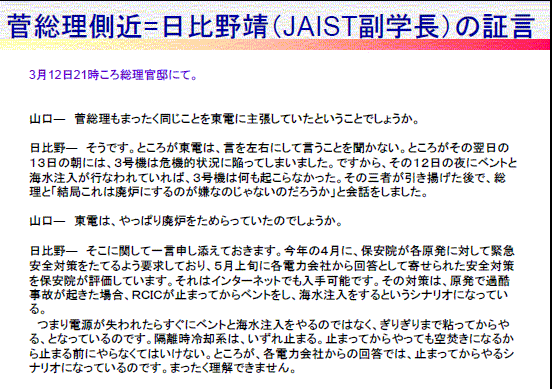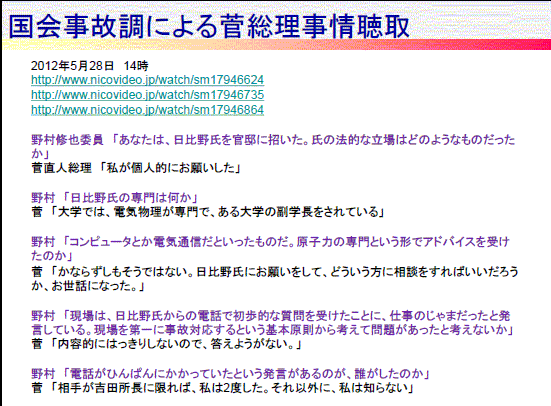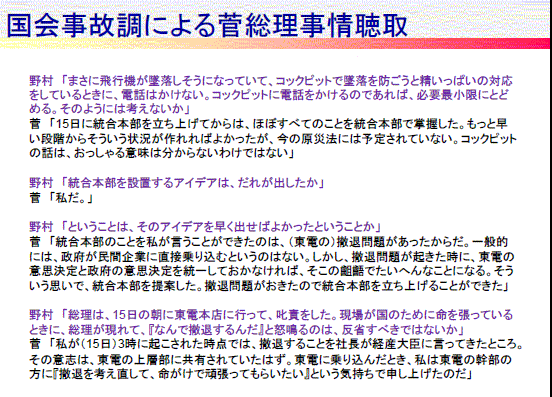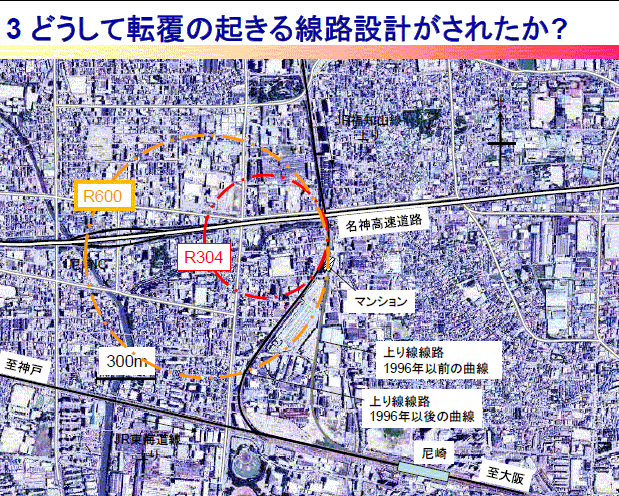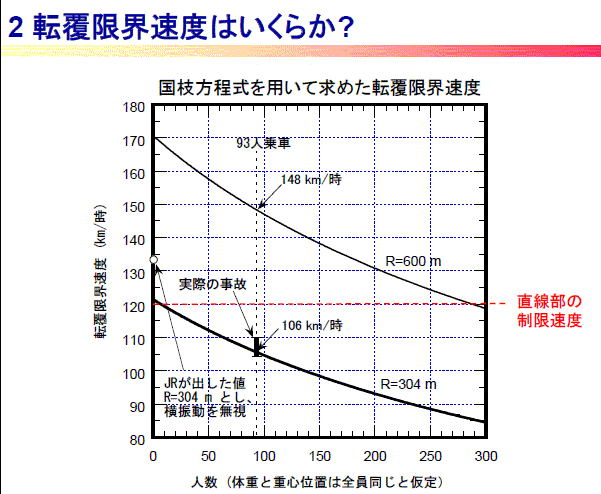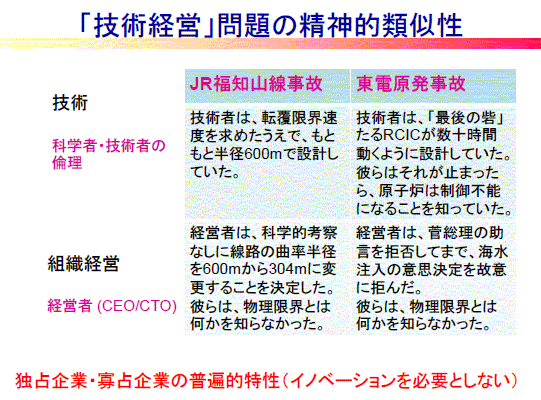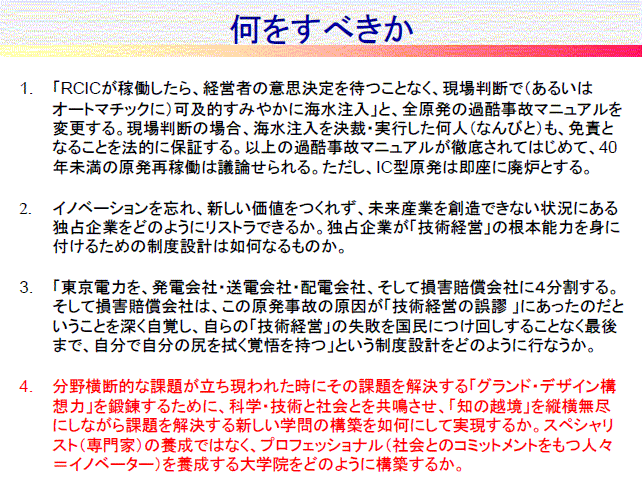私は先週、(1ヶ月前に送られてきていた) 東大YMCAの『會報』のこの記事に目が留まりました。読んでみて非常に大事な記事だと思いましたので、すぐに著者の山口先生(と東大YMCA)にメールして、本『TRIZホームページ』への再掲載を願い出ました。山口先生は快諾くださり、私の求めに応じて、2月の座談会でのスライド一式、『會報』掲載原稿のWordファイル、および、
外国人記者発表で使われた英文スライドファイルを送ってくださいました。これらの一揃いをここに掲載でき、厚く感謝いたします。
2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、下記の4件の事故調査報告が出たことはよく知られております。
(a) 「民間事故調」: 福島原発事故独立検証委員会 (一般財団法人日本再建イニシアティブ)、北澤宏一委員長、報告書提出:2012年2月27日。
(b) 「東電事故調」: 福島原子力事故調査委員会 (東京電力株式会社)、山崎雅雄委員長(東電副社長)、報告書提出:(中間)2011年12月2日、(最終)2012年6月20日。
(c) 「国会事故調」: 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 (国会)、黒川清委員長、報告書提出:2012年7月5日。
(d) 「政府事故調」: 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 (政府)、畑村洋太郎委員長、 報告書提出:(中間)2011年12月26日、(最終)2012年7月23日。
本件記事は、これら4件のほかに出された「草の根事故調」ともいうべき、つぎのプロジェクトの報告に関連しています。
(e) 「草の根事故調」: FUKUSHIMAプロジェクト委員会、山口栄一委員長、報告書出版: 2012年1月30日 (日経BPコンサルティング刊)。
これら5件の報告書はそれぞれ綿密・詳細なものですから、私自身もほとんど読めていませんでした。
そのような折に、この10頁ばかりの簡潔な記事は読みやすいものでした。特に、事故の本質を、「技術の欠陥」というよりも、「技術経営の誤謬」であり、東電の経営陣に大きな責任があると、明快に論じています。他の(a)〜(d)ではあまり明確にしていない論点であり、貴重なものと思います。FUKUSHIMA プロジェクトは300人以上の方の寄金を得て報告書の廉価出版をしていますから、本件のテーマに関心をお持ちの方はもっとずっと早くからこの情報を知っておられることと思いますが、できるだけ多くの人々の目に触れることが有益と考え、本ホームページにも再掲載させていただく次第です。
和文ページに、記事のHTML版とPDF版 、スライドのPDF版
、スライドのPDF版 を掲載し、英文ページ
を掲載し、英文ページ に外国人記者発表における英文スライドを掲載します。なお、本ページの編集後記をも参照ください。
に外国人記者発表における英文スライドを掲載します。なお、本ページの編集後記をも参照ください。
2011年5月に作ったページ「東日本大震災 (地震、津波、原発事故) と 今後: 参考資料とノート」 を親ページとして扱い、本ページへもリンクを張っておきます。
を親ページとして扱い、本ページへもリンクを張っておきます。
追記(中川 徹、2013. 9.29): 英文ページに、山口栄一教授の国際会議 (ISIS2012、英国ケンブリッジ大学、2012年9月11日)での講演を掲載しました。Fukushima Report (2)
原子炉の配管構造
まず、福島原発の1号機と2、3号機の配管構造の図を見てください。 原子炉の炉心(燃料棒)は、「やかん」と思ってください。原子炉の問題は、科学でもなんでもない。技術の問題です。そして、その技術とは、要はこのやかんをいかに冷やすかという問題なのです。
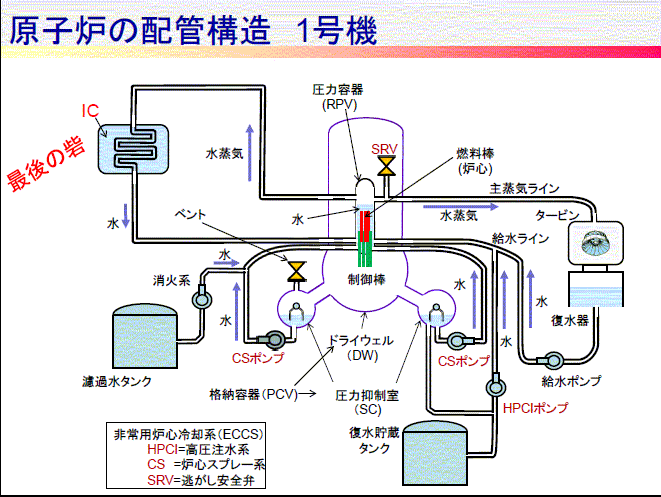
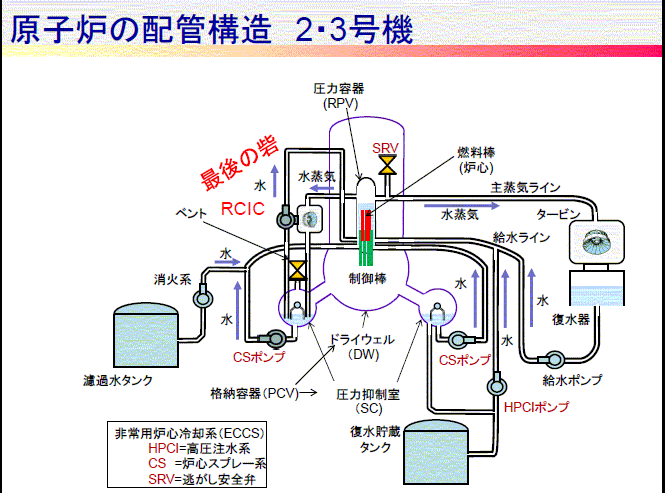
炉心で作られた水蒸気は、主蒸気ラインを通り、タービンを回して電気を起こします。 その後、蒸気は復水器で、大量の海水によって冷却されて水にもどされ、それがまた炉心に戻って炉を冷やします。ところが、津波のあとAC電源が壊れ海水を取り込むポンプが壊れて、この主蒸気ラインを通じての炉心の冷却ができなくなりました。
しかしこの事態になった時でも、非常用炉心冷却系(ECCS)というシステムが機能し、冷却を続けることができます。 まず、圧力容器内の気圧が75気圧以上になるとSRV(逃がし安全弁)が開いて圧力容器から格納容器に水蒸気を逃がします。次にHPCI(高圧注水系)とCS(炉心スプレー系)の2系統が作動し、復水貯蔵タンクや圧力抑制室の水を圧力容器に送って炉心を冷やすのです。
ところが、津波で非常用電源が壊れ、ECCSは、3号機を除いて停止してしまいました。 「ECCSがだめになったので、常に水の中に入れて冷やしておかなければならない圧力容器内の燃料棒が水から露出してしまい、原子炉はついに制御不能になった。」
マスメディアはそう報じました。ですから、みなさまもそのように思いこんでいたのではないかと思います。
でも、そうではありません。 実は「最後の砦」があったのです。1号機では「IC」(非常用復水器)、2、3号機には「RCIC」(原子炉隔離時冷却系)という「最後の砦」があって、ECCSがダウンした後も、1号機のICは8時間、3号機のRCIC(とHPCI)は36時間(1日半)、2号機のRCICは70時間(約3日)動いて、冷却を続けていたのです。ECCSがだめになり、すぐに暴走が始まったわけではなかった。ここが、まさに今日の課題です。 この「最後の砦」が動いている間に手を打てば、原子炉は暴走しませんでした。そして客観的にみて、少なくとも3号機と2号機については、海水注入をする余裕がありました。ところが、経営者はそれを拒んだ。なぜなのか。これが、今日のテーマです。
わざわざ山を削って原子力発電所を海抜10メートルという低い位置に原子炉を建設したこと、非常用電源のほとんどを地下1階に配置したこと、など、いわゆるリスクマネジメントの不備がさかんに問われています。また1号機については、現場の作業員がICを止めてしまうなど、現場の失敗を、政府事故調などは糾弾しています。もちろんこれらは重大です。ところがこの原発事故の原因を考える時に、リスクマネジメントの問題や現場の失敗にばかり目を向けると、問題の本質を見誤ります。本質は、リスクマネジメントでも現場の失敗でもない。技術経営の過失なのです。いまからそれを論証します。
原子炉の制御の3つの物理量
原子炉の暴走の状況を調べる時、測定された物理量について大事なものが3つあります。 第1に、圧力容器の中の「原子炉水位」。これは、燃料棒(炉心)の露頭から測ることにします。よってこの値はプラスでないといけません。プラスなら、燃料棒が水に浸っていて炉心は制御可能の状態にある。
ところがマイナスになると炉心が水から顔を出すことになるので、とたんに制御不能となり、暴走して燃料棒のメルトダウンが始まります。
第2に、「圧力容器の圧力」。 圧力容器は、最大83気圧まで耐えられます。 先ほど申し上げたように、75気圧になるとSRVが作動し、中の水蒸気を逃すようになっています。今回の事故ではこのSRVがきちんと作動したことが分かっています。
そして第3に、「格納容器の圧力」。格納容器の耐圧は、3.8気圧です。もしこの圧力が3.8気圧を大幅に超えてしまったら格納容器が爆発してしまいますので、ベントを手動で開ける。こうして格納容器の爆発を防ぐようになっています。ただし日本の原発では、ベントのあとに放射性物質をトラップするフィルターが付けられていませんでした。とはいえ、原子炉水位がプラスであるあいだにベントを開ければ、周囲に放射線被害をほとんどもたらしません。ところが原子炉水位がマイナスになって炉心の一部がすこしでも溶けた後にベントを開けると、放射性セシウムなどが外に放出され、多大な放射線被害をもたらします。福島の悲惨はこうして起きました。第1の「原子炉水位」がプラスであるうちにベントをして中の圧力を抜き海水注入をしていれば、この悲惨は免れたのです。
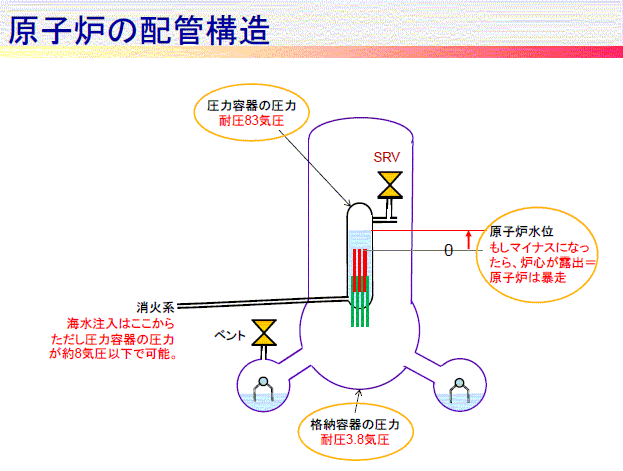
この3つの物理量をよく記憶しておいていただき、3号機ついで2号機がどのように制御不能になったのか、東電から官邸に送られたファクスを読み取って作り上げたデータを今から示します。
3号機はどのように制御不能になったか
まず、3号機。
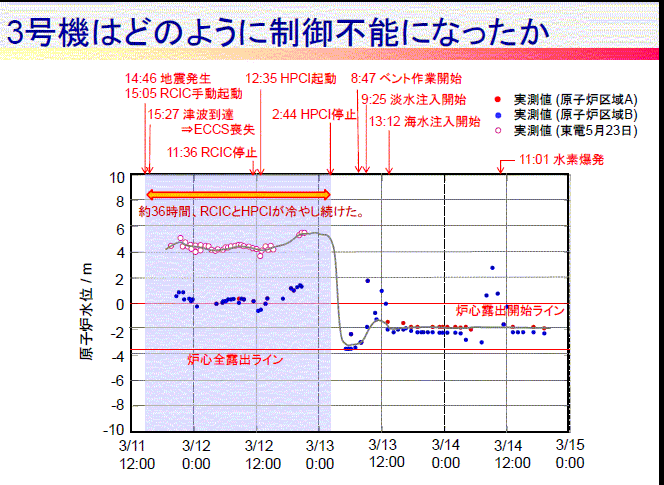
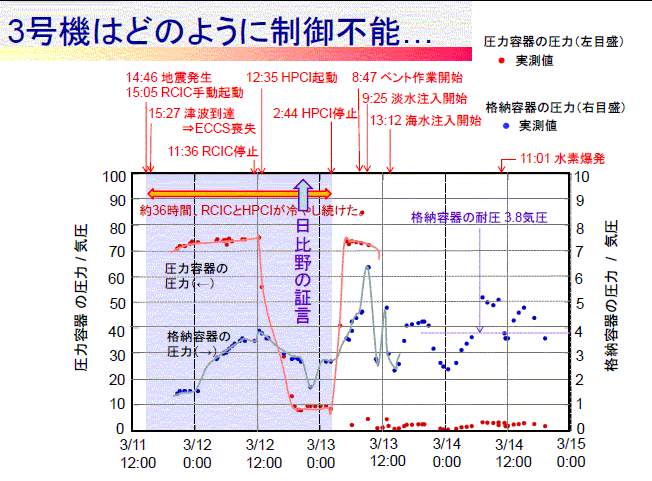
地震発生の後、11日の午後3時5分にRCICが手動起動されます。その後、ECCSが津波で喪失した後もRCICは動き続けます。作業員のミスで12日午前11時36分にRCICが止められますが、HPCIがその1時間後に自動的に動きはじめ、こうして、13日午前2時44分まで1日半の間、3号機の原子炉は冷やされ続けました、その結果、原子炉水位はプラス4メートルから5メートルで推移しています。圧力容器の圧力もHPCIが起動した途端、75気圧ぐらいから一気に下がり始め、12日の午後には8気圧にまでさがりました。HPCIは、RCICに比べて冷却能力が10倍程度あるゆえんです。
ここで、みなさんは不思議に思われるはずです。
ならば、なぜRCICおよびHPCIが動いて原子炉水位がプラスであるうちに、可及的速やかにベントの上、海水注入をしなかったのか。とりわけHPCIが動き始めたあと圧力容器の圧力は8気圧程度にまで下がったのですから、3月12日の夕刻から13日未明にかけては、ベントを開ける必要すらなく消防ポンプで容易に海水を入れられたはず。なぜ海水注入の意思決定はなされなかったのか。
海水注入をしてしまうことで3号機がダメになってしまう。ぎりぎりまで海水注入をすることなく粘りたい。東電の経営陣としては、そう考えたのではないか。3号機を廃炉にすることが嫌だったから、海水注入を意図的にしなかったのではないか。
しかし、これは仮説に過ぎません。そう主張したとしても、証拠がない限り、意味を持ちません。その証明は、FUKUSHIMAプロジェクトの最大の課題となりました。
2号機はどのように制御不能になったか
次に、2号機について分析してみましょう。
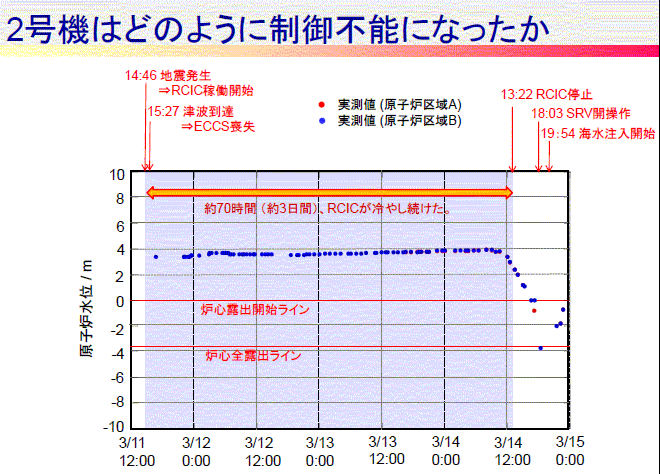

2号機では、RCICが驚異的にも約3日間ものあいだ、炉心を冷やし続けました。
原子炉水位はその間4メートルを維持し、圧力容器の圧力は50気圧台から60気圧前後、格納容器も3月12日は、3気圧未満でした。だから、3号機同様、この「制御可能」の間にベントを開くことも海水注入も行なうことができました。 ところが東電の経営陣は、海水注入の意思決定をしなかった。3号機も2号機も、「最後の砦」が停止し、原子炉水位がマイナスになってしまって炉心溶融が起きてから、ようやく海水注入を行なう意思決定をしています。 水位がマイナスになってしまったら、燃料棒が崩壊熱で溶け、放射性セシウムやストロンチウムが格納容器のほうに出てきて、ベントを開ければこれらが外界に出てしまって大変なことになる。
繰り返しますが、とりわけ3号機では、HPCIが動いて圧力容器の圧力が8気圧の時であれば、比較的容易に消防ポンプで効率よく海水を注入できた。原子炉水位をプラスに保ち続けていれば、決して原子炉は暴走に至らなかった。
なぜ東電の経営陣は、ベント操作も海水注入も、原子炉水位がマイナスになり原子炉が暴走するまで、その意思決定をしなかったのか。
仮説の検証- 菅総理側近=日比野靖(JAIST副学長)の証言
私は、2011年3月に、東電が逐次公表するデータ(さいわい官邸が逐次公表していました)をグラフにプロットしながら、この謎を解こうと思いました。繰り返しますが、仮説は明らかです。すなわち東電は2、3号機を廃炉にすることが嫌だった。だから意図的に海水注入を拒んだ。
しかし、その仮説を主張してみたところで、東電経営陣が「いやいや、そんなことはない。我々は最善を尽くした。海水注入についても、原子炉暴走の前(原子炉水位がプラスであるうち)に意思決定した。しかし結局のところ現場があわてふためいて混乱し、海水注入ができなかった」と主張すれば、水掛け論になってしまいます。ここは実際に現場にいて「状況」を目の当たりにした方の証言がどうしても必要です。しかしそのような証言者の発見は、まったく不可能でした。
しかし僥倖が訪れました。
2011年11月、菅直人前総理の側近として官邸で対応した日比野靖JAIST副学長から、メールが届いたのです。 日比野さんは管さんに乞われ、2011年3月12日の午後9時から菅さんのそばにいて、そこで起きたことを見聞きしていたのでした。 そこで私はさっそく日比野さんにお会いしてインタビューさせていただきました。 資料に、日比野さんからのインタビュー録をそのまま載せています。 12日の午後9時ごろの話です。
菅さんは、東電の武黒一郎フェロー(当時)、原子力保安院院長、原子力安全委員会委員長に「3号機と2号機について、いますぐベントをして圧力を抜き、すぐさま海水注入すべきではないか」と何度も尋ねています。 日比野さんも、東電(原子力安全部長)から「海水注入のリスクはない」との答えを得たあと、「そうなら、なぜ早くベントと海水注入をしないのか」と言ったといいます。これに対し、東電は、「ベントは、できるだけ粘って最後にしたほうがいい」と主張したそうです。そして結局、HPCIが停止した13日朝、3号機は暴走してしまった、と日比野さんは証言してくださいました。
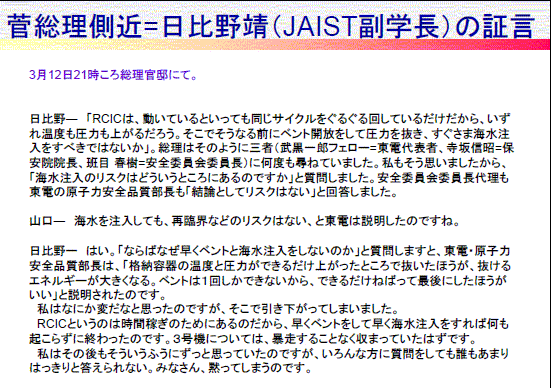
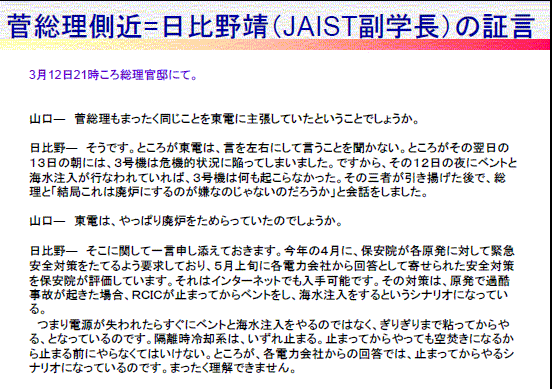
国会事故調による菅総理事情聴取 −閉鎖的専門家(原子力村)と非専門家
以上、論証してきたように、この原発事故は、技術経営の誤謬にもとづくものです。
ところが、去る5月28日に、国会事故調査委員会が、菅前総理の事情聴取を行ないました。その中で、聴取にあたった野村修也氏(中央大学法科大学院教授・弁護士)は、「日比野靖氏という、原子力の専門家でない人間を官邸に呼び、福島原発の所長たちにさまざまな素人質問をさせたことで、現場を混乱させた」と主張しました。日比野さんは確かにコンピューターサイエンスが専門ですが、若い時に物理学を修めた立派な物理学者です。 しかし、野村氏にしてみると、原子力工学出身で原子力工学の技術者ないし教授をしていない人は、すべて「専門家でない」のでしょう。
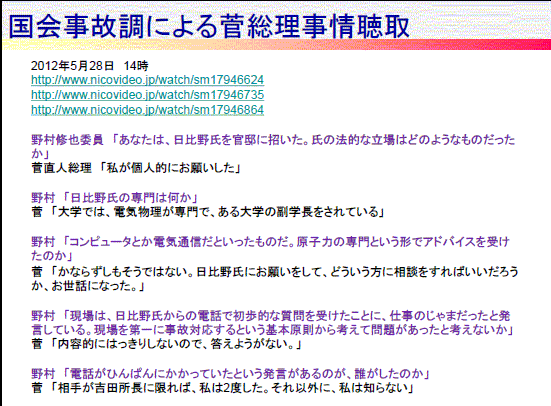
「原子力工学を修めた人以外は、この領域に踏み込むべきでない」という野村氏の意見について、みなさんはどうお考えでしょうか。私は、この原発事故にしても、日本の原子力行政にしても、原子力工学を修めた人だけで、閉鎖的共同体(原子力村)を作ってしまったことのほうが本質的な問題なのだと思っております。むしろ原子力村以外の科学者たちが大いに越境して問題解決に取り組むべきだと考えています。
野村氏は、国会事故調の事情聴取の場で、「管リスク」を声高に叫びました。
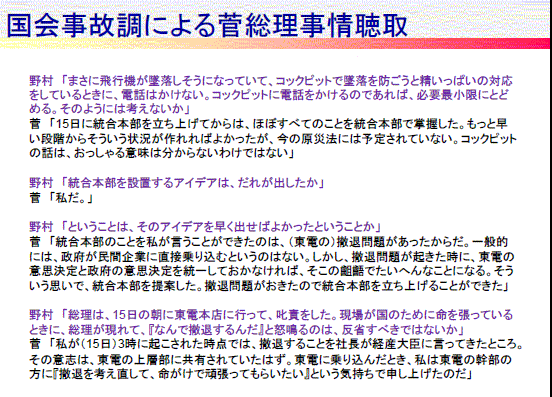
「菅さんが専門家でもないのに専門家ぶったことがこの事故を大きくした」というのです。 しかし、私は、少なくともこの原発事故については、東電の撤退要請を断固として拒んだことで、菅氏は日本を救ったのだと思います。東電の撤退要請に対して、政府や経産省の「専門家」は「撤退やむなし」と結論していたと聞いています。 しかし彼ら「専門家」にしたがって東電が事故現場から撤退していたら、いまごろ東京までも人の住めない地域になっていた可能性がある。 またすでに論証したように、3号機と2号機については、「専門家」こそが、過ちを犯しました。菅氏は、残念ながらその専門家たちに異を唱えられなかった。かくて海水注入がなされなかったということです。
このように分析を進めると、じつは、今回の原発事故の本質は、2005年4月25日に西日本旅客鉄道(JR西日本)が起こし、107人が死亡したJR福知山線事故にとても似ていることに気づきます。
この事故は拙著『JR福知山線事故の本質』で論証したように、「線路曲線を半径600mから304mに変更した際、転覆限界速度が直前の制限速度よりも小さくなる」という科学的真理を経営陣が看過したことに起因します。
地図をみてください。事故現場の線路曲線は、かつて半径600mでした。しかし、JR西日本の経営陣は1996年12月に、半径304mに変更する意思決定をしました。
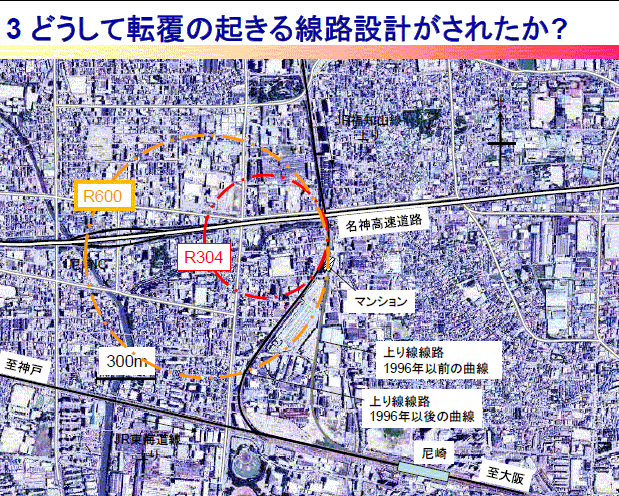
図に示した私の計算によれば、事故時と同様に93人が乗車すると仮定すると、半径600mの転覆限界速度は148km/h。これに対し、半径304mでは106km/hです。さらに半径600mであれば、乗客が288人(事故時の3倍以上)まで乗っていても転覆限界速度は120km/h以上である一方、半径304mの場合は、乗客数が8人以上であれば120km/hを下回ります。つまり、速度120km/hでこのカーブに進入した時、半径600mであれば事実上決して転覆しないけれども、半径304mであれば事実上必ず転覆するということです。
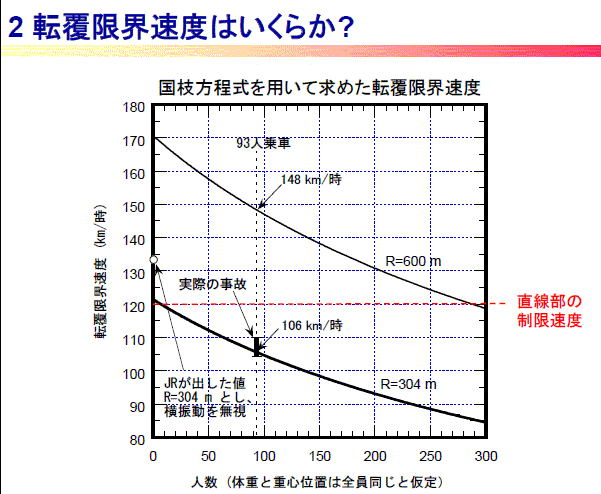
当時、北方の伊丹駅から事故現場まで6.5km続く直線部の制限速度は、120km/h。事故現場の曲線の直前で制限速度は70km/hに転ずる制度設計になっていました。したがって半径304mの場合、直線部を運行する約3分間に運転士が人事不省に陥り、そのままこの曲線に侵入すれば、必ず転覆すると予見できたはずです。ところが線路の設計変更によって、将来、確率1で転覆事故が起きることが、担保されてしまったのです。
ところが経営陣は、科学的考察をすることをせず、難なくその変更を決定しました。「技術には常に『物理限界』が存在する」という科学的真理を理解しなかったからなのです。
科学パラダイムに依拠する技術には常に物理限界があり、その限界が技術の「制御可能」の次元と「制御不能」の次元との境界を特徴づけます。そして、境界を超えると、列車は転覆し、飛行機は墜落し、原子炉は熱暴走するのです。従って、技術に立脚する企業は、その境界の位置と特徴、構造を根本から知悉しておく必要があります。しかも、境界を超える「想定外」の事象が起きたら、経済性を超えてリスクを最小限に抑えることに専念しなければならないのです。
(1) 本件の記事のより詳細は、下記の報告書、特にその第1章(執筆:山口栄一)を参照ください。
『FUKUSHIMAレポート - 原発事故の本質』、水野博之、山口栄一、他(FUKUSHIMAプロジェクト委員会)、日経BPコンサルティング刊、2012年1月30日刊行、504ページ、定価900円(+税)
なお、事故の2ヶ月後 (2011年5月13日)に、著者は本件の原形であるつぎの記事を発表しています。
「見逃されている原発事故の本質 -- 東電は『制御可能』と『制御不能』の違いをなぜ理解できなかったのか」、山口栄一、日経ビジネスオンライン、2011年5月13日。 http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110510/219895/
「福島原発事故の本質 -- 『制御可能』と『制御不能』の違いをなぜ理解できなかったのか --」、山口栄一、『日経エレクトロニクス』、2011年5月16日号 (2011年5月13日発刊)、pp. 82-89。
この記事の2日後(5月15日)に、東電は(それまでの発表を一変させて)「(シミュレーションによれば) 1号機は津波到着後の比較的早い段階において、燃料ペレットが溶融し。圧力容器底部に落下したとの結果が得られた」と発表した。この発表の問題点、また、この発表をマスメディアが誤って事実と認識して報道した(ほとんどの全国民がそう信じさせられた)ことの問題点などは、上記の『FUKUSHIMAレポート』を参照されたい。
著者は、(旧知であった)日比野靖(JAIST副学長)から、2011年11月4日に一通のメールをもらい、その後同氏にインタビューができたという。その詳細も『FUKUSHIMAレポート』に記録されている。
(2) 福島原発事故に関連しては、多くの書籍、Web情報、などが発表されておりますが、それらのうち以下のものが参照しやすいものと思います。
民間事故調関係:
・ 『福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書』、一般財団法人日本再建イニシアティブ、(株)ディスカヴァー・トェンティワン刊、(2012年3月11日)、412頁、定価 1575円。
・ 一般財団法人日本再建イニシアティブのWeb サイト中のFUKUSHIMAプロジェクト: http://http://rebuildjpn.org/fukushima/
国会事故調関係:
・ 『国会事故調 報告書』、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、(株)徳間書店刊、2012年9月30日、592頁、定価1600円+税。
政府事故調関係:
・ 『福島原発で何が起こったか 政府事故調技術解説』、淵上正朗、笠原直人、畑村洋太郎、B&Tブックス、日刊工業新聞社刊、2012年12月25日、206頁、定価 1400円+税。
・ 『福島原発事故はなぜ起こったか 政府事故調核心解説』、畑村洋太郎、安部誠治、淵上正朗、講談社刊、2013年4月20日、208頁、定価 1300円+税。
全般:
・ 『4つの「原発事故調」を比較・検証する − 福島原発事故13のなぜ?』、日本科学技術ジャーナリスト会議、(株)水曜社刊、2013年1月6日、定価 1600円+税。
・ ウィキィペディア: 福島第一原子力発電所事故、 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島第一原子力発電所事故
・ ウィキィペディア: 福島第一原子力発電所事故の経緯、 http://ja.wikipedia.org/wiki/福島第一原子力発電所事故の経緯
なお、海外の国際機関が、多角的に分析した資料を、一般の人にも分かりやすく公表しています。私はきちんとサーベイしたわけでありませんが、次のような記事とビデオが有用であると思いました。
International Atomic Energy Association (IAEA): 'Fukushima Nuclear Accident', http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/
World Nuclear Association: ’Fukushima Accident 2011’, http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Fukushima-Accident-2011/
IRSN (フランス) Webサイト: ’The Fukushima Accident', http://www.irsn.fr/EN/publications/thematic-safety/fukushima/Pages/overview.aspx
IRSN (フランス) Webサイト: ’Analysis by IRSN of the Fukushima Daiichi accident of March 2011’ ビデオ: http://www.irsn.fr/EN/popup/Pages/fukushima-video-2-years.aspx (69分)
(3) 東京大学学生キリスト教青年会(略称:東大YMCA)は、1888年(明治21年)に創設され、東京大学の学生の間にキリスト教を宣べ伝えることを目的にし、また、社会的な活動をした125年の歴史を持ちます。東大農学部正門のすぐ前に会館兼寄宿舎を持ち、20人前後の学生が、勉学と信仰を中心とした学生生活を送っています。http://todaiymca.blogspot.jp/
私は、理学部化学科3年の4月から、大学院博士課程1年の7月まで、4年余をこの寮で過ごしました。多数の同期、および先輩・後輩の人たちとともに、充実した学生時代を過ごせたことを感謝しています。私は、19歳〜27歳頃に教会生活をしておりましたが、その後は教会から離れております。それでも私の心にはキリスト者としての土台があるものと思っております。(「「中川 徹のミッション・ステートメント」 と その心」 (中川 徹、2010. 1. 3) )。
)。
この寄宿舎では現在空室があり、随時入寮者の募集をしております。入寮資格は、「東京大学学部もしくは大学院の男子学生にして、キリスト者あるいはキリスト者たらんとする者」です。お知り合いの方にお薦めいただけますと幸いです。
(2013. 9.20)
(2013.10. 3)