アルトシュラーの 76の標準解から 新しい111の標準解へ
Davide Russo* and Stefano Duci (ベルガモ大学、イタリア)
第13回 ETRIA TRIZ Future 国際会議 (TFC2013)、 2013年10月29-31日、Ecole Nationale d'Arts et Metiers of Paris、 パリ、フランス
和訳: 高原 利生 ( )、中川 徹 (大阪学院大学)
Press the button for going to the English page.
編集ノート と 論文紹介(中川 徹、2014年 4月27日)
本件は、昨年10月末のETRIA(欧州TRIZ協会)主催の国際会議
で発表されたものです。その国際会議で発表された優れた論文数編を和訳掲載したいと考え準備してきました。本件はTRIZ自身の方法に関する論文として、非常に明快で優れたものです。高原利生さんが和訳をしてくださり、中川が推敲させていただいて、ここに和訳の論文とスライドを掲載いたします。なお、英文での論文もスライドも著者からは掲載の許可を得ているのですが、ETRIAが出版社からのWeb掲載を模索中で掲載許可が得られていないため、中川による紹介だけを掲載しています。[英文論文を読みたい方は、著者に直接依頼されるのも一法ですが、あるいは、ETRIAの会員になって(40ユーロで5年間有効)、ETRIAサイトに会員限定で開示されている従来からの全論文へのアクセス権を得るのが得策です。]
この論文で扱っていますのは、アルトシュラーが開発した、「物質―場モデル」と、それをベースにした「76の発明標準解」についてです。アルトシュラー後のいろいろな研究者のアプローチをも検討したうえで、著者らは独自にきちんとした概念整理をし、明快で分かりやすい新しい体系をつくっています。その体系は、すっきりしていて、非常に使いやすいものです。
(1) アルトシュラーの「物質―場モデル」の特異的な表現(三つ組み表現)に固執せず、もっと一般的に普及し理解されている「機能分析」での表現を用いる。ただし、多数の構成要素の関係を考えるのでなく、問題システムの中心部分での二つのオブジェクト(「物質」)とその間の作用(相互作用、機能)に考察の焦点を絞る。
(2) アルトシュラーの「発明標準解」は、このように焦点を絞ったときの、問題状況とその解決策のヒントを網羅・分類しようとしたものである。本論文は、その考え方を受け継ぎ、「76の標準解」に取り込まれているすべての情報を漏らさずに、再整理する。再整理にあたっては、分類の分かりやすさ、各標準解の理解しやすさ、記述の構造の明確さと均一性、などを趣旨とした。
(3)まず基本の分類は、「問題状況」で大きく区分した。その中心は、上記の二つの物質(オブジェクトとツール)の間の作用についての問題状況である。この作用が、「有害または過剰」(だからその作用の効果を減らす必要がある)の場合と、「不十分または欠如」(だからその作用の効果を増す必要がある)の場合とがある。(この他に、測定・検出の問題と、まだシステムが未完成の場合があるが、重要でない。)
(4) そのつぎには、各問題状況に対して、可能な解決策を簡潔な動詞で表現し、それを「アクション」と呼んだ。例えば、有害な作用に対しては、「そらせる」、「ブロックする」、「出せなくする」、「感じなくする」、「他のシステムと組み合わせる」、「有害でなくす」の6種にまとめた。不十分な作用に対しても、対応する6種にまとめた。
(5) 上記の各アクションに対して、その主要手段を分類し「サジェスチョン」と呼んだ。例えば、有害な作用をそらせるためには、新しい物質を(ツールとオブジェクトの間に)導入するか、新しい場を(有害な作用の場に介入して)導入するかである。このような高い抽象化のレベルでは、サジェスチョンは、各アクションに対して、2個または3個にしか過ぎないことが分かった。
(6) これらの「アクション―サジェスチョン」による解決策の指針をより具体的にするノウハウが「76の標準解」には多数含まれている。その具体化、詳細化は、大きく言うと、4テーマに分けられる。すなわち、「物質を付加/導入するやり方」、「物質を修正するやり方」、「場を付加/導入するやり方」、「場を修正するやり方」の4種であり、これらをまとめたものを4つの「クラウド」と呼んだ。各クラウドは、複数の「アクション―サジェスチョン」から呼び出される。(このようにまとめて「呼び出し」の形式にすることで、記述の重複をなくし、分かりやすくなった。)さらに詳細はこのクラウド内での、注記の形にして、元の標準解に含まれる記述レベルの不均一を、吸収した。
(7) 以上に述べた概念と構成法に従って再整理し、新しく提唱する(ベルガモ大学方式の)「111の標準解」の全体構成は、以下の図のように表される。
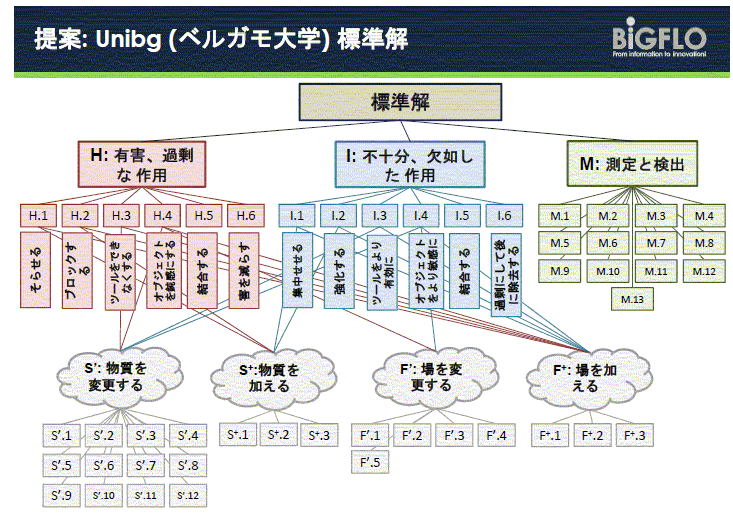
(8) この方式による標準解の一つの記述(下の図の左半分)とその簡単な事例(図の右)を例示する。この左側の記述は順に、「アクションH.2」(最初の2行)、「サジェスチョン S+」(次の2行)、「(機能分析の表現による)物質―場モデル」(図式)、「S+ クラウド内のヒント S+.2」(2行)、そして[注」の形の詳細なヒント(7行)、である。事例の例示は、分かりやすい。
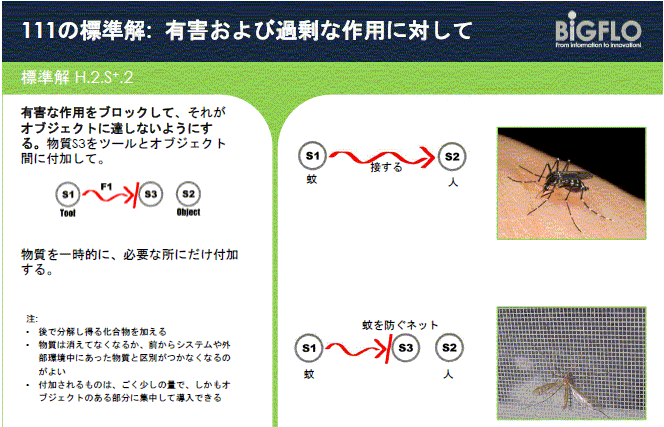
*** 以上に説明したように、非常に分かりやすい体系であり、一つ一つの標準解の記述である。著者らの論文は、従来の研究をきちんと踏まえたうえで、新しい提案を明確に出しており、素晴らしい研究論文であると思う。物質―場モデルと発明標準解という、TRIZにおける一つの重要な方法(アルトシュラーが1975年〜1985年の10年間にわたって開発した方法)が、ここに「現代化」され、非常に使いやすい体系になったのは、TRIZの発展にとって大いに意義深いことであると思う。著者らをはじめイタリアのTRIZグループに感謝し、エールを送ります。(ベルガモ大学のTRIZグループの状況は、著者らのスライドに記述されています。)
英文 論文 PDF (公開許可待ち、リンクなし)
英文 スライド PDF (公開許可待ち、リンクなし)
論文の目次
3.1 G. アルトシュラー後の批判と改良
3.2 標準解の情報4.1 標準解の新しいクラス
4.2 新しい 標準解セットの利用の実用的な例
| 本ページの先頭 | 論文の先頭 | 1. はじめに | 2. 物質―場分析 | 3.アルトシュラーに標準解 | 4. 提案 | 5.比較 | 6. 結論 | 参考文献 |
| 論文紹介(中川 徹) | 論文PDF |
スライドPDF |
ETRIA TFC2013報告 |
英文論文(未) | 英文スライド(未) |
発表論文
アルトシュラーの 76の標準解から 新しい111の標準解へ
Davide Russo* and Stefano Duci
(ベルガモ大学、イタリア)和訳: 高原 利生 ( )、中川 徹 (大阪学院大学)
TRIZ Future 2013 (欧州TRIZ協会(ETRIA)主催 国際会議)、
2013年10月29-31日、ANSAM、パリ概要
G. アルトシュラーの76の標準解は、一般的な発明問題の解として創られている。これが創られて以来、多くの著者が、この標準解を正しく使う際のいくつかの困難や修正の必要性を指摘して、改良に取り組んできた。本稿で新しい111の標準解の組を提案する。それは、簡易で厳格な機能アプローチを使って、アルトシュラーの標準解の情報を再構成したものである。この新しい標準解は、有害作用、不十分作用、測定と検出の問題という三つのマクロクラスに分けられる。各標準解は、機能的目的を指し示す「アクション」(例えば、有害作用を“ブロックする”・“そらす”など、不十分機能を“集中させる”・“強化する”など)と、目標を見付ける方法を示す「サジェスチョン」(物質と場を付け加えたり修正したりする提案)とから構成される。従来の標準解とこの新しい標準解との比較を示す。
キーワード: 標準解, TRIZ, 機能
1. はじめに
76の標準解は、TRIZの良く知られた非常に強力なツールである。これはG. アルトシュラー [1]によって、1975年から1985年の間に、特許の研究から抽出した一般的発明問題の解として、創られた。これら標準解は、技術システム進化の法則から直接得られたもので、技術システムの合成と変換をガイドし、技術的矛盾を暗黙的に解消する[2]。実際には、普通、ARIZ (発明問題解決のアルゴリズム) [3] において、物質−場分析の一部として、物質−場モデルを作り、解に対するすべての制約を特定した後に用いられる[4]。.
物質−場モデルと標準解はどちらも、疑いなくイノベーションに効果的なツールであるにもかかわらず、その利用はいくらか限られたものになっており、特に企業や西側の大学では限られている。その理由はさまざまであり、翻訳者の解釈の影響[5]から、方法そのものの欠点までいろいろである。[6, 7]
多くの著者がこのギャップを埋めようと試みてきて、標準解を適切に適用する際のいくつかの難しさを指摘し、経験の少ないユーザーにも魅力的にしようとしてきた。こうしてこの強力なツールを修正するニーズが生まれた。TRIZ専門家たちの多くの人々 (例えばV. Petrov, V. Souchkov, N. Khomenko, A. Smirnov, I. Belski, Z. Royzen, S. Savransky その他) が、この道を進んできた。その中のある人たちはガイドラインや新しい分類を定義し、他の人たちはこの標準解から出発して、あるいはこれと他のイノベーションツールを結合して、新しい方法を作りあげている。本稿は、もとの76 の標準解を再定式化し、111の標準解の新しい体系として強化することを目指す。これは、使いやすさと柔軟性を改善し、G. アルトシュラーがその広範な研究の中で確定した標準解を少なくとも同数維持したままにする。
2. 物質−場分析
物質−場分析は、TRIZの方法の一つであり、物質−場モデル作成フェイズ、抽象的解決フェイズ、および解釈フェイズで構成される[8]。このアプローチはTRIZの考え方と合っている:それは、問題を高い抽象度で解くこと、特定の技術分野にこだわらず、先行する同様な問題に対する知識を活用すること、を提案している。
この方法の一部として、物質−場モデルは技術システムを図的に表現したものである。これは三つのコンセプトで表現される:すなわち、物質、場、相互作用である(図1参照)。
図 1 物質−場モデルのオントロジー(の一部) [8–10].
もともとの物質−場モデルでの用語は、本稿で用いている用語と随分違っている。本稿では、機能分析とツール−オブジェクトープロダクトモデル[11] の一般的な解釈を反映している。物質−場モデルは76の標準解を説明するのに用いられているから、これらの差異が幾分の曖昧さをもたらす恐れがある。特に、もとの記法 (図2の左) において、点線は「問題の特定によって導入されるべき作用(または相互関係)」を意味し、一方、波線は「問題の特定により置き換えられるべき不十分な作用(または相互関係)」を意味する[9]。この定義によれば、 機能分析の記法 (図2の右) における過剰な作用、不十分な作用、有害な作用は、もとの波線の作用のサブクラスとなる。
図2 もとの 物質−場 モデル の記法(左)と機能分析の記法(右)
物質−場の三つ組 (つまり完全な物質−場)の定義については、もっと混乱を引き起こす。 もともとの三つ組のコンセプトにおいて、アルトシュラーは、一つの場と二つの物質 を描いたのだが、彼はまた二つの物質間の相互作用のための第二の場をも含意していた。実際、[9] からとった一つの例では、覆いつきの楔デバイスを示しており、楔 S1 と楔の覆いS2とからなり、楔の除去を容易にする設計になっている。楔は二つの部分で構成されていて、その一方は簡単に融ける。熱の場 F1がS2に作用し、物質 S1とS2間の力学的な作用F2を変えることで [S1に作用する]。アルトシュラーのアプローチによれば、物質間の相互作用は、その相互作用の形式の詳細を描くことなしに示される。(図 3参照)
図 3 アルトシュラーの三つ組記法 [9].
このようにして、彼は、直接に制御可能な場に焦点を当て、それをどのようにして作るかには言及しなかった。この十年間、何人かのTRIZ専門家たちが物質−場の三つ組を機能分析とより調和した方法で使ってきて [10, 12]、場F1を物質間の場として使っている (図 1参照)。本稿では、採用した記法は機能分析の記法と同様であるが、もともとの標準解についての解釈では、両者の視点をともに考慮している。
3. アルトシュラーの標準解についての議論
最初の5つの標準解が1975年にG. アルトシュラーによって開発された [13]。それらは理論的な説明をつけて提示されたが、分類されてはいなかった。おおよそ二年の間に標準解の数は5から10に増えた[9]。
標準解の開発に質的飛躍があったのは1979年のことであり、28の標準解からなる体系が出版されたときである[14]。その体系は三つのクラスで構成されていた。システムを変更する標準解、検出と測定の標準解、そして、標準解の利用についての標準解である。
二番目の重要な改善は1981年のことで、発明の標準解の数は50になった。同じ3つのクラスであるが、サブクラスをより論理的に整理したものである。やがて、現行の番号システムが採用され、通し番号から構造的な番号に変えられた。そのシステムは、3つの数で組み立てられている:クラスの番号、サブクラスの番号、そして各サブクラスでの標準解の番号である。クラスの数は1985年まで変わらなかったが、1985年に76 の標準解からなる現行のシステムが提示された[1]。それは5つのクラスで構成されている [2]:
1. 物質−場モデル(SFM)の構築と解体
2. 物質−場モデル(SFM)の進化
3. スーパーシステムやミクロレベルへの移行
4. 検出と測定の標準解
5. ヘルパー3.1 G. アルトシュラー後の批判と改良
1985年以降、標準解のシステムはTRIZ社会から批判され、いくつかの欠点が浮かび上がった 。
- 5つのクラスを持つ標準解の構造は、利用のしかたを複雑にし、3つのクラスだけのシステムより論理性が欠けるように見える[7, 13]。
- 多くの標準解は、技術システムの進化トレンドに等しいが、システム発展の法則のすべてから得られた結果ではない[6, 13]。
- 標準解のシステムは、知られている物理的、化学的、生物学的、幾何学的効果のすべての分野で適用されたわけではないし[13]、拡張も困難である。
- それは不均一である[6]:いくつかの標準解は、より一般的な標準解の特殊な場合であり、その結果、繰り返しが度々ある。特に、磁場の導入が強調されすぎているが、磁場は場の導入の一例に過ぎない。
- ほとんどの標準解は物質−場モデルでモデル化可能だが、いくつかのものは物質−場の記法の範囲を超えている。
- さらに、さまざまな標準解の定式化と構造は異なっており一貫性に欠ける。
- 最後に、この種の分類は、特定の問題に対して適切な標準解を選択するためのガイドとして、必ずしも適当でない。解のタイプを分類するのでなく、問題を同定するクラスを使った新しい分類をつくるべきである。これらの前提を出発点にして、76の標準解のシステムを改善するための多くの努力がなされてきた。多数のTRIZ専門家たちが、この問題をいくつかのやり方で取り組んできた。
- 最初は、フロ−チャートの形の指針が開発され、一般的または特定の状況での標準解の利用を容易にすることを目指した[15, 16]。
- その後、もっと根本的な提案がいくつか行われた。例えば、V. Petrov は、標準解を、システムの進化の法則のメカニズムと解釈することによって、一般的なモデルのシステムを作った[17]。
- 他の著者たち [7, 18, 19] は、簡潔な標準解の独自のセットを作りあげた。特に、彼らは、標準解の数を減らし、クラスの数も減らした。クラスは次の三つになった:変更なしまたはわずかの変更によるシステムの改善;解の変更によるシステムの改良;検出と計測、である。
- Ogot はまた、異なったモデリングツールを示唆した。エネルギー−物質−信号モデル [20]である。効果のない番号付けを置き換えるために、Kimは、問題状況と解の双方を表す新しい記法を示唆した [21]。
一方でGadd [12] は、標準解を再定式化し、次の3つのクラスに再分類した:有害な場合の24の解;不十分な場合の35の解;測定のための17の解である。
- 同様にMann [22] は、次の4つの標準解のクラスを提案した:不完全な物質−場;測定/検出問題;有害効果;不十分/過剰な関係である。以上に述べた提案のすべては、標準解の古典的な分類と定式化についての大変効果的な改善である。しかし、それらのいくつかはもとのアルトシュラーの考えから遠く離れてさまよっていた。それらは 、標準解と物質−場モデルとの間の強いリンクを弱めたが、このリンクこそアルトシュラーの最も偉大な発見の一部なのであった [23]。さらに、標準解の利用を簡易にする目的で、彼らは標準解に含まれる情報の総量を減らしたり、このイノベーションツールの柔軟性を減らしたりした。
3.2 標準解の情報
標準解の分析からわれわれは、これが問題記述と問題解決の両方を実施するための情報を持っていることを観察できる。問題記述の部分が、目的と制約と初期条件を使って問題を一般的に定義し、一方、問題解決の部分が、解決策のための示唆を含む。これらの情報はテキストや物質−場の図の形で見いだされる。これらのすべての情報は、標準解のもともとのシステムにおいて構造化されている (図4参照)。
一つの標準解は、そのクラス、サブクラスと本体で定まる。「測定と検出の標準解」を例外として、すべてのクラスとサブクラスは、それが導く解のタイプに応じて名前が付けられている。だからこれらの名前は、解へのテキストによる示唆であるとみなせる 。
標準解の本体は、目的および/または初期条件を規定する第一の条件を含む。第二の条件、そしてときにはさらに第三の条件が、問題の制約条件を特定するのに用いられる。本体の残りは、解への示唆、目的、初期の物質−場モデルと解の物質−場モデルの図的表現、そしていくつかの例、を含む。
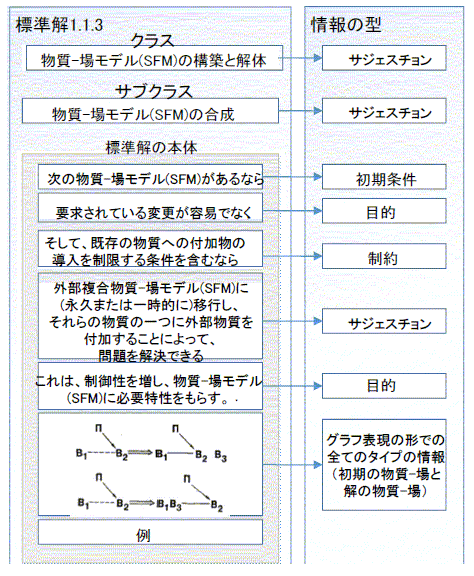
図4. もとの標準解システムにおける標準解 1.1.3の情報の型
標準解に含まれる情報は断片化されていて複雑である。その結果として、標準解の解釈と読みは難しい。標準解の利用は、初期条件に応じて与えられ、それは「 if <条件> then」の文として表現される。このアプローチは効率的でなく面倒である。実際多くの著者が、標準解の応用を簡易化するアプローチを提案してきており、機能ダイヤグラムに基づいた外部シェーマを提案している [24]。しかし、もとのシステムに含まれるすべての情報を組織化し、クラス 「ヘルパー」の適正な利用を管理するのに、多くの困難が報告されている。
4. 提案:標準解の新しい分類
本稿で提案する新しい分類は、物質−場モデルと標準解の間の関連を強化することを目指している。それは、柔軟性と使いやすさの改善を目的とし、もとの標準解に含まれている、解を見つけるあらゆるパスとその他の情報(制約、条件など)を保存したままにする。
それは直観的な機能的アプローチに従っており、三つのマクロクラスから構成される。
I: 不十分および欠如した作用に対する標準解 (49 の標準解で、6の 「アクション」に分けられる);
H: 有害および過剰な作用に対する標準解 (49の標準解で、6の「 アクション」に分けられる);
M: 測定と検出のための標準解 (13 の標準解).
すべての標準解は、はっきり定義された構造を持っている。第一の部分は「アクション」である。それは、動詞と目的語からなり、解へのパスを特定する。例えば、有害な作用を除去するためには、それをブロックする、そらす、ツールをその生成ができないようにする、などができればよい。
第二の部分は「サジェスチョン」と呼び、「アクション」を実現するために、物質−場モデル上に起こすべき変化を特定するヒントを含んでいる。例えば、有害な作用をブロックするためには、ツールとオブジェクト間にある物質を加えることができる。その物質はシステムの内部か外部かに見つけられ、永続的にあるいは一時的に加えることができる、等々。サジェスチョンは、従来の標準解システム全体(「ヘルパー」を含む) からのヒントを含んでいる。
[訳注: 原論文では、新しく提案する標準解の第一の部分を「Action」と大文字で書いており、この和訳では「アクション」と記述する (最初は「 」付きであるが、後の方ではつけない)。また一方、物質−場モデルにおける機能(相互作用)のことを、原論文では「action」と小文字で書いている。この和訳では、通常「作用」と記述する。紛らわしいが、このように区別して理解いただきたい。]
各標準解はすべて、一つのアクションと一つのサジェスチョンから構成されている。
標準解の管理を簡単にするために、サジェスチョンを4つの「クラウド」にグループ化した::
S+: 物質を追加する (3サジェスチョン);
F+: 場を追加する (3サジェスチョン);
S’: 物質を修正する (12サジェスチョン);
F’: 場を修正する (5サジェスチョン).
これらの 「クラウド」は必要なときに呼び出すことができ、一般化した物質−場モデルを修正するためのガイドラインを含んでいる。この意味で、一つのアクションは一つ以上のクラウドとリンクをすることができ、標準解のサブクラスの全体を形成する (図5参照).
図5 標準解を再グループ化するための「クラウド」の利用 (サブクラス H.1)
この構造は、システムに負担をかけずに、単純さと完全性を兼ね備えている。利用者は可能なアクションについての全貌を容易に理解し、問題を解決するのに最も適切なパスを選ぶことができる。さらに、特定のクラウドを参照することにより、そのサジェスチョンを深めることができる。
4.1 標準解の新しいクラス
「不十分および欠如した作用に対する標準解」(I) のクラスと、「有害および過剰な作用に対する標準解」(H) のクラスは、不満足な作用を持つ問題一般へのアプローチのために設計されている。この分類は、問題状況を特定して、不十分な作用、欠如した作用、有害作用、あるいは過剰作用と分かりさえすれば、直ちに標準解のシステムに入り込めるように、検討されてきた。
新しさは、問題に介入する方法の定義のしかたにあり、「ブロックする」、「そらせる」などの動詞を使うことである。有害な作用から不十分な作用に移ると、その動詞が目的とともに変化することである。例えば 、「ブロックする」が「強化する」になり、「そらせる」が「集中させる」になる、など。その結果、クラス Hのアクションとクラス Iのアクションには論理的な対称性がある。
有害作用と過剰作用は、同様に取り組める。なぜなら、それらは一つの作用の効果を減らすという同じ目的を持つからである。不十分な作用と欠如した作用についても、それらが一つの作用を改善するという目的を共有しているから、同様の考察をできよう。しかし、クラスIは、また、プロダクトを得るに際しての制御性、効率性、困難さという問題をも持っている、つまり、より総括的な欠陥のある問題である。
両方のクラスは6つのアクションの組で定義でき、図6で示される。それらによって、利用者は、解へのパスの全体像を把握できるようになる。さらに、それらは特定の「クラウド」を呼び出すことによって展開できる。この創造的プロセスとアクションの解釈は、解のグラフ表現によってサポートされる。
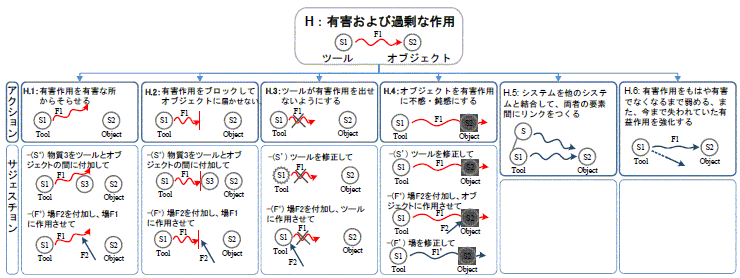
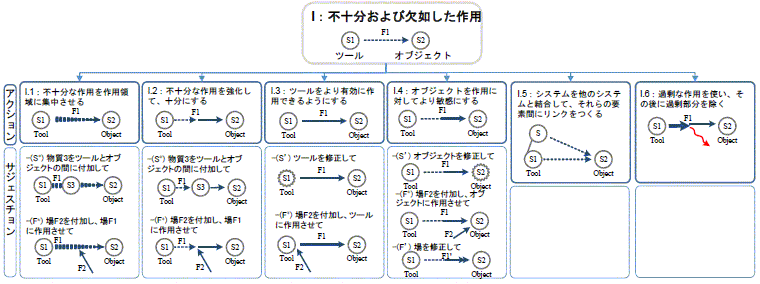
図6 有害作用(左) と不十分な作用 (右)の問題のためのアクション
[訳注: 大きな図です。A4で印刷することを想定して本Webページをつくっています。明細はスライドのPDFを参照ください]
もとの標準解のシステムにおける測定と検出のためのクラスは、諸文献においてTRIZコミュニティからあまり批判されていないようである。それはよく整理された標準解のセットになっている。このため、新しいクラス 「測定と検出のための標準解」 (M) はもとのものに大変よく似ている。しかし、順序は維持されているが、個々の標準解の構造は調整されていて、一つのアクションと一つのサジェスチョンから構成され、サブクラスを持たない。例えば、従来の標準解 4.2.2 は、「もし、システム(またはその部分) が測定と検出をもたらさないなら、問題は、容易に検出できる添加物を導入することにより、内部または外部の複合測定物質-場モデル(SFM)への移行により解決できる」である。これに含まれる情報は、新しい標準解 M.5中に含まれる。すなわち、「オブジェクトを容易に検出できるようにする−容易に検出できる添加物を導入することにより」である。
4.2 新しい 標準解セットの利用の実用的な例
工業用サーキットブレーカーのケースで、アーム(これはメカニズムの一部である)の動作を瞬間的に止めるためにピンが使われている。衝撃の圧力が加えられると、ピンが壊れて、その機能が停止する可能性がある。ピンの破壊を避ける解が必要である。
問題状況の物質−場モデルは、「アームがピンに対して有害な作用 (「壊す」) を作用させている」として描くことができる。作用が有害だから、クラスH が使える。そこで、図6上を参照して、 問題を解決するかもしれないアクション6つを読むことができる。いくつかの解が、いかなるサジェスチョンの助けもなしに、容易に出てくる。例えば:H.1 -> 有害な作用を、他の要素(犠牲になる/代替の要素)にそらすことができる。こうして、その要素が壊れたとしても、ピンはその機能を実現するだろう。
H.2 ->有害な作用を、アームとピンの間 [に入れた] 一つの物質でブロックすることができる。物質が衝撃を分散させるようにする。
H.3 -> ピンを壊さないように、アームを変更することができる。衝撃を減らすようにアームを設計できるだろう。
これらの解は非常に抽象的であり、もっと具体的な結果を得るように詳細化する必要がある。今のところ、このフェーズで深く検討すべきベストの解がどれかを選択する効果的方法はない。しかし、問題の制約を考慮し、より一般的に検討することにより、直観的に解を詳細化することが有用であろう。
この例では、われわれは解への第三のパスを検討する。それはアクションH.3から見つかったものである。そこでわれわれは、サジェスチョン (クラウドに編成されている)を見て回り、より具体的な解を導くことを目指す。
「(S’) ツールを修正することによる」に関する諸サジェスチョンを読み、われわれは柔軟な物を使用することについて有益なヒントを得る。「S’.6:物質の動性の度合いを上げる。システムをより柔軟で急激に変化する構造に移行することにより。(注:物質を動的にするには、物質を二つの部分に分割してジョイントすることから始めて、つぎの線に沿って進めていく:一つのジョイント –-> 多くのジョイント –-> 柔軟なオブジェクト)」。 このサジェスチョンは、一つの柔軟な部分または一つのジョイントを持つアームに導く。
同様に「(F+) ツールに作用する場を追加することにより」に関する諸サジェスチョンを読んで、われわれはもう一つの有用なヒントを見つけた。「F+.2: 高いレベルの制御性を持つ場を検討せよ。磁場や電場など」。このサジェスチョンは、アームの動作を磁場で遅くするという解を導いた。
この問題の解は、例えば、これら二つの解を同時に適用することかもしれない。つまり、柔軟な部分を持つアームで、ピンに衝撃を与える前に磁場で動きを遅くさせるようにしたもの。つきつめて言うと、アクションは、極めて抽象的に、可能な解を特定するのに有用である。そのつぎに、少しの検討の後、種々のサジェスチョンに含まれるヒントに従い、解をもっと詳細に展開しないといけないかを決めることができる。
5. 比較
111の標準解は、アルトシュラーの標準解の中に含まれている情報を秩序立てる意図で設計されている。それで、76 の標準解のすべて (一つを除き) は新しい標準解の体系に含まれている。
もとの標準解のシステムは、しばしば、一つのタイプの問題に対してだけ示唆を提供する。新しいシステムは、一つの示唆を問題の目的によって、異なった動詞形を用いてヒントを再定式化して、振り分けている。例えば、もとの標準解 1.2.1 は、有害な作用のために定義されているが、新しい標準解ではこれを不十分な作用にも用いることを薦める。それで、もしある作用を 「ブロックする」のに一つの物質を使えるなら、同様に、それを「強化する」のに一つの物質を使える(増幅器)。
もとの標準解セットのいくつかのヒントは、意味の類似性に従って統合された。例えば、「既存の物質を変更したものを導入する」 (1.2.2) と「外部環境を一つの物質として導入する」 (1.1.4) は、より一般的な新しいサジェスチョン 「物質を見つけ、創る」の一部になる。
もとのいくつかの標準解で、非常に特殊な示唆を提供するものは、新しいシステムでは事例や注の形で含めた。これは、標準解の有効性のレベルを均一にし、より同質な示唆を与えるようにするためである。例えば、標準解のサブクラス2.4は、強磁性物質と強磁場の利用を参照するが、これは解への一般的なパスとして確保するには明らかにあまりに特殊すぎる提案である。
アルトシュラーの標準解では、すべての制約条件を最初から考慮に入れることが想定されている。一つの標準解を利用することは、「if <条件> then」で表されるその標準解自身の適用条件と密接に関係している。この方法では、利用者は標準解システムの全体をくまなく 探し回って、自分の問題を解くための最適な示唆を見つける必要がある。
ここに新しく提案した標準解システムでは、制約に関わる条件が取り除かれている。特に、分類自身が条件に取って代わっている。利用者は、自分の問題の機能モデルに応じて標準解システムに入り込め、適切な標準解の組を直接参照できる。
標準解の数は76から111に増えたが、それらはわずか25のアクションにグループ化されていて、完全さと単純さを同時に実現している。アクションは、解を見つける可能なパスの全体像をすばやく見ることを可能にしている。必要な場合にだけ、利用者はクラウドを読んでもっと詳細な示唆を参照すればよい。
もとの標準解と新しい標準解の対応を検討して、もとの標準解の情報のすべてが新しい標準解中に存在することが確認されている。ただ一つの例外は、標準解 1.1.1である。この標準解は、新しい機能の創生を示唆しており、新しい標準解システムに適合しない。このタイプの問題には、いくつかの全体的方法が開発されている [25]。
6. 結論
本稿では、111の発明標準解の新しいシステムを提案した。これはアルトシュラーの76の標準解に含まれている情報を詳しく分析して得られたものである。
この新しいシステムは、各標準解の利用を簡単にし、機能的アプローチ に一層適合し、経験の少ない人にも一層魅力的なものにしている。
各標準解の構造を、一つのアクションと一つのサジェスチョンに分ける。これにより、問題の克服のために標準解の全セットを読む必要はもはやない。実際、アクションの動詞形をチェックするだけで、標準解の全体を読まないでも、解が見つけられることがしばしばあり、その結果、時間と労力を節約できる。
解を見つける種々の新しいパスが、標準解の新しい組織化を通じて指し示された。それらは、もとの標準解の種々のヒントそのものを検査して、さまざまな目的にマッチさせることで得られたものであり、標準解のシステムを完全にする助けとなった。
7. 参考文献
[1] C. Authors, A Thread in the Labyrinth. 1988.
[2] Y. Salamatov, TRIZ: The Right Solution At The Right Time. 2005.
[3] G. Altshuller, To find an Idea, Publ Nauka, Novosibirsk, p. 1986, 1986.
[4] J. Terninko, E. Domb, and J. Miller, The seventy-six standard solutions, Classes from 1 to 5, TRIZ Journal, 2000.
[5] D. Cavallucci, P. Lutz, and D. Kucharavy, Converging in problem formulation: a different path in design, Proceedings of the Design …, 2002.
[6] S. D. Savransky, Engineering of creativity. 2000.
[7] P. Soderlin, Thoughts on Substance-Field Models and 76 Standards Do we need all of the Standards?, TRIZ Journal, 2003.
[8] A. Bultey, F. B. De De Beuvron, and F. Rousselot, A substance-field ontology to support the TRIZ thinking approach, International Journal of Computer Applications in Technology, vol. 30, no. 1–2, pp. 113–124, 2007.
[9] G. Altshuller, Creativity as an exact science. 1984.
[10] J. Terninko, Su-field analysis, TRIZ Journal, 2000.
[11] Z. Royzen, Tool , Object , Product ( TOP ) Function Analysis, TRIZ Journal, 1999. .
[12] K. Gadd, TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
[13] V. Petrov, The history of development of standards. 2003.
[14] G. S. Altshuller and A. B. Selutskii, Wings of Icarus. 1980.
[15] N. Khomenko, How to use Standard Solution, Triz.ko, 2002.
[16] V. Souchkov, Accelerate Innovation with TRIZ, 1997.
[17] V. Petrov, System of generalized models, 2008.
[18] M. Ogot and G. Kremer, Engineering design: a practical guide. 2004.
[19] M. Orloff, Inventive thinking through TRIZ: a practical guide. 2006.
[20] M. Ogot, EMS models: adaptation of engineering design black-box models for use in TRIZ, Proceedings of the ETRIA TRIZ future conference, no. November, 2004.
[21] S. Kim, Conceptual Design Based on Substance-Field Model in Theory of Inventive Problem Solving, International Journal of Innovation, Management and Technology, vol. 3, no. 4, pp. 306–309, 2012.
[22] D. Mann, Hands-on systematic innovation. 2002.
[23] J. Kowalick, Altshuller’s Greatest Discovery - And Beyond, TRIZ Journal, 1997.
[24] V. Souchkov, Systematic Innovation for technology applications, Course Slides (Bergamo), 2005.
[25] D. Russo, T. Montecchi, and D. Regazzoni, A systematic exploration for conceiving function and behaviour of a new technical system, extras.springer.com.
| 本ページの先頭 | 論文の先頭 | 1. はじめに | 2. 物質―場分析 | 3.アルトシュラーに標準解 | 4. 提案 | 5.比較 | 6. 結論 | 参考文献 |
| 論文PDF |
スライドPDF |
ETRIA TFC2013報告 |
英文論文(未) | 英文スライド(未) |
| 総合目次 |
新着情報 | TRIZ紹介 | 参 考文献・関連文献 | リンク集 | ニュー ス・活動 | ソ フトツール | 論 文・技術報告集 | 教材・講義ノート | フォー ラム | Generla Index |
| ホー ムページ |
新 着情報 | TRIZ 紹介 | 参 考文献・関連文献 | リ ンク集 | ニュー ス・活動 | ソ フトツール | 論文・技 術報告集 | 教材・講義 ノート | フォー ラム | Home Page |
最終更新日 : 2014. 4.30 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp