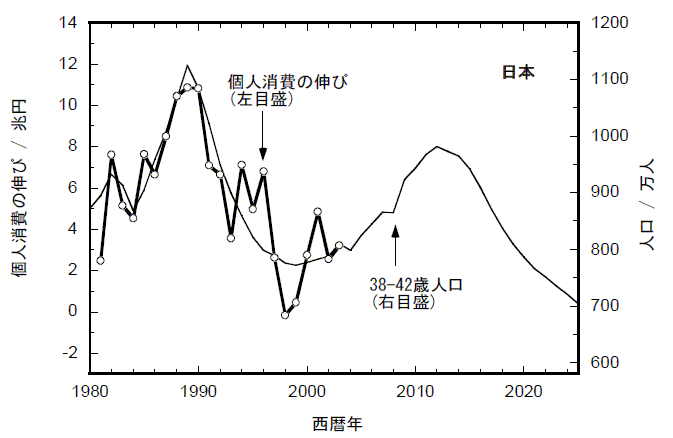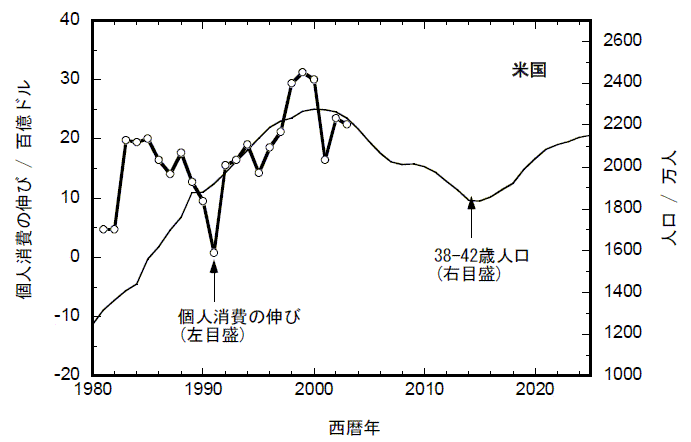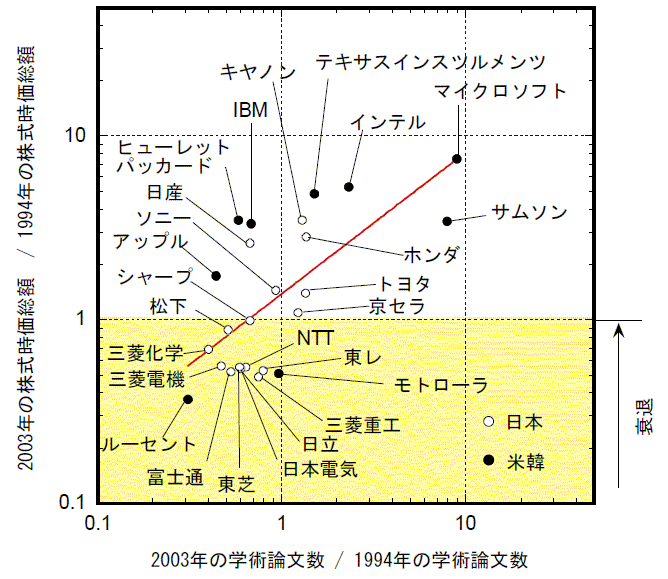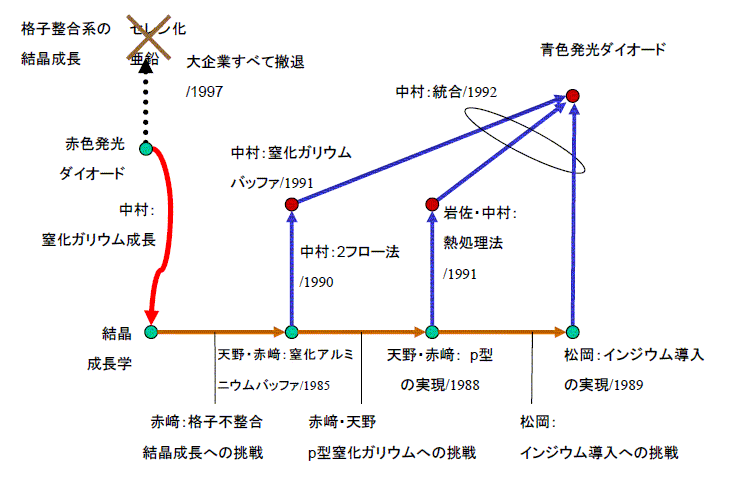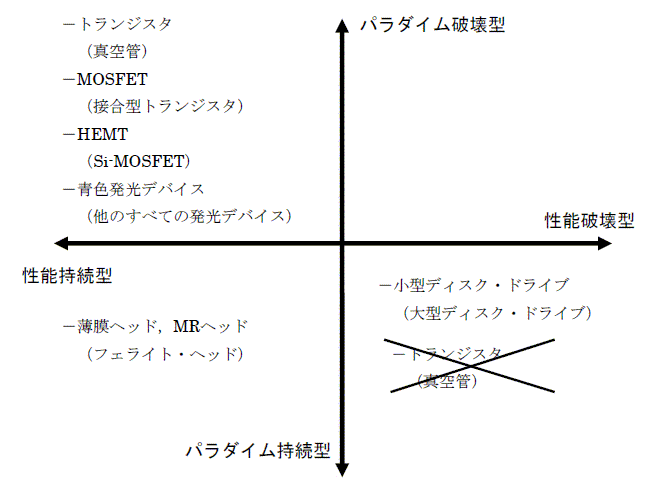Innovation 論文 Innovation 論文 |
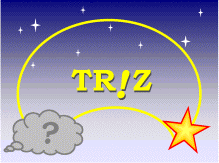
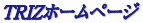  |
イノベーションの構造 -パラダイム破壊型イノベーションとは何か-
(青色発光ダイオードの事例を分析する) |
山口 栄一 (同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター(ITEC))
(現: 京都大学大学院総合生存学館(思修館) 教授) |
同志社大学 ITEC Research Paper Series, (2004) Vol.4 No.13, pp.1 - 15 (許可を得て転載) |
英文ページ: 'Rethinking Innovation', Eiichi Yamaguchi,
"Recovering from Success: Innovation And Technology Management in Japan" (2006年5月 Oxford University Press) (ISBN 978-0199297320), 共著 (Edited by R. Cole and D. Hugh Whittaker) |
| 掲載:2014.12.10 |
Press the  button for going to the English page.
button for going to the English page.
編集ノート (中川 徹、2014年12月10日)
本稿は、昨年に「東電原発事故の本質 (Fukushima Report)」 
 を掲載させていただきました、山口栄一教授(前:同志社大学、現:京都大学)にお願いして、掲載が実現したものです。私の依頼メール(12月8日夜)は次のようでした。
を掲載させていただきました、山口栄一教授(前:同志社大学、現:京都大学)にお願いして、掲載が実現したものです。私の依頼メール(12月8日夜)は次のようでした。
京都大学 山口栄一先生 2014.12. 8 中川 徹 (大阪学院大学)
10月21日のICSTI2014シンポで、初めて直接にお会いでき、ご講演をお聞きして、大変刺激を受けました。
その後、『イノベーション 破壊と共鳴』[山口栄一著、NTT出版刊] を拝読し、
山口先生のバックグラウンド、データ解析の緻密な研究スタイル、イノベーションに関する深い洞察などを
知ることができました。Fukusima Reportが生まれた素地も初めて理解しました。
先日お願いしていた件ですが、「イノベーション・ダイアグラム」 を使って表現しようとされていることの、基本的な
考え方をお書きになった記事・解説・発表などで、適当なもの(10~20頁程度のもの)を、
『TRIZホームページ』に再掲載させていただけないでしょうか?
和文と英文があれば(対応するものでなくても)大変嬉しいのですが。また、無償にてお願いいたします。
ご多忙の先生に厚かましいことをお願いしており、まことに申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 敬具
翌朝に山口先生が送付くださいましたのが、本和文ページの論文(2004年)と、英文ページの関連論文(2006年)です。重要で時宜を得た記事ですので、早速にここに掲載させていただきます。(本ページのタイトル末尾の()内は、中川がつけさせていただきました。)
ちょうど今夜は、ノーベル賞の授賞式で、「青色発光ダイオードの発明」に対して、日本の3人の研究者、赤﨑勇・名城大学教授、天野浩・名古屋大学教授、中村修二・米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授が、物理学賞を受賞されます。おめでとうございます。
-- その発明が行われたプロセスを、物理学の研究の観点とと、技術経営の観点から、調査・分析・考察しているのが、山口先生のこの論文です(より詳しくは、『イノベーション 破壊と共鳴』に記述されています)。
目次
要約
1. 研究・開発のリストラがもたらした日本の危機
謝辞
 論文 PDF
論文 PDF 
イノベーションの構造
-パラダイム破壊型イノベーションとは何か-
山口 栄一 (同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター(ITEC))
(現: 京都大学大学院総合生存学館(思修館) 教授)
同志社大学 ITEC Research Paper Series, (2004) Vol.4 No.13, pp.1 - 15 (許可を得て転載)
要約
20世紀最後に日本で生まれた著しいイノベーションである「青色発光ダイオード」について、その生成プロセスを分析する。この分析によってイノベーションの構造を調べ、イノベーションには、クリステンセンのいう「破壊的イノベーション」つまり「性能破壊型イノベーション」とは直交する次元として,「パラダイム破壊型イノベーション」が存在することを論証する。パラダイム破壊型イノベーションを目前にしたとき、大企業がなぜ失敗するかを議論するとともに、パラダイム破壊型イノベーションを実現するための方法に触れる。
1. 研究・開発のリストラがもたらした日本の危機
半導体の活況に刺激されて、ハイテク産業が息を吹き返しつつある。シリコン・サイクルによる今年限りの過渡現象と見る向きもあるものの、図1に示すように第2次ベビーブーマーが40歳を迎える2010年代前半まで個人消費を引っ張っていくと予想されるため、今後10年ほど持続的な景気回復が期待されよう。もっとも、その後は20年以上続く底なしの少子化によって日本の景気は、単純には悪化の一途をたどる可能性が高い。それに備えるためには、今後10年かけてビジネスモデルの中核に「イノベーション」を据える体質改善を、日本の産業社会が成しとげることだ。日本は否応なくポスト工業化社会への道を選ばざるを得ないのである。
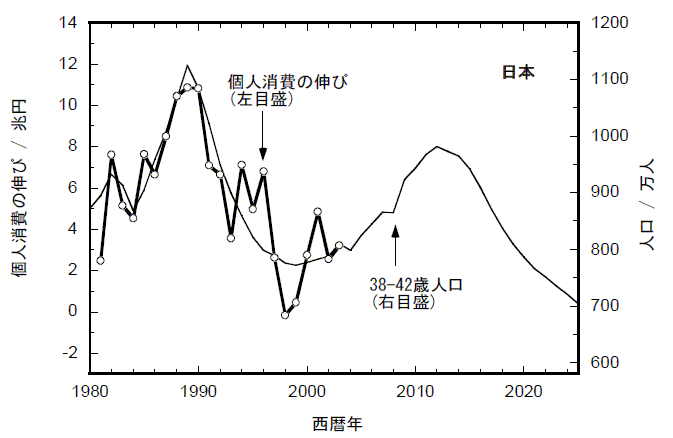
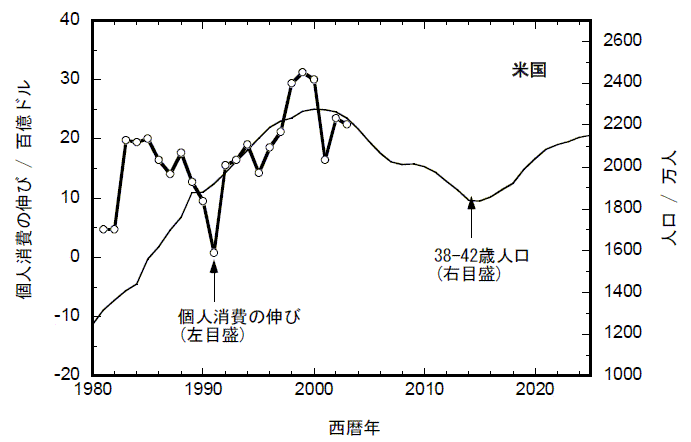
図1: GDP(国内総生産)における個人消費の伸びの経年変化(上=日本、下=米国)。
日米ともに、38-42歳人口の動きとよく似たダイナミクスを持つ。
ところが過去10年近く日本のハイテク産業は、研究・開発部門の一斉リストラを進めてイノベーションの源泉を潰してきた。能力評価をせずに研究者を部門ごとリストラして製造部門や営業部門に回したり、子会社に移してそのまま解雇したりした。そのため鍵となる基幹研究者や技術者が少なくなってしまい、イノベーションのエンジン自体が馬力を落としてしまった。研究・開発費に占める国の拠出割合が大きい諸外国と異なり国の研究・開発の約8割を民間企業に依存してきた日本にとって、これは国のイノベーション・システムの危機に他ならない。
図2をご覧いただきたい。この図で、縦軸は1994年の株式時価総額に対する2003年の株式時価総額、横軸は1994年における各企業からの学術論文寄与度に対する2003年の学術論文寄与度。要するに、縦軸は1994年から2003年にかけて企業価値がどれくらい増加したかを表わし、横軸は1994年から2003年にかけて知の創造への志向度がどれくらい増加したかを表わしていると考えてよい。実はこの横軸は、基幹研究者の数の増減とほぼ連動する。統計データによると基幹研究者1人が1年に書く論文数はほぼ一定だからだ。
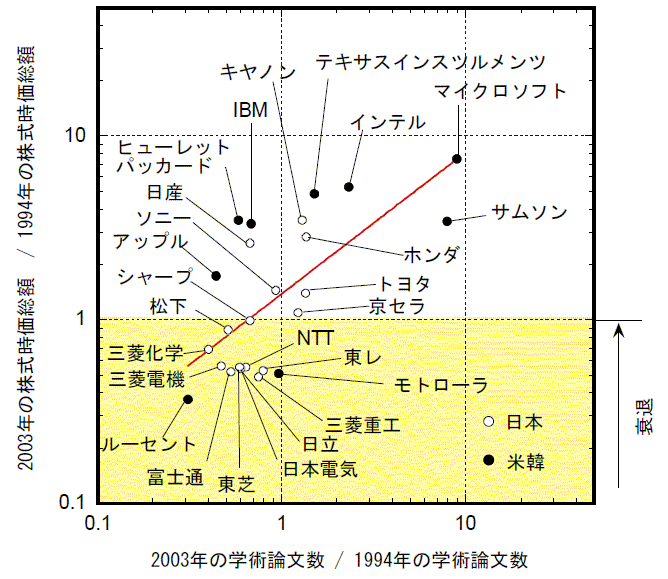
図2: 1994年(ただしルーセントのみ1996年)から2003年にかけての株式時価総額の伸び(縦軸)と学術論文寄与度の伸び(横軸)の相関。
相関係数は0.711。ここで学術論文寄与度とは、論文数を母集団に含まれる全論文数で除した値。ただし母集団は、SciSearch + Social SciSearch。
日米韓の主要大企業についてプロットしてみると、興味深いことが見えてくる。企業価値増加度と知の創造への志向度という、まったく無関係に見えるこれら二つの変数がきわめてよい相関をもち、しかも国によらず普遍的な1本の回帰曲線に乗る、ということだ。
この奇妙な現象は、いったい何を意味するのか。思いつくままに理由を挙げてみよう。
- 真摯な研究・開発が行われた結果、ヒット商品が生まれ、企業価値増加につながった。
- 研究者や技術者を増やしたり論文執筆を奨励したりした企業では、研究部門のモティベーションが上昇。それが他部門に波及して、生産性や商品開発力の増加につながった。それとは逆に、研究者や技術者のリストラを大規模に行なった企業では、研究部門のモティベーションが低下。それが開発部門や製造部門に波及し、生産性や商品開発力が低下して企業価値が下がった。
- 高収益を上げて企業価値を増やした企業では、その収益増を研究・開発費にふりむけ、その結果、研究者数の増加や論文数の増加につながった。いっぽう収益を上げられずに企業価値を減少させた企業では、コスト要因である研究部門のリストラを行ない、その結果、論文数が減少した。
ここで、1990年までのイノベーション・モデルであった「線形モデル」すなわち「基礎研究・応用研究・実用化を自前で連ねながら技術革新を行なう」という手法はすでに終焉を迎えているので、①がありえないことは言うまでもない。
個別企業ごとに詳しい分析をすると、この相関の主たる原因は、②と③が互いに連鎖的に働いたことによる可能性が高い。なかでも、NTTをはじめ日本のIT関連の大企業が、申し合わせたようにほぼ同じポイントに折り重なっていることは興味深い。1990年代に各社横並びで研究者のリストラを行ったものの、それを契機に会社から独創を育む場と土壌が失われ、その集合意識としてのモティベーションの低下が製造部門などにも伝播して、結局のところ企業の全体活力が失われていったことが推測できる。近年、各社とも研究・開発体制を再強化する方向に舵を切りつつあるものの、失われた場の再構築には、壊すのに要した何倍もの時間と労力がかかることを否応なく経験するにちがいない。
2. クリステンセンの「破壊的イノベーション」
さて、では線形モデルに取って代わる新しいイノベーション生成モデルは、どのようなものだろうか。少なくともIT革命を契機に市場と技術と科学的知見とが、従来とは比較にならないほど速いフィードバック・ループでつながり始めたこの10年間、新しいイノベーション・モデルは、価値の最終需要者である顧客をも取りこまなければならなくなった。
ところが、顧客をよく観察し、顧客のニーズを徹底的にモニターすればするほど、却って不可避的に企業が失敗する可能性があることを、米国のクレイトン・クリステンセンは見出した。「イノベーションのジレンマ」 (Christensen 1997) の中で展開された彼の議論を、ここで簡単に紹介しておこう。
彼はハード・ディスクの歴史を定量的に調べ上げた。最初、メインフレーム用の14インチ・ドライブとして市販されたハード・ディスクは、1970年代から90年初頭にかけて単位面積あたりの記録密度を急速に伸ばした。この伸びは、技術革新によって磁気ヘッドの発生する磁気力が増えていったことによる。このように「性能を引き上げる」イノベーションを、クリステンセンは「持続的イノベーション」と呼んだ。
さて1978年、数社のベンチャー企業が、小型の8インチ・ドライブを市販する。それは14インチ・ドライブの10分の1程度の記録密度だったにもかかわらず、ミニコンの顧客に評価されて新しい市場を創った。一方14インチ・ドライブのメーカーはこの8インチ市場に参加しなかったり遅れて参入したりした。結局14インチのハード・ディスク専業メーカーは、すべて敗退した。
1980年、あるベンチャー企業が5インチ・ドライブを市販する。これはデスクトップ・パソコンの顧客に評価されて新しい市場を形成した。一方8インチ・ドライブのメーカーはこの新市場への参入に遅れをとって、4社のうち3社は消滅した。
ところが5インチ・ドライブを初めて売り出したこの会社も、1985年に別の新しいベンチャー企業が市販した3.5インチ・ドライブに関心を示さなかった。1988年にようやく当社 [同社] は3.5インチの生産を始めたものの、ノートブックの市場には参入できなかった。
つまり「性能を引き下げる」イノベーションが起きて実績のある企業を失敗に導いた、というわけだ。これをクリステンセンは「破壊的イノベーション」と呼んだ。
では、なぜ優秀な大企業は「破壊的イノベーション」を前にしたときに、経営判断をまちがえるのか。
市場のない所に乗り出す勇気がないからか。それとも会社の図体が大きくなると、事なかれの官僚主義に陥るからか。
いや。そのような、取るに足らない理由に因るのではない。そうではなくて、すべての企業が特定の価値観のネットワークに組み込まれているからだと、彼はいう。
たとえば1980年のエポックを考えてみよう。5インチ・ドライブのメーカーは、デスクトップ・パソコンの顧客が作る価値観のネットワークに組み込まれていた。そのため必然的に、記憶容量に高い価値を置く顧客しか見えなかった。実際、お得意さんに向けてアンケートを取ってみたものの、記憶容量より携帯性の方が大切だとする未来の顧客の声を聞くことができなかった。
その結果、利益率が低く明確な市場も形成されていない3.5インチに下りていけなかった。むしろ顧客の要望に沿いながら高い利益を得られる方向に上っていくことを決断した。行き着く先に「市場の死」が待ち構えているとも知らずに…。
クリステンセンはこうして「優秀な経営判断が下せたはずの大企業がどうして、性能を引き下げられた『破壊的イノベーション』を前にして敗退するか」を論証した。なお、ここで「性能を引き下げる」とは、ある技術創造で生まれた技術の未熟さに因るものではなく、あえて本質的に性能を引き下げた、ということを意味する。既存の製品・サービスより敢えて劣る製品・サービスを提供することで、使いよさや安価さを求めるまったく新しい顧客を創造し、市場構造を破壊して組み替えてしまうということだ。
3. 青色発光ダイオードは、クリステンセンの「破壊的イノベーション」か?
では、クリステンセンのこの議論を念頭に置きながら、20世紀最後に日本で生まれた著しいイノベーション「青色発光ダイオード」について考察してみよう。
このイノベーションは、徳島県阿南市のベンチャー企業である日亜化学工業による。元従業員の中村修二氏(現カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授)を中核とし、妹尾雅之氏・岩佐成人氏・向井隆志氏などの若手研究者からなる研究チームが経営者と連携しながらこのイノベーションを成功に導いた。しかし、このイノベーションを成立させる科学的発見は、中村氏らによるものではない。松下電器出身の赤﨑勇氏とその弟子・天野浩氏、それからNTTの松岡隆志氏によるものであった。
1980年代、すでに赤色を発光する半導体デバイスは開発されていたものの、緑や青を発光する半導体デバイスはできていなかった。もし緑と青を発光するデバイスができれば光の三原色が揃うことになり、どのような色の光でも発光できる。これで電灯を作ればエネルギー消費がきわめて少なく半永久寿命を持つ明かりができることになる。こうして、緑や青の発光ダイオードの研究は、大企業の中核的なテーマとなった。
理論的には、窒化ガリウム結晶か、またはセレン化亜鉛結晶の、いずれかの半導体を用いれば、緑や青の光を出せることは分かっていた。しかし前者を作るのは、困難を極めた。
なぜか。結晶を成長させるのは、結合手のあるブロック(たとえばおもちゃのレゴ)遊びに似ている。レゴの上にレゴでないブロックを積めない。結合手の間隔が違うからだ。同様に、結晶を作るには、下地結晶(基板という)にそれと同じ結合手の間隔を持った結晶を用意しなければならない(格子整合条件という)。しかし窒化ガリウムの場合、そのような基板がなかったのだ。
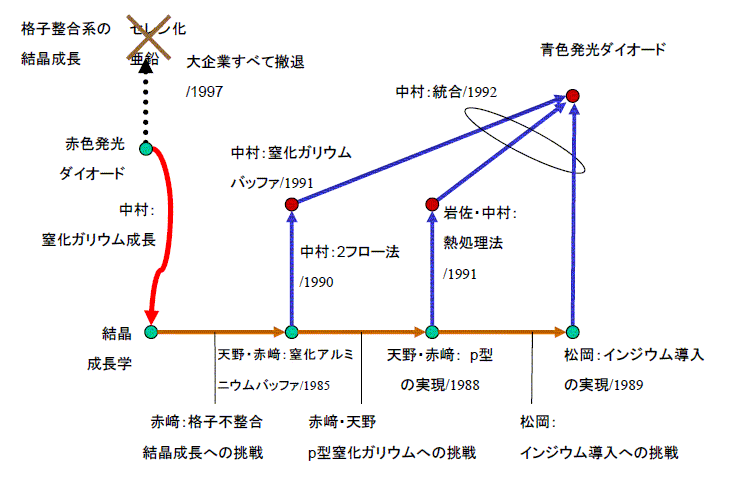
図3: 青色発光ダイオードのイノベーション・ダイヤグラム。
横軸は、知の創造への営為(発見など)を示し、縦軸は、知の具現化(発明などの技術創造)を示す。
「パラダイム破壊型イノベーション」の特徴は、常に根本原理(科学的知見など)に降りるベクトルを含むこと、および降りたところに共鳴場が生成されて、暗黙知の伝播が行なわれることである。大企業では一般に、時間に逆行するように見えるこの回帰ベクトルを許さず、縦軸方向に進むベクトルでのみ構成されるイノベーション・プロセスのみを評価するので、「パラダイム破壊型イノベーション」に失敗する。
一方セレン化亜鉛の場合は、すでにコモディティになっていて容易に手に入るヒ化ガリウム(通称、ガリウム・ヒ素)がそのまま基板になる。そのため1980年代の終わり頃までには、セレン化亜鉛の結晶成長技術は確立した。そこで世界中のどの大学も、どの企業研究所も、このセレン化亜鉛を青色発光ダイオードの材料として選び、研究資源を重点的に投入していった。
しかし赤﨑氏は、敢えて窒化ガリウムを選び取った。
なぜか。その理由の中に「研究とは何か」に対する彼の思想を読み取ることができる。
研究とは「まだ見ぬものを見(発見)、まだこの世界にないものをあらしめる(発明)」ことに他ならない。だから「できないとされていたことをできるようにする(パラダイム破壊)」ことこそが研究であった。
松下電器からの研究中止命令で当社 [同社] を辞し名古屋大学に移った赤﨑氏は、そのパラダイム破壊に挑戦。1985年、彼の指導下にいた大学院生の天野氏が「サファイアの上に、結晶になりきっていない窒化アルミニウムをまず積んでから窒化ガリウムを積むと結晶性が極めて良くなる」ことを発見した (Amano et al., 1986)。結晶になりきっていない層がバッファの役割を果たしたのである。天野氏と赤﨑氏によるこのバッファ層法の発見こそ、青色発光ダイオードというイノベーションの最初の端緒を開くこととなった。
次のパラダイム破壊も、天野氏と赤﨑氏が偶然に開くこととなる。
当時、窒化ガリウムは、どのように工夫してもn型のままでp型にはならなかった。窒素の欠陥があるとp型にはならないという理論を出す理論物理学者もいた。もしp型ができないとすると、pn接合による発光デバイスが作れない。
天野氏もまた、このp型窒化ガリウムを作ろうと、アクセプタをドープする実験を何度も試みたものの常に失敗した。1987年、結晶成長したアクセプタ・ドープの窒化ガリウムを電子顕微鏡で観察していた天野氏は、奇妙な事実に気づいた。観察のために電子ビームを照射していると、みるみる窒化ガリウムが光り始めるのである。電子ビームでアクセプタが活性化したのだ。このセレンディピティを契機に、天野氏と赤﨑氏は工夫を重ね、ついに窒化ガリウムのp型化に成功した (Amano et al., 1989)。1988年のことだった。
これら2つのパラダイム破壊に勇気づけられたNTTの松岡氏とそのチームは、さらに窒化ガリウムと窒化インジウムとの混晶(合金のこと)を作ることを企図。なぜなら、紫・青・緑と、発光する色を変えるためには、この混晶を作って混ぜ合わせの比率を変えてやらなくてはならないからだ。だが、窒化ガリウムと窒化インジウムを混ぜることもまた、当時できないとされていた。しかし1989年、その常識を破って松岡氏らはこれに成功 (Matsuoka et al. 1990)。こうして、3つ目のパラダイム破壊も達成された。
さて、中村修二氏に話を戻そう。
彼が、窒化ガリウムを選び取った理由は、赤﨑氏らとは異なる。彼は日亜化学に入社後、半導体製造に従事し、自分で作った半導体を売り歩いた。しかし中小企業が大企業と同じものを作ったところでひどく買い叩かれることを身に染みて知った。だから「誰も実用化に成功していない青色発光ダイオードを作ろう」と思い至ったとき、彼には選択の余地がなかったことになる。大企業がやっているセレン化亜鉛を選ぶわけには行かないのだ。
彼は、社長の小川信雄氏に直訴する。今ここにないものを作って売らない限り、中小企業はピラミッドの底辺で苦しまなくてはならないと。
薬剤師として戦地ガダルカナルに赴任、死淵を経験して故郷の阿南に戻りゼロから日亜化学を創業した小川氏には、中村氏の言葉が身に染みた。彼は、中村氏の魂の叫びに五億円の研究費をかけることにした。
こうして中村氏は1988年フロリダ大学に留学し、結晶成長法の基礎を学んで1989年に帰国。すでに日亜化学の首脳陣が中村氏のために準備していた結晶成長装置を手にして、十分な研究資金を受けながら即座に研究を開始。1年後の90年に「2フロー法」のアイデアに辿りつく (Nakamura et al., 1991)。
2フロー法とは、横から原料ガスを反応炉の中に導入すると同時にそれとは直角の方向からサファイア基板に向かって大量の窒素ガスと水素ガスを吹き付ける方法である。この方法は条件設定パラメーターが多くて最適値を見出すのが難しいのだが、彼は最初のトライアルで今までだれも得られないほど良質な窒化ガリウム結晶を成長させた。
この結晶成長では、赤﨑氏・天野氏によるバッファ層技術を用いた。しかし1991年、彼は窒化アルミニウムではなく窒化ガリウムをバッファ層として用いることにした (Nakamura, 1991)。
p型を作る際も、最初は天野氏が見つけた電子ビーム照射法を試した。しかしうまく行かない。頭を抱えていたところ、部下の岩佐氏が、当たって砕けろとばかりマグネシウム・ドープの窒化ガリウム結晶を、窒素雰囲気中で単純にアニール(熱処理)してみた。すると、何ということか窒化ガリウムが容易にp型化した (Nakamura et al., 1992)。コロンブスの卵であった。
インジウムの導入方法については、松岡氏に徹底的に学んだ。それに対して松岡氏は、「論文に書いてある通りにやると良い」と、彼のノウハウを正直に教えた。
こうして1992年に中村氏は、青色発光ダイオードを驚異的なスピードで実用化した(Nakamura et al., 1993)。意思決定の重層構造を持たないからこそ、この技術革新をイノベーションにまで高めることができたのである。
一方、松岡氏はまさにその1992年に、NTTから研究中止命令を受けて、研究のストップを余儀なくされた。研究所の経営陣は、セレン化亜鉛への「選択と集中」を決断したのだった。
また、東芝、日本電気、ソニーなどはさらに四年経って、ようやく自分たちの選び取ったセレン化亜鉛の道がまちがっていたことに気づき、日亜化学の後を追い始める。しかしついに追いつくことはなかった。
いったいなぜ、松下電器は赤﨑氏のチームに研究中止命令を出し、NTTは松岡氏のチームに研究中止命令を出したのか。そしていったいなぜ、東芝や日本電気そしてソニーなどの大企業は、日亜化学に遅れをとったのか。
4. もう一つの「破壊的イノベーション」-「パラダイム破壊型イノベーション」
これらの疑問に答える前にまず、このイノベーションがクリステンセンの「破壊的イノベーション」に分類されるかどうかを考えてみよう。たしかに、このイノベーションでは、そうそうたる大企業が判断ミスをしたり遅れをとったりした。だから一見、クリステンセンの「破壊的イノベーション」に分類されそうに見える。では、「性能を引き下げて」いるか。
答えは否である。それは今までにない画期的技術であった。新しい性能をもたらしたという点において、発光デバイスの性能を劇的に引き上げた。だからこれは、まぎれもなく「持続的イノベーション」である。
実際、クリステンセンは、トランジスタを真空管にとっての「破壊的イノベーション」であると述べているけれども、これも誤りだ。トランジスタは、量子物理学の予言どおりに設計されたとき、古典物理学で動作する真空管の周波数応答性能を圧倒的にしのいだ (注1)。したがって、これも「持続的イノベーション」である。
(注1): トランジスタの発明者の一人、ウィリアム・ショックレイ氏は、「1950年4月20日、私の書き散らしたノートにしたがって写真写りの良くないnpn型の接合型トランジスタができた。これは、理論どおりの動作をしたものの、周波数応答が悪く誰も関心を示さなかった」(Shockley, 1984) と述べている。しかしこれによって「トランジスタは、真空管より性能が悪かった」と考えてはならない。この劣悪な性能は、単にp層(ベース)の厚さが厚すぎたためであって、量子力学の教えどおりにできていなかったためである。「技術の未熟によって期待する性能がでない」ことと「性能破壊型イノベーションにおいて性能を敢えて引き下げる」こととを混同してはいけない。
では、「持続的イノベーション」でありながら、なぜ大企業は一様に失敗したり敗退したりしたのだろう。それを知るためには、イノベーションの構造にあるもう一つの次元を見つける必要がある。すなわちパラダイムの破壊性にかかわる次元である。
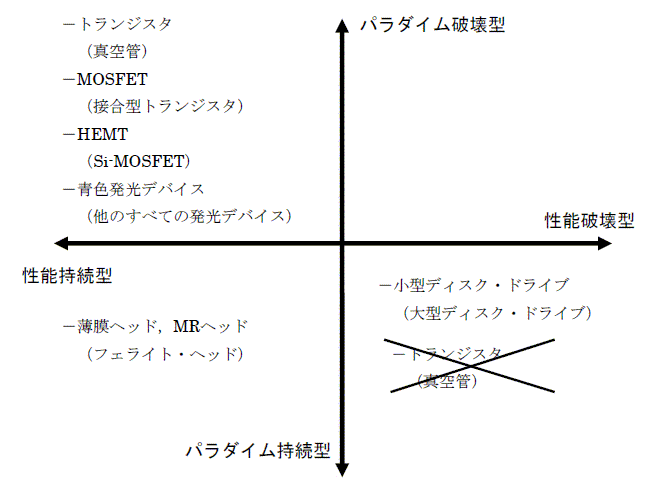
図4: イノベーションの構造。
クリステンセンの「破壊的イノベーション」(「持続的イノベーション」)を「性能破壊型イノベーション」(「性能持続型イノベーション」)と呼び変えてある。この軸とは直交する次元として、「パラダイム破壊型イノベーション」および「パラダイム持続型イノベーション」が存在する。
このような型に属するイノベーションを「パラダイム破壊型イノベーション」、そうでない型を「パラダイム持続型イノベーション」と呼ぼう。混乱を避けるために、以下ではクリステンセンの「破壊的イノベーション」を「性能破壊型イノベーション」、「持続的イノベーション」を「性能持続型イノベーション」と言い換えることにする。(図4参照)
前者のペアは、イノベーションの生成プロセスの違いで分類される。「科学的パラダイムを破壊したか否か」、つまり「今まで科学的にできないとされてきたことを、できるようにしたか否か」ということだ。いっぽう後者のペアは、「性能を引き下げる製品を市場に投入したか否か」で分類される。だからイノベーションの生成プロセスを問題にしない。
「パラダイム破壊型イノベーション」には、その生成のプロセスに共通の特徴がある。そしてその特徴によって、実績ある大企業が敗退したり遅れをとったりするワナが隠されている。そのワナは、クリステンセンがいう「価値観のネットワーク」によるものではなく、暗黙知の伝達が難しいことにある。
このことを詳しく分析するために、「パラダイム破壊型イノベーション」を成立させている特徴を、青色発光デバイスを例に取りながら一般化しておこう。
① 青色発光デバイス用材料として第一候補であったセレン化亜鉛は格子整合条件を守って結晶成長ができるので、実績ある企業はそちらを選び取った。窒化ガリウムのように格子整合条件を守らずに結晶成長を行なうことは結晶成長学のパラダイムに反していたからだ。ところが、青色発光デバイスの最終解は、セレン化亜鉛の道の彼方にはなかった。
すなわち、「パラダイム破壊型イノベーション」においては、最終解は既存技術の延長線上にはない。
②「セレン化亜鉛のような弱くて欠陥ができやすい材料ではなく、硬くて強い窒化ガリウムこそが本命である」という暗黙知に到達したことが明暗を分けた。この暗黙知は、固体物理学の原点に帰ることによって得られるものであった。さらに赤﨑氏の夢を実現させたのは、愛弟子の天野氏が偶然辿り着いた「バッファ層技術」というパラダイム破壊だった。
すなわち、最終解に到達するためには、いったん根本たる科学的知見まで戻らねばならない。そうして初めて、パラダイム破壊が生ずる。
③ しかし最終的に窒化ガリウムの青色発光ダイオードを実用化させたのは、赤﨑氏・天野氏でも松岡氏でもなく中村氏であった。創業者小川氏の共鳴を得てこの世界に入り、結晶成長の最適条件を掘り当てた中村氏は、先達が得たパラダイム破壊を統合して実用化にまで止揚させた。
すなわち「パラダイム破壊型イノベーション」では、その生成プロセスの遂行チームの中に、事業を最終的に成功させる責任者が中核として存在しており、そのプロセスに関わる暗黙知を共有しているかどうかが鍵になる。
5. 暗黙知を伝える唯一の手段としての共鳴場
この3法則の中で、②は研究者の力量にかかっている。しかし①と③は、企業における経営者の力量にかかっていることは重要だ。イノベーションを成功させるも失敗させるも、技術経営の方法論が鍵を握っているのである。
このもっとも端的な例がMOSFETだ。MOSFETとは、コンピューターなどの電子機器の中のLSIを構成するトランジスタのことである。シリコンからできており、その表面を酸化させて作った絶縁膜とシリコンとの界面を走る電子の流れをスイッチングすることで動作する。これ以前のトランジスタをバイポーラ・トランジスタと呼ぶ。
このMOSFETは、1960年に発明されたものの当初は特性が不安定で、その原因がなかなかつかめなかった。しかしロバート・ノイス氏とゴードン・ムーア氏をリーダーとするフェアチャイルド・セミコンダクタ社の研究チームが、1964年にこの不安定要因を発見。これを除去することでMOSFETの集積回路(MOS-IC)へのメドがついに立った。
ところが、フェアチャイルド・セミコンダクタ社の親会社から派遣された経営陣は、MOS-ICの事業化に反対した。バイポーラICの事業は十分に成功していたし、競争が激化していて資源をMOS-ICの可能性追求に振り向けるわけには行かなかったからだ。
結局、フェアチャイルド・セミコンダクタ社を創ったノイス氏とムーア氏は、再度のスピン・オフを決意して同社を辞しインテル社を創業。さっそくMOS-ICをコアとする事業を展開して大成功を収める。一方、ノイス・ムーア両氏を失ったフェアチャイルド・セミコンダクタ社はほどなく消滅した。
いったい何がおきたのか。フェアチャイルド・セミコンダクタ社の親会社とノイスとの不仲説が定説となっているけれども、実はMOSFETの天賦性を経営陣に説明することが不可能だったからだと思われる。
MOSFETの実現の鍵を握っていたのは、半導体・絶縁膜界面における電子トラップ(界面準位という)であった。量子力学の教えでは、格子整合しない異種物質の接合による界面準位は必ず存在せねばならず、 MOSFETというデバイスは、一般にはあってはならない。ところが、シリコン上に成長させた酸化膜に限って、この界面準位がほとんどなかった。天賦の幸運であった。「なぜ界面準位がシリコン酸化膜に限って異常に少ないか」ということは、ようやく近年スーパー・コンピューターを用いた量子力学計算で証明されつつあるが、その時点では理由がわからない。しかし、その物性に対峙した研究者は暗黙知として感じ取っていた。MOSFETこそ、天賦のトランジスタだ、と。
しかし研究チームは、この時点で彼らの暗黙知を経営陣に伝えることが原理的に不可能であった。経営陣は、「表面を用いるデバイスは不安定で使い物にならない」という、教科書に書かれた科学的パラダイムに捉われていたからだ。つまり、未知の領域に踏み込んだ研究チームは、MOSFETが「パラダイム破壊型」の技術創造であることを暗黙知として共有していながら、その暗黙知を経営陣は決して共有できなかった、ということだ。そこでノイス氏は、その暗黙知を共有する同胞だけを連れてスピン・オフするしかなかった。
このように、発明者を含む研究チームの中では、イノベーションの成功に向けての暗黙知が必ず醸成される。ところが、この暗黙知を経営サイドに伝達することは、常にきわめて困難である。とりわけ科学的パラダイムを破壊するタイプの技術創造の場合、その暗黙知を伝達できるのは、その独創の生成プロセスを共有した場合に限られる。
この暗黙知が醸成され伝達される場を、とくに「共鳴場」と呼ぶことにしよう。「共鳴場」の生成者は、今この世界にない新技術を創造したいと渇望する人間である。事業化の責任者がこの「共鳴場」に参加して暗黙知を共有することで、「パラダイム破壊型イノベーション」の生成プロセスが初めて成立する。
6. 「パラダイム破壊型イノベーション」を前にして、大企業はなぜ失敗するか
では、最初に提起した二つの疑問に答えてみよう。
まず、第一の疑問。なぜ松下電器は赤﨑氏のチームに研究中止命令を出し、なぜNTTは松岡氏のチームに研究中止命令を出したのか。これは、松下電器においてもNTTにおいても経営者が「共鳴場」に参加していず、暗黙知を共有できなかったからだ。
成功体験を積んだ経営者は、合理的な判断として暗黙知に支えられた技術創造を捨ててしまうし、大企業でそれが階層化していれば捨てられる確率はどんどん高くなるからである。その結果、優秀な意思決定者が何重にも存在する企業ほどパラダイム破壊型の技術創造を捨ててしまう可能性が高くなる。
次に、第二の疑問。NECや東芝、さらにソニーなどの大企業は、なぜこのイノベーションに遅れをとったのか。一方、小さなベンチャー企業だった日亜化学は、いかにしてこのイノベーションの最終エンジンになりえたのか。これは、既存技術の延長上にニセの解があるときには、同質の戦略手法をもつ優等な集団であればあるほど、形式知化しやすいその解を選ぶからだ。真の解を獲得するには、できる限り多様で異質なものが「共鳴場」を形成して、暗黙知の伝達をより広い領域に波及させたほうが良い。
中村氏は、辺縁の小企業にあって、窒化ガリウムを選ぶというリスクに挑戦しない限り勝ち目はない立場にいた。しかも、すべてのパラダイム破壊がおきたあとにレースに参加するという幸運に恵まれた。そして野性的天才によって、いち早く結晶成長の最適条件を掘り当てた。しかしこれら以上に彼を「巨人たちの肩に乗せた」要因は、日亜化学の創業者小川氏が暗黙知を共有し、中村氏に潤沢すぎる研究費と存分すぎる研究機会を与えたことである。その意味で、青色発光ダイオードの真のイノベーターは、小川信雄氏であったということすらできよう。
イノベーションを如何に生み出していくか。もっとも容易な方法は、既存知識の延長に向かって進むことだ。しかしそれは必ず行きづまる。行きづまったとき、既存の知をいったん捨てて科学的地平にある根本に降りていくことは、とりわけ経営者にとっては図太いチャレンジ魂がいる。しかしそれを避けてはいけない。もし経営者に、根本に降りる時期を見極める力がないのなら、その力を持つ人を研究・開発のプロデューサーにして責任と権限を付与しておくべきであろう。そして同時に、経営者は現場との共鳴場をたえず維持し、現場の暗黙知を常に汲み取る努力をすることだ。知が滞留して経営者に伝達されなくなった組織は必ず腐る。それ以上に、知が形式知でしか経営者に伝わらなくなった組織もまた、みずからの独創力を必ず腐らせるからである。
イノベーションには、テクノロジー・イノベーションとビジネス・イノベーションの他に、人を安心させたり心地よくさせたりすることに価値軸を持つイノベーションが存在することにも気づいておくべきだ。美しさや快適さを求めるという意味のギリシア語にちなんで、これをアエステシス(Aesthesis) イノベーションと名づけておこう。すると、クリステンセンが例示したハード・ディスクの場合、小型化というのは性能を引き下げたのではなく性能を表現するベクトルの方向をテクノロジー・イノベーションの方向からアエステシス・イノベーションの方向に回転させたと考えることができる。実は、性能破壊型イノベーションの殆どは、アエステシス・イノベーション軸における性能を引き上げる製品開発に他ならない。アエステシス・イノベーションという隠れた次元を顕在化させることもまた、新製品開発にとって重要な法則の一つである。
謝辞
株式時価総額については、塩脇啓吾氏(21世紀政策研究所)に収集していただいた。心から御礼申し上げる。本研究は、文部科学省21世紀COEプログラムに採択された「技術・企業・国際競争力の総合研究」プロジェクトにおける研究成果である。
参考文献
Christensen, C. [1997], “The innovator’s dilemma”, Harvard Business School Press.(伊豆原弓訳「イノベーションのジレンマ」翔泳社, 2001)
Amano, H., Sawaki, N., Akasaki, I. and Toyoda, Y. [1986], “Metalorganic vapor phase epitaxial growth of a high quality GaN film using an AlN buffer layer”, Appl. Phys. Lett. 48, 353.
Amano, H., Kito, M. Hiramatsu, K. and Akasaki, I. [1989], “P-type conduction in Mg-doped GaN treated with low-energy beam irradiation (LEEBI)”, Jpn. J. Appl. Phys. 28, L2112.
Matsuoka, T., Tanaka, H., Sasaki, T. and Katsui, A. [1990], “Wide-gap semiconductor (In,Ga)N”, Inst. Phys. Conf. Ser. 106, 141 (Proceedings of Int. Symp. GaAs and Related Compounds, Karuizawa, 1990).
Nakamura, S. [1991], “GaN growth using GaN buffer layer”, Jpn. J. Appl. Phys. 30, L1705.
Nakamura, S., Harada, Y. and Seno, M. [1991], “Novel metalorganic chemical vapor deposition system for GaN growth”, Appl. Phys. Lett. 58, 2021.
Nakamura, S., Mukai, T., Senoh, M. and Iwasa, N. [1992], “Thermal annealing effects on p-type Mg-doped GaN films”, Jpn. J. Appl. Phys. 31, L139.
Nakamura, S., Senoh, M. and Mukai, T. [1993], “P-GaN/n-InGaN/n-GaN double heterostructure blue-light-emitting diodes”, Jpn. J. Appl. Phys. 32, L8; “High-power InGaN/GaN double-heterostructure violet light emitting diodes”, Appl. Phys. Lett. 62, 2390.
Shockley, W. [1984], “The Path to the Conception of the Junction Transistor”, IEEE Transaction, Electron Devices, ED-31, 1523.
 英文ページ
英文ページ 
 英文論文 'Rethinking Innovation', Eiichi Yamaguchi,
英文論文 'Rethinking Innovation', Eiichi Yamaguchi,
in "Recovering from Success: Innovation And Technology Management in Japan",
edited by R. Cole and D. Hugh Whittaker, Oxford University Press (May 2006), (ISBN 978-0199297320) 
 編集ノート後記(中川 徹、2014年12月10日)
編集ノート後記(中川 徹、2014年12月10日)
この論文には、沢山の重要な指摘があると思います。主なものは次のようです。
最終更新日 : 2014.12.10 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp