電子機器の発熱を自然空冷により効率よく放出する方法
[掲載: 2001. 7. 4]
|
|
|
| USITトレーニングセミナー参加報告:
事例: 電子機器の発熱を自然空冷により効率よく放出する方法 |
|
| 上野浩輝
(オムロン株式会社), 2001年 7月 2日 (投稿受理)
[掲載: 2001. 7. 4] |
|
| 初出(口頭): 上野浩輝: 三菱総合研究所主催第5回創造手法分科会, 東京, 2001. 1.19 |
本内容は、2000年1月26日〜28日にかけて三菱総合研究所主催の「USITトレーニングセミナー」に参加したときのセミナー内容と個人的な感想を、三菱総合研究所主催の第5回創造手法分科会で報告した時に作成した資料からまとめたものです。セミナーでの検討内容は、不十分な点も多々ありますがTRIZ,USITを学ぼうとされるかたの幾分かのご参考になれば幸いです。著者所属: オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションカンパニー 技術統括センタ
目 次
1. はじめに
2. 想定した課題
3. トレーニングセミナー・プログラム
4. 問題定義プロセス
5. 問題分析プロセス
6. 解決策生成プロセス
7. まとめ
8. 参考文献
| 本ページの先頭 | 1. はじめに | 2. 想定した課題 | 3. セミナープログラム | 4. 問題定義プロセス | 5. 問題分析プロセス | 6. 解決策生成プロセス | 7. まとめ | 編集ノート | USITせミナー報告(中川) |
1.はじめに
本トレーニングセミナーに参加するまでのTRIZおよびUSITに関するバックグランドを紹介する。当センタでは、TRIZを開発効率向上のツールとして検討し、TOPE(三菱総研扱いIM社ソフト)を導入すると同時に、情報収集のため三菱総合研究所主催の知識創造研究会に参加し、TRIZの普及方法と有用性の検証をはかっている。
TRIZの理解に取り組み、普及させようと試みると、BS法、KJ法、TMなどの開発手法と同様にプロセスを手順的に明記した資料を欲する。しかし、TRIZにおいては、手順を示したものはなく興味を持った開発者も挫折してしまいがちである。企業で広く普及していけるものか疑問であった。
そこで興味をひいたのが本ホームページにも掲載されているFord社の事例研究である。その後、中川教授による知識創造研究会での講演をもって
USITがTRIZを使って開発をすすめる近道であるとの予感を持った。今回のトレーニングは、大きな期待を持って参加したものであり、講師の中川教授、主催の三菱総合研究所様に感謝します。また、トレーニングにあたり、同グループで3日間、持ち込んだ課題に取り組んでいただいた小永田正一様,、大久保泰宏様(事務局兼務でご苦労様でした)、およびグループ発表・討議で貴重なご意見いただきました本トレーニング参加者の皆様に感謝します。
2.想定した課題
本セミナーでは、各自が課題を用意することという参加条件があった。参加に際して準備したものは、図1のようなものである。お互いが持ちよった課題を説明し、参加者が希望のテーマを選択して、希望者の多いテーマが検討課題となった。幸い、本課題をグループでの検討課題としていただいた。
第1図:用意した課題の説明
3.トレーニングセミナー・プログラム
各演習の区切りにおいて全グループの検討内容を発表し、その内容に対して全員で討議する形式で実施された。この方式により、全グループの課題に対して取組むこととなり、多くの経験を得られることや異なる分野の課題に対して検討することで適度のブレイクにもなることで効果的であった。
図2 トレーニングのプログラムとフローチャート
4.問題定義プロセス
ここで示されることは、極めてシンプルである。
a.1つの問題を取り出す。
b.短い文で問題を定義する。
c.簡単なスケッチを描く。
d.根本原因を文で表現する。
e.関連のオブジェクト群をリストアップする。
f.問題に関与する最小限のオブジェクト群に絞る。
しかし、ここでの定義付けは最終的なコンセプトに大きく影響する。何を問題とするのか? 発熱させない、熱に弱い部品の温度を上げないなどの中から今回は、熱が逃げないことに特定し、次のように定義した。
問題: 『自然対流による放熱効率を向上する』 スケッチ: 根本原因: 『ヒートシンクの熱がケースの外に出にくい』 オブジェクト群: 図3 問題定義プロセスの結果
5.問題分析プロセス
5−1.閉世界法
現在のシステムの分析からスタートすることから、現行システムを改良するアプローチに向く。
閉世界法のアプローチは、以下の通りである。
a.閉世界ダイヤグラムを構成する。
b.定性変化グラフを作る。
まず、閉世界ダイヤグラムを作成するということで、先に定義した「最小限のオブジェクト」に対して個々の機能を考えて作成していく。ここでは、現状の分析よりシステムの設計意図を尊重して機能分析していく。
USITは、TRIZの思想に基づいて構築されているが、閉世界ダイヤグラムはTRIZの「物質−場」分析に対応している。
図4 作成した閉世界ダイヤグラム
構成するオブジェクトの属性を列挙していく。ここでは、問題との関連性などの先入観を持たずにTRIZ的に力学、電気、磁気、熱、光学の観点で属性を列挙していく。
図5 オブジェクトの属性の列挙結果
縦軸に問題としている効果、横軸にオブジェクトごとに関連する属性をとりグラフ化する。
グラフの傾きは、増大か減少を区別するだけと考えて定性的にそれぞれのオブジェクトの属性をリストアップする。定性変化グラフは、TRIZの技術的矛盾に対応している。問題を減らしていくためには、どの属性をどの方向に変化させるべきか、列挙された諸属性をチェックして技術的矛盾を読み取る。
図6 作成した定性変化グラフ
5−2.Particles法
理想解を考えることからスタートすることから、新たなシステムを創造するアプローチに向く。
ParticlesはTRIZの「Smart Little People」をより抽象性を増して対応している。
Particles法のアプローチは、以下の通りである。
a.問題状況のスケッチを描く。
b.理想解の状況のスケッチを描く。
c.これらのスケッチ中に”Particles”を配置する。
d.”Particles”にして欲しい行動を記述する。
e.各行動のために”Particles”が持つとよい性質を列挙する。
Particles:
「任意の性質を持ち、任意の行動ができる魔法の物質・場」
問題状況、理想解のスケッチを作成する。「理想解」とは、TRIZで定義された次の概念で考える。
・完全に機能する(Works perfectly)
・コストはゼロである
・存在しない (無が有を生む)
図7 Particles法での問題状況スケッチ結果
問題状況と理想解とで変化がある位置にParticlesとして×印(マークも心理的に意味があるので×にする)を描く。つぎにこのParticlesにどんな行動をしてもらうとよいか、それにはどんな性質が必要かを考えていく。
Particlesに託す行動と性質を階層的に表現する。最上部に望ましい状態を記入し、階層的に分解していく。分解した要素行動が必ず同時に必要か(AND)、いずれかの行動があればよいか(OR)を記入し区別する。行動の表現は、技術用語の持つ概念に拘束されないよう技術用語を避け日常の平易な言葉を使う。分解した要素行動をPartilesが実行するために持っているとよい性質を思いつくままに列挙する。
『Particlesが熱を消費する』要素行動への展開は、Particlesの概念を使うことで容易に創造しえた印象を持った。
図8 Particles法での問題状況分析結果
5−3.時間・空間特性の分析(Uniqueness分析)
問題の状況を多次元的に捉えるため、定義したモデルを時間・空間で展開する。
Uniqueness分析はTRIZの物理的矛盾の解消に対応している。
Uniqueness分析のアプローチは、以下の通りである。
a.問題状況の問題となる効果の空間特性を定性的に描く。
(理想解の状況をも重ねて描き対比する)
b.問題状況の問題となる効果の時間特性を定性的に描く。
図9 時間・空間特性の分析結果
6.解決策生成プロセス
USITに用意された解決策生成のアプローチは、4つある。今回のトレーニングセミナーでは、それぞれを充分理解するには至らなかった。当グループでは、早い段階で「対流を意図的に作る」というところに集中してしまい材料など実現手段に議論をすすみ時間を使ってしまった。後日、社内で担当者と最初から実施したときに、Particles法での分析段階で「熱を消費(変換)する」という方向性を得ることができた。(図8には、追加反映済み)
4つのアプローチの理解不足から前段での問題分析結果との対応がとれず、どの分析結果をどのアプローチで考察するのかに戸惑った。グループ発表もあるということで時間的に切迫し、BS法(ブレーンストーミング)的にでた結果だけに終わった。狙いとしていた分析結果に基づいた網羅的な解決コンセプトの生成には、至らなかった。
前段の問題分析の目的を十分理解しないまま作業的に進めていたせいで、方向性を持たず解決コンセプトを考え始めた。これは、USITのプロセスへの習熟で解決する問題であるが、当面はFord社の例に倣って検討グループに経験を持つメンバが入り、リードしていくことが有効と思われる。
図10 USIT法で示された4つの解決策生成アプローチ
6−1.「対流を意図的に作る」コンセプト
対流を意図的に作るという方向性で検討した結果、以下のようなアイデアが出た。
実際の筐体内でエントツ効果を狙い流路を設けるとなると上位目的の小型、高密度と矛盾してしまう。
これらのエントツ効果を狙う場合、生じる新たな課題解決が必要となる。
(1) 流路の断面積に差をつける。
(2) 流路を長くする。
(3) 流路によって温度勾配をつける。
(4) 流路の抵抗をなくす。
(5) 熱源を集中させる。
(6) 渦流をつくる。
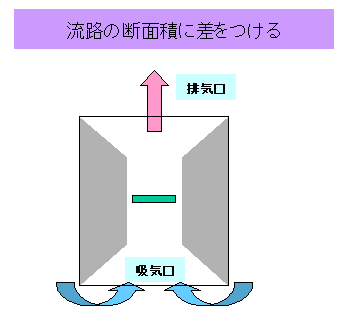 |
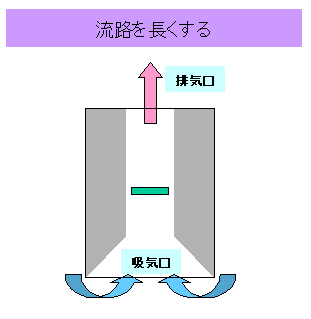 |
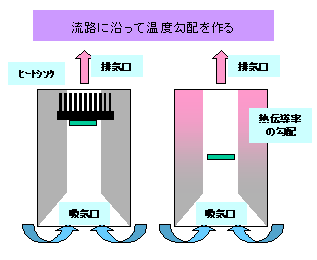 |
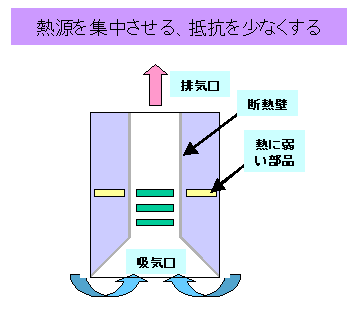 |
| 図12 解決策生成結果 | |
6−2.「熱を消費(変換)する」コンセプト
これは、社内で担当者と最初から実施したときにでてきたコンセプトである。
Particles法での分析段階で新たに出てきた「熱を消費(変換)する」という方向性からスタートした。ゼーベック効果は、TOPEのEffectモジュールを用いて検索した。特に電気へ変換するゼーベック効果は、変換した産物である電気は、すでに存在する配線を使用して逃がせること(新たなリソースを使用しない)やすでに腕時計で利用されていることからパッケージ方法や放熱効率の算出により具体化の可能性がある。
(1)電気に変換する → ゼーベック効果
(2)機械的に変換する → 形状記憶合金
図13 TOPE Effect モジュールの出力
7.まとめ
今回トレーニング内では、USIT法に期待した解決コンセプトを網羅的、体系的にまとめるという結果は得られなかった。しかし、後日検討した結果、2つ目の方向性(「熱を消費する」)を見出せたのはUSITによる問題分析の効果と考える。今回のコンセプトは、実現性を検討した結果、筐体内の配管することによるスペース効率の悪化や熱変換する素子の効率やコストにより開発検討には至らなかった。
後日談になるが、エントツ効果はトレーニング参加から半年あまり経過した8月に発売されたApple社のPowerPC G4 Cubeを見て驚いた。本体中央に下部から上部に突き抜ける冷却配管を設けて自然対流で熱を逃がす構造と発熱源を配管に実装する構造は、エントツ効果での解決コンセプトそのものであった。カタログから察するとCubeでは、ファンレス化という商品コンセプトが存在していたため、スペース効率という新たに生まれた課題に対しても解決策を見出して商品化に結び付けている。
ここで、気がついたのは問題定義のプロセスにおいて直接問題となっている熱の排出にとらわれて、高発熱部品を高密度に実装し、信頼性を確保するという製品の課題設定を見落としていたことである。
熱対策自体は、製品の機能のとしてはサブシステムであり製品としての基本機能ではないため、方式選択のためには、製品としてのシステム全体を定義して取り組む必要がある。
プログラムは、3日間でUSITの全てのプロセスを実践するもので作業に追われ、内容を消化するには時間的には厳しかった。セミナーでは、各プロセスでのエッセンスを理解することに重点をおき、後日再考することを前提にセミナー内で解決策を求めることに集中しない方が良いと思う。解決策を求める気持ちが強すぎるとBS的に発散したり、実現性に興味が移り、時間的に余裕がなくなる。プロセスを大切にして問題分析の結果に集中して討議をすすめるべきであったと反省している。
セミナーへの参加者としては、自身のテーマに拘らず、新鮮で興味を持てそうな課題を選択する方が、3日間のトレーニングを有意義に刺激的に過ごせるかも知れない。
8.参考文献
[1] 中川 徹(大阪学院大学)
:
USITトレーニングセミナーテキスト[2000.1.26−28]
編集ノート (中川 徹, 2001. 7. 4)
本稿は, オムロン株式会社の上野浩輝氏より, 投稿いただいたものです。著者のまえがきに記載されていますように, 2000年 1月26-28日に, 三菱総研主催で小生が講師をした3日間の「USITトレーニングセミナー」での事例です。著者自身が持ち込まれた問題について, 3名のグループ (そして全体で12名の参加者) が問題解決を図った事例です。
上記のUSITトレーニングセミナーは, さまざまな企業の人達が集まり, それでいて (教科書問題でない) 自分たちの実地の問題を共同で解決することを試みたものでした。関係者全員で誓約書に署名し, 6ヶ月間の守秘義務を負い, その後は技術内容を含めて公開可能という約束にしました。本件は, 本問題を提案した著者が, 自社内でのその後の検討をも含めて, 1年後に三菱総研の創造手法分科会で口頭発表され, 今回正式に本ホームページに投稿されたものです。
このような事例を公表いただきました 著者の上野浩輝氏 およびオムロン株式会社殿に, またセミナー主催者の三菱総合研究所知識創造研究グループに厚く感謝申し上げます。
著者: 上野 浩輝氏 Email: hiroki_ueno/OMRONJP@ns2.omron.co.jp
著者所属企業: オムロン株式会社 WWW: http://www.omron.co.jp/
セミナー主催者: 三菱総合研究所知識創造研究グループ WWW: http://www.internetclub.ne.jp/IM/
| 本ページの先頭 | 1. はじめに | 2. 想定した課題 | 3. セミナープログラム | 4. 問題定義プロセス | 5. 問題分析プロセス | 6. 解決策生成プロセス | 7. まとめ | 編集ノート | USITせミナー報告(中川) |
| ホームページ | 新着情報 | TRIZ紹介 | 参考文献・関連文献 | リンク集 |
| ニュース・活動 | ソフトウェアツール | 論文・技術報告集 | TRIZフォーラム | English
Home Page |
最終更新日
: 2001.7. 4 連絡先: 中川 徹 nakagawa@utc.osaka-gu.ac.jp