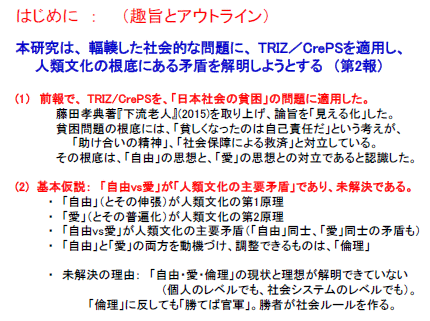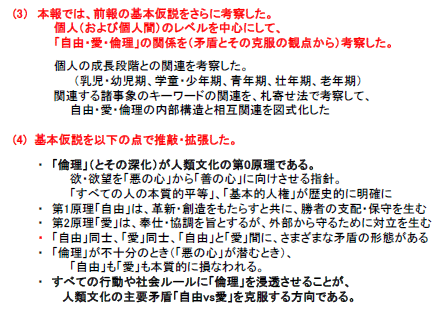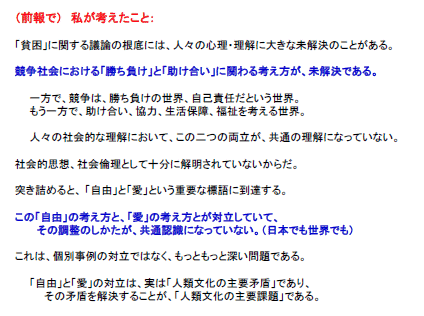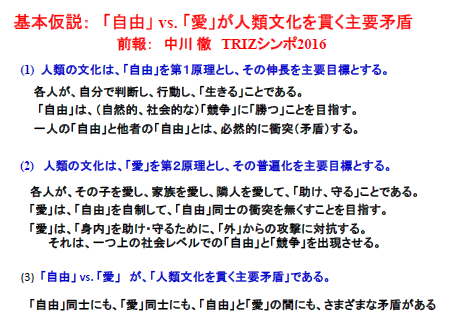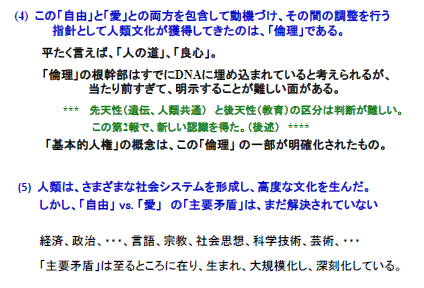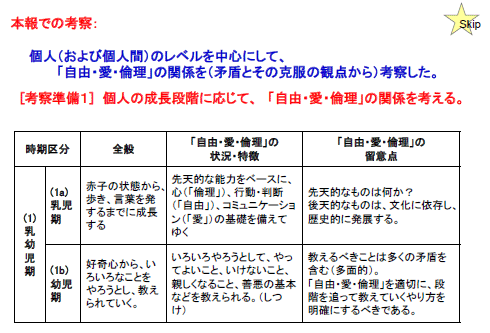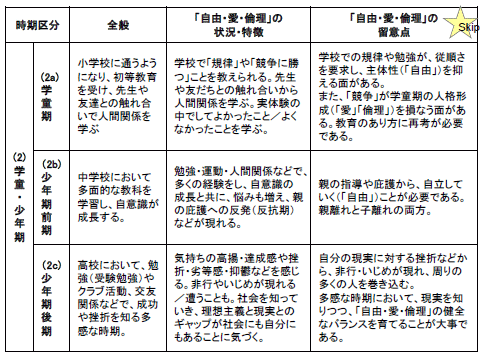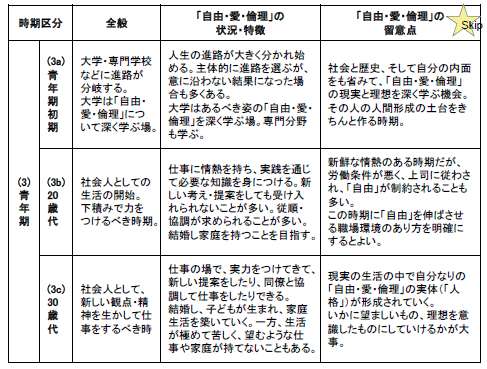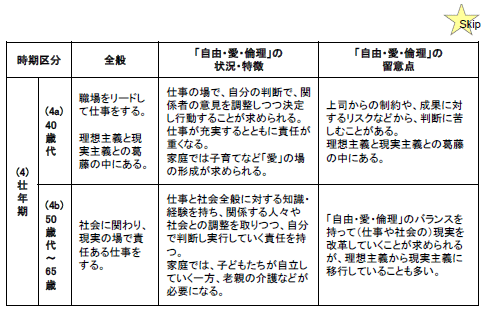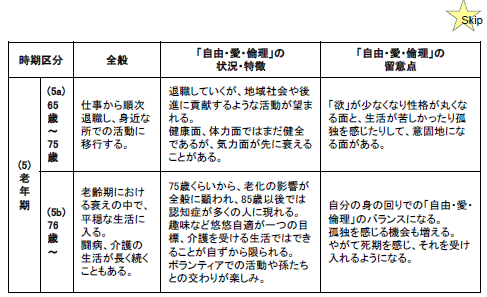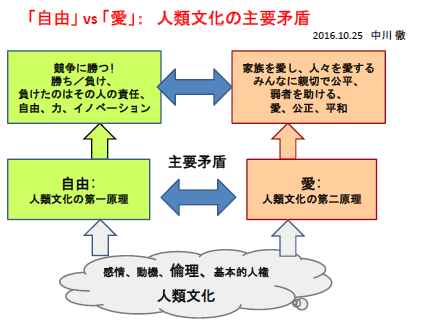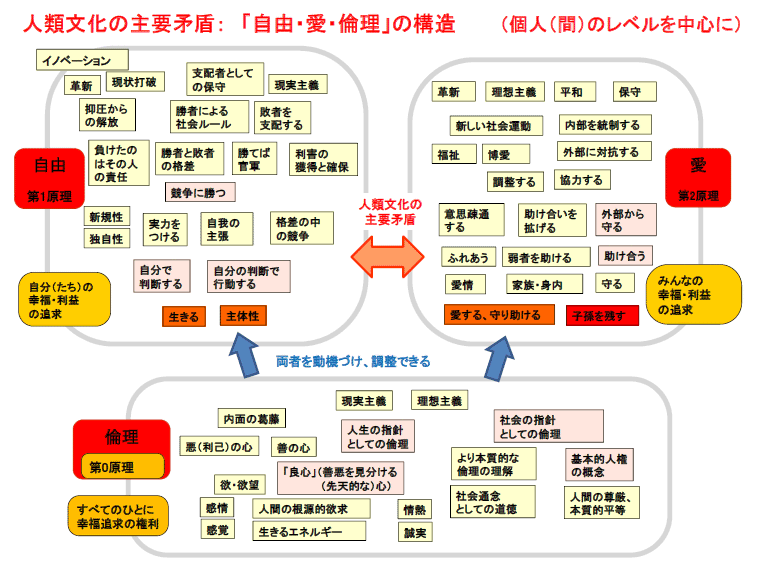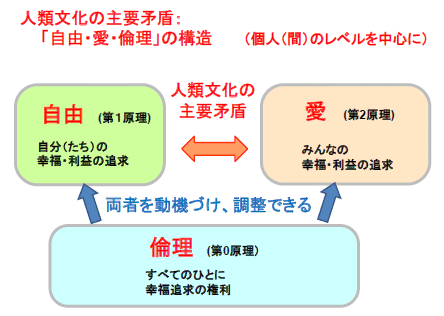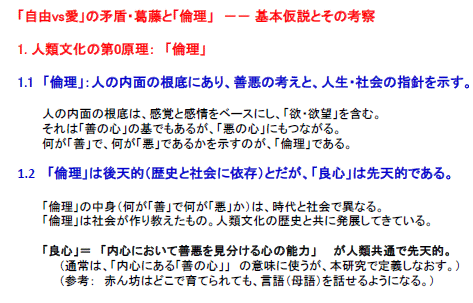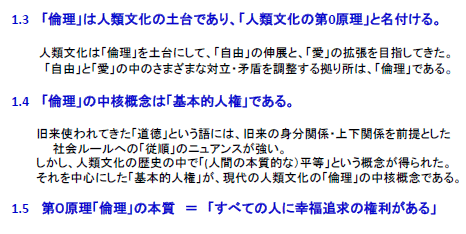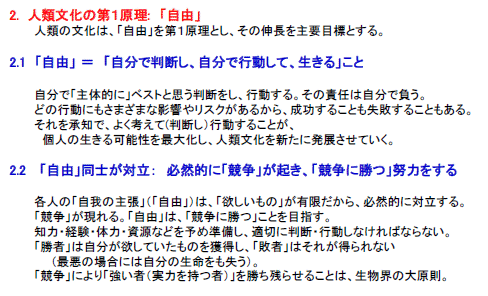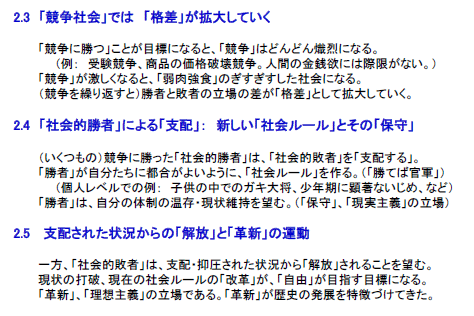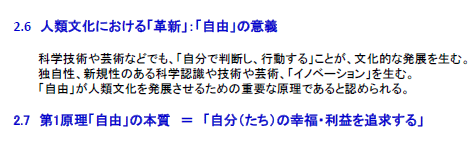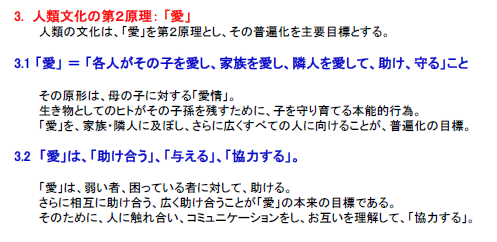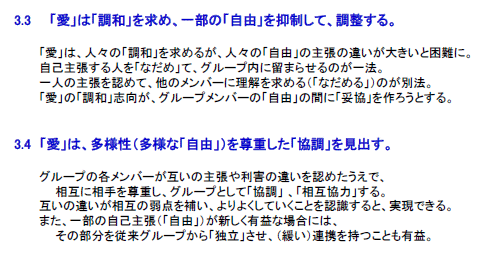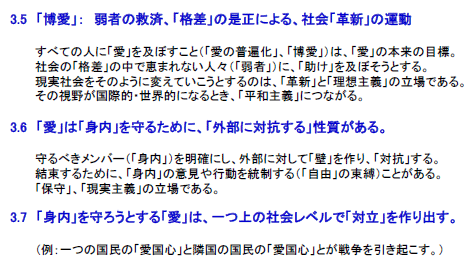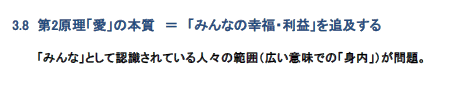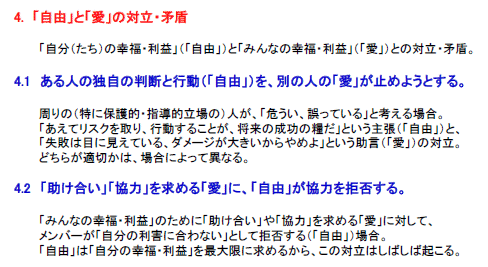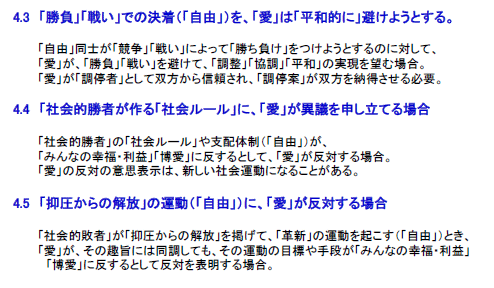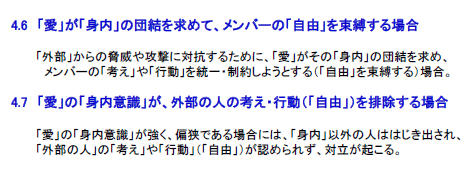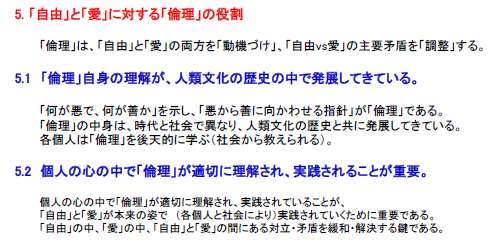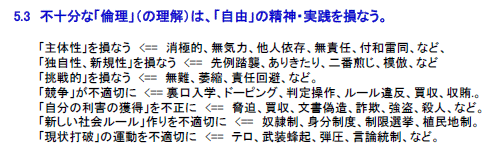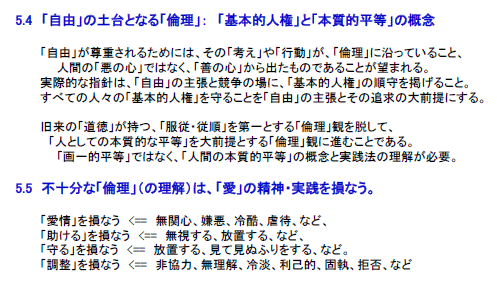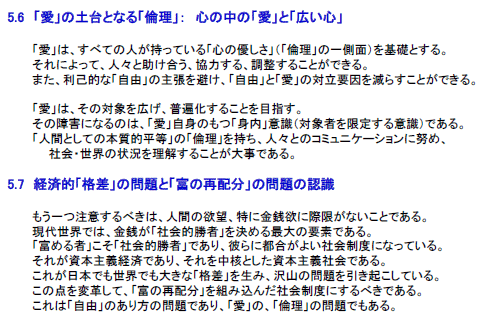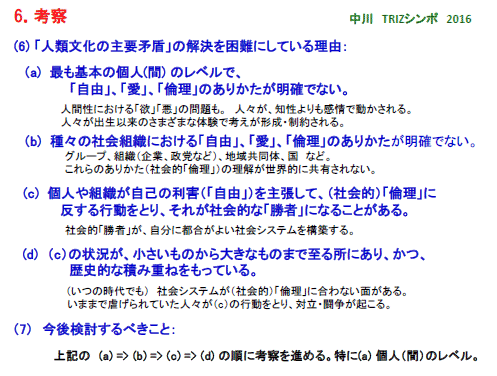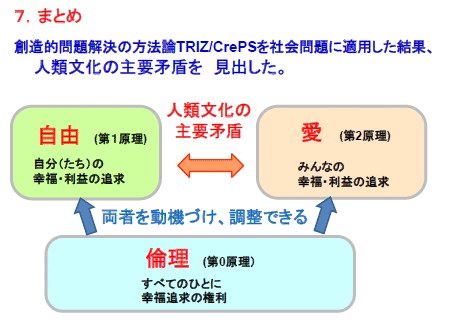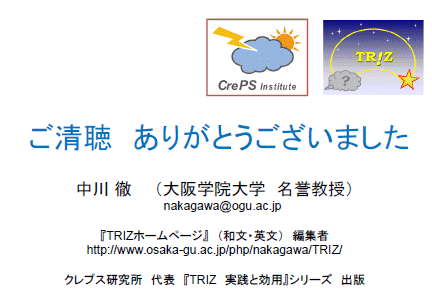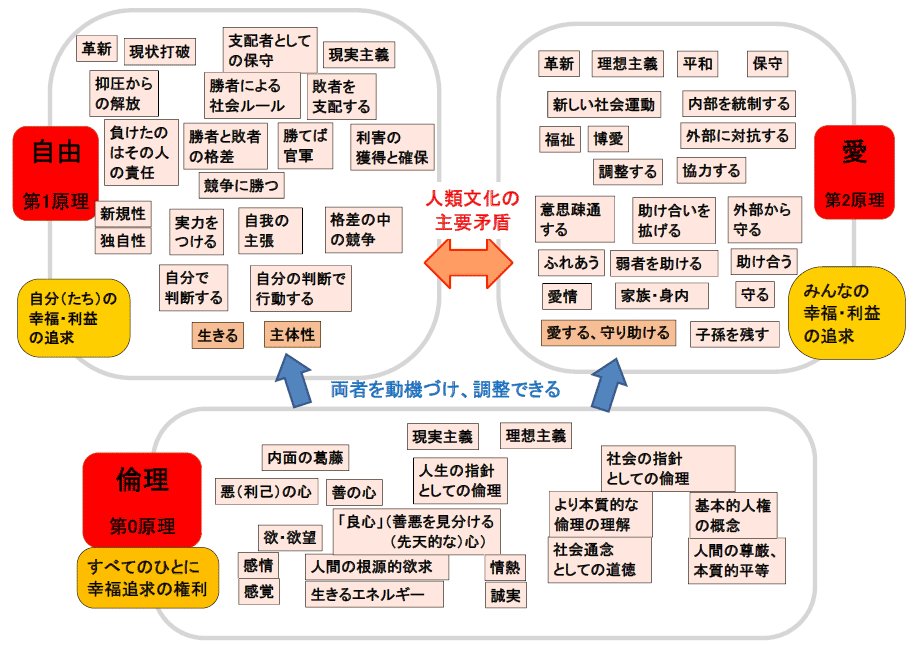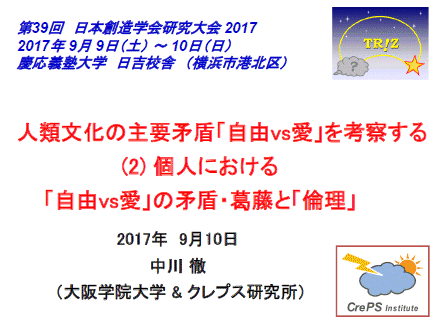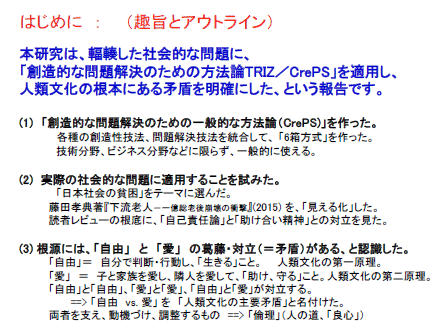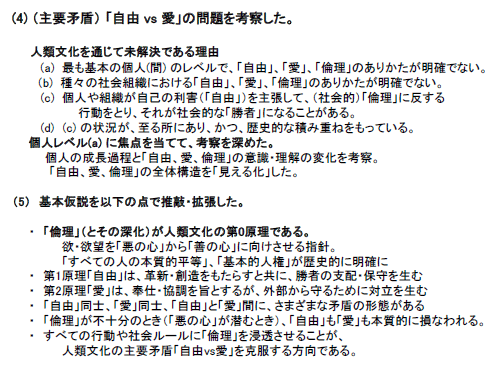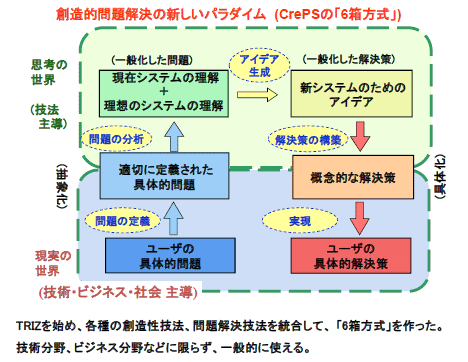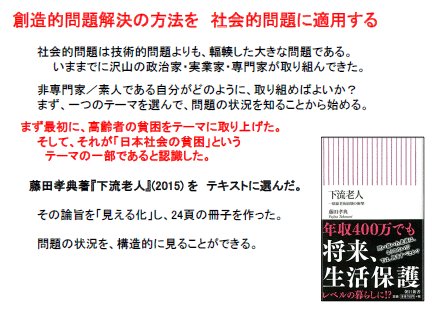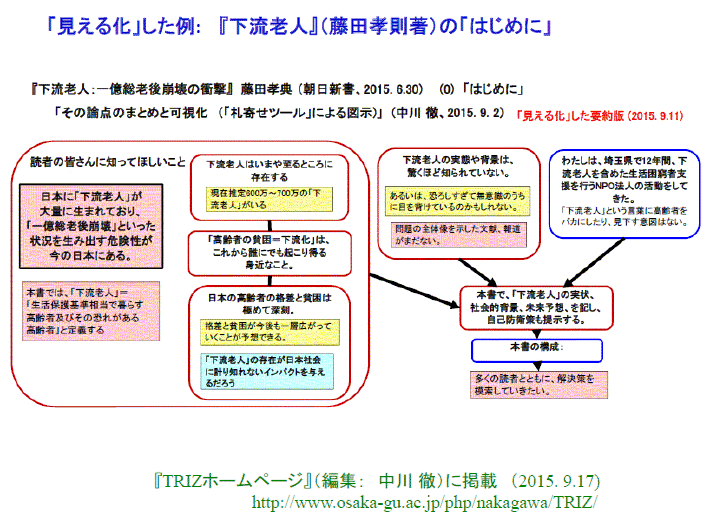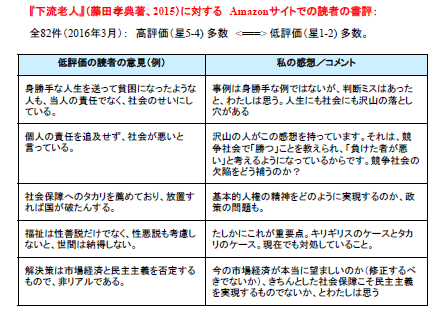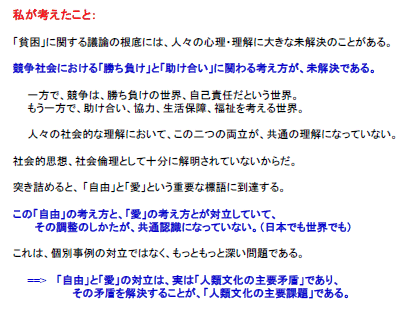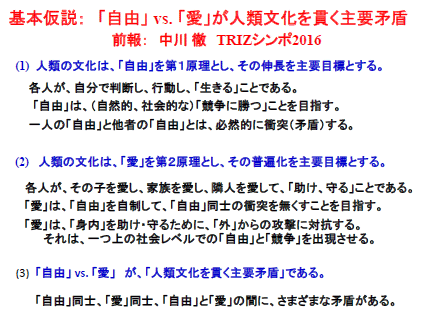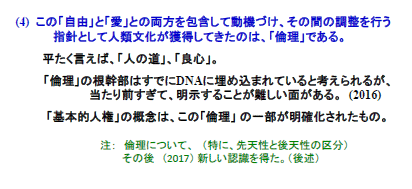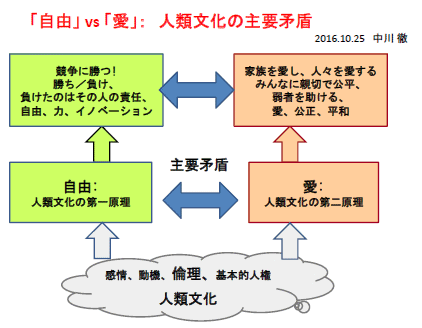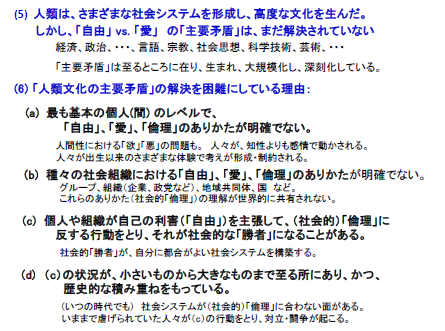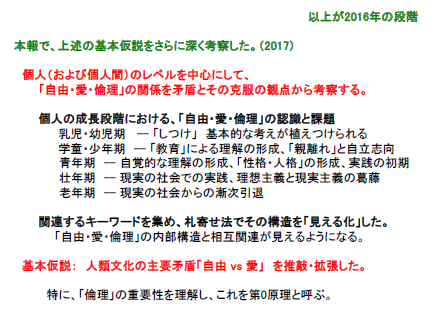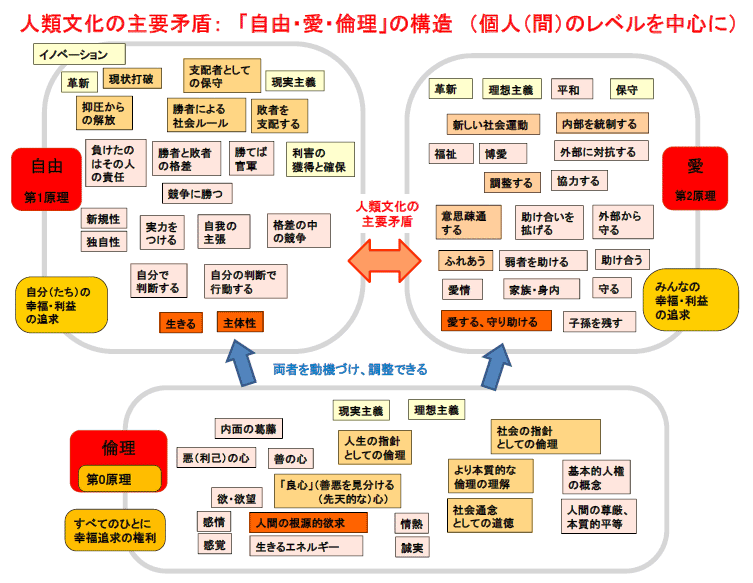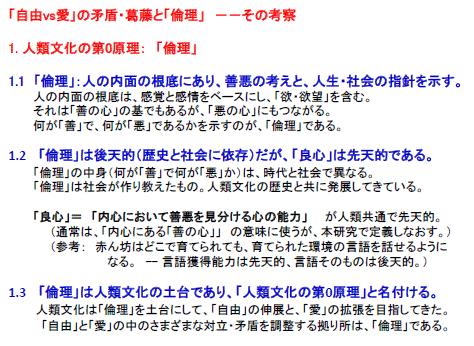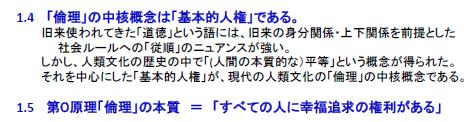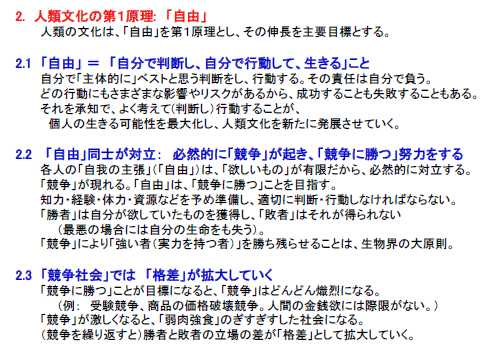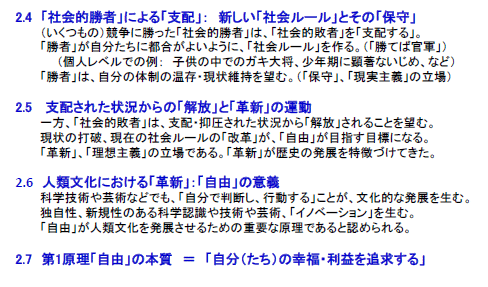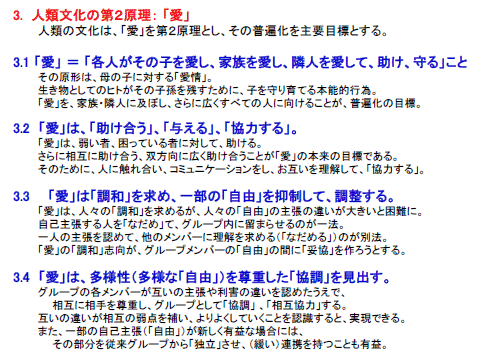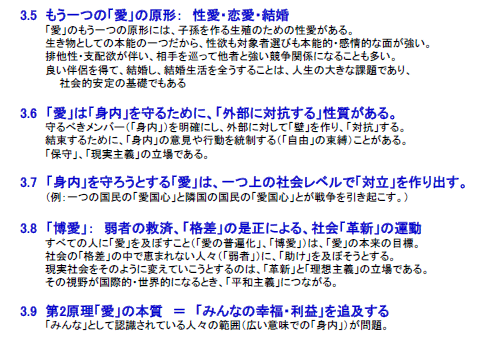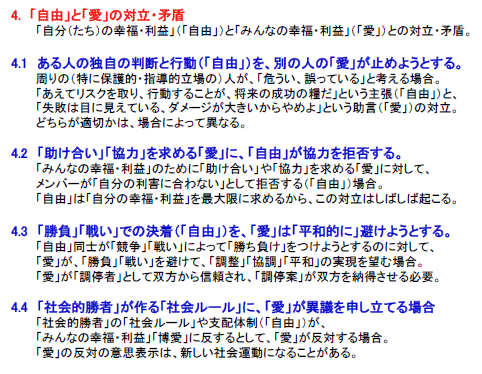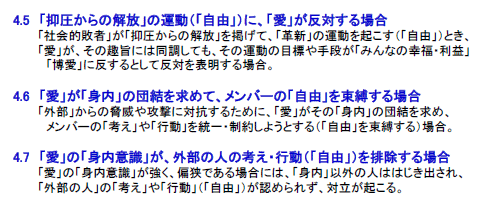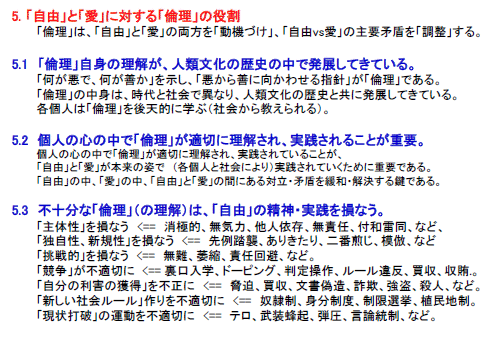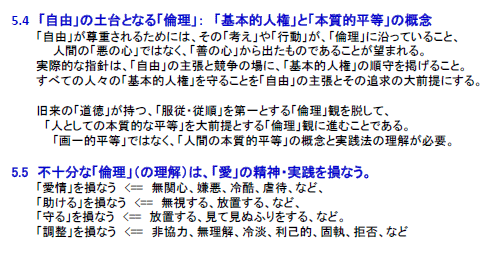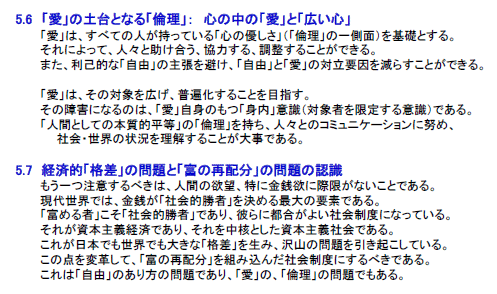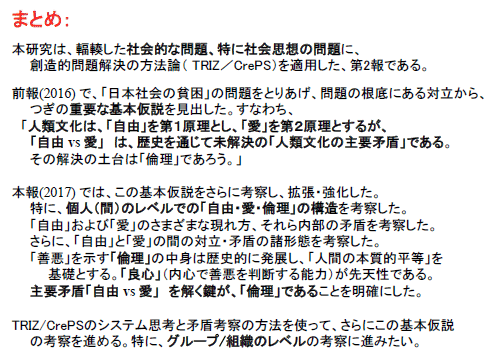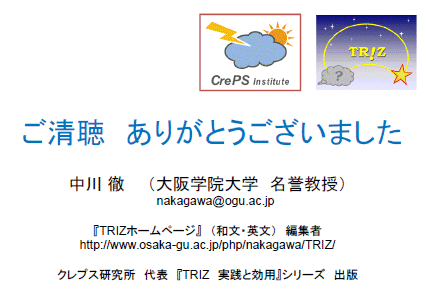TRIZ/CrePS 発表(社会問題) TRIZ/CrePS 発表(社会問題) |
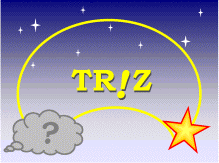
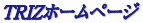  |
人類文化の主要矛盾「自由 vs 愛」を考察する
(2) 個人における「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」 |
中川 徹 (大阪学院大学 名誉教授 & クレプス研究所 代表)
|
(A) 第39回日本創造学会研究大会2017 発表、2017年9月9-10日 慶応義塾大学日吉校舎(横浜市港北区)
(B) 第13回日本TRIZシンポジウム2017 発表、
2017年9月21 - 22日 中野サンプラザ (東京都中野区)
(C) 欧州TRIZ協会(ETRIA) TRIZ Future Conference (TFC2017) 発表、2017年10月4-6日、Lappeenranta、フィンランド
(D) 拡張論文: 『TRIZホームページ』掲載、2018年 6月25日 
拡張論文英訳版: 『TRIZホームページ』掲載、2018年 8月14日 
|
掲載:2017. 9.27 ; 更新: 2018. 6.25; 8.14 |
Press the  button for going to the English page.
button for going to the English page.
 編集ノート (中川 徹、2017年 9月23日)
編集ノート (中川 徹、2017年 9月23日)
私は表記の演題で、日本創造学会研究大会と日本TRIZ協会TRIZシンポジウムとで、相次いで発表しました。ほぼ同じ内容ですが、原稿提出時期、提出形態が異なり、参加者層も違いますので、少しずつ調整した原稿と発表にしています。[また、10月4-6日には、欧州TRIZ協会のTFC2017でも同じ演題で発表します。]
[追記(中川、2018.6.20): ETRIA国際会議での発表論文が ETRIA Journal 上に正式に出版されました(2018. 3.18)ので、英文ページ に論文へのリンク
に論文へのリンク を張り、また、論文のHTML
を張り、また、論文のHTML と PDF
と PDF 、およびスライドのHTML
、およびスライドのHTML およびPDF
およびPDF  を掲載します。
を掲載します。
また、創造学会の発表論文(B)に「考察」の節を設け大幅に拡張した和文論文(D)を別ページに掲載しました 。下記の表にも追記します。]
。下記の表にも追記します。]
[追記(中川、2018.8.14): 拡張論文(D)を全文英訳して、掲載しました。 ]
]
本ページに掲載するものの関連を一覧表にして示します。開催順に示していますが、原稿提出が早かった順番は、TRIZシンポ、創造学会、ETRIA TFCの順でした。
学会発表では、論文のページ数が制約されており(創造学会A4最大8頁、ETRIA B5最大8頁)、発表時間も短く(創造学会とTRIZシンポは質疑込みで25分、ETRIA は20分)、要点だけを書く/話すことになりました。このため、3つの学会での発表の主要部はほぼ同じ情報になっています。日本創造学会は、創造性教育・創造技法・イノベーションなどやや広い分野を対象にしており、また昨年は発表していませんので、本研究の最初からの説明をしています。TRIZシンポは、分野がTRIZに集中しており、昨年も発表しましたので、比較的短い導入部だけで話しています。「自由・愛・倫理」の図式の簡略版を作ったのが効果的でした。ETRIAは10日先ですが、発表時間が短い上に英語ですから、もっと簡潔に話す必要があります。
各発表の構成(目次)を 一覧並記しておきます。(なお、創造学会の予稿集論文をさらに拡張して(考察部を記述し)、日本創造学会論文誌に投稿し、査読待ちです。)
| |
TRIZ シンポ 発表スライド  |
創造学会 論文  |
創造学会 発表スライド  |
導入 |
趣旨とアウトライン
|
はじめに |
趣旨とアウトライン |
|
|
|
創造的な問題解決の方法論 TRIZ/CrePS
社会的問題(高齢者の貧困)に適用する
その「見える化」、読者書評の分析 |
前報 |
問題の本質を捉える
基本仮説: 「自由」 vs. 「愛」が人類文化を貫く主要矛盾
「自由」 vs. 「愛」 の図式表現 |
|
問題の本質を捉える
基本仮説: 「自由」 vs. 「愛」が人類文化を貫く主要矛盾
「自由」 vs. 「愛」 の図式表現
主要矛盾の解決を困難にしている要因 |
本報の方法 |
個人の成長段階との関連
札寄せ法:「自由・愛・倫理」の図式
(前報、本報詳細版、簡略版) |
「自由・愛・倫理」の図式(詳細版) |
個人の成長段階との関連
「自由・愛・倫理」の図式(詳細版) |
本論 |
「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」
1. 第0原理「倫理」
2. 第1原理「自由」
3. 第2原理「愛」
4. 「自由」と「愛」の対立・矛盾
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割 |
「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」
1. 第0原理「倫理」
2. 第1原理「自由」
3. 第2原理「愛」
4. 「自由」と「愛」の対立・矛盾
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割 |
「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」
1. 第0原理「倫理」
2. 第1原理「自由」
3. 第2原理「愛」
4. 「自由」と「愛」の対立・矛盾
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割 |
| 考察 |
解決を困難にしている要因 |
|
|
| まとめ |
まとめ 「自由・愛・倫理」の図式簡潔版 |
6. まとめ |
6. まとめ |
なお、本ページの掲載にあたり、本研究で得た基本仮説の理解を次のようにまとめました(2017. 9.26)。
(1) 「倫理」(とその深化)が人類文化の第0原理である。人間の内面において、欲・欲望を「悪の心」から「善の心」に向けさせる指針である。「何が善で、何が悪か」という「倫理の内容」は、後天的に社会から教えられ、歴史と社会によって異なる。しかし、「内心において善悪を判断する心の能力(=「良心」)」が人類には先天的に備わっていると考えられ、それが人類文化の根源的な拠り所である。「すべての人の本質的平等」、「基本的人権」の概念が歴史的に明確になってきた。第0原理の本質は、「すべての人に幸福追求の権利がある」という原理である。
(2) 第1原理「自由」は、「自分で判断し、行動して、生きる」ことであり、競争に勝つことを目指す。革新・創造をもたらすと共に、勝者の支配・保守を生む。第1原理の本質は、「自分(たち)の幸福・利益を追求する」原理である。
(3) 第2原理「愛」は、「各人が子・家族を愛し、隣人を愛して、助け守る」ことであり、「自由」を自制し、奉仕・協調を旨とする。(広い意味の)「身内」を守ろうとして、外部と対立を生む面がある。第2原理の本質は、「みんなの幸福・利益を追求する」原理である。ここで、「みんな」として意識されている範囲が問題であり、この範囲の普遍化が課題である。
(4) 「自由」同士、「愛」同士、そして「自由」と「愛」の間に、さまざまな矛盾が存在し、その多数の類型を整理して示した。
(5) 「倫理」(の理解)が不十分のとき、すなわち、動機に「悪の心」(利己的な心)が(強く)潜むとき、「自由」も「愛」も(その精神や効果が)本質的に損なわれ、「自由 vs 愛」の矛盾が強く現れる。だから、各個人の内面と行動においても、またさまざまな社会組織の行動や社会ルールにおいても、「倫理」を浸透させること、特にその中核である「すべての人の本質的な平等」の精神を浸透させることが、人類文化の主要矛盾「自由vs愛」を軽減・克服するための鍵である。
(6) 突き詰めると、「自分(たち)の幸福・利益を追求する」「自由」と、「みんなの幸福・利益を追及する」「愛」に対して、その両者を動機づけ、同時に両者を調整して両者間の矛盾(「人類文化の主要矛盾」)を解決するのは、「すべての人に幸福追求の権利がある」という「倫理」(第0原理)である。
本研究で、個人のレベルでの問題とその解決の考え方が随分明確になりました。種々の社会組織・社会システムにおいて、この考え方を明確にしていくことが今後の大きな課題です。
(B) 日本TRIZシンポジウム2017
 発表概要 PDF
発表概要 PDF  (1頁、128 KB) (TRIZシンポ2017 Proceedings収録; 2017. 5.19提出)
(1頁、128 KB) (TRIZシンポ2017 Proceedings収録; 2017. 5.19提出)
人類文化の主要矛盾「自由 vs 愛」を考察する
(2) 個人における「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」
中川 徹 (大阪学院大学 & クレプス研究所)
第13回日本TRIZシンポジウム2017 発表
2017年9月21日〜22日 、中野サンプラザ (東京都中野区)
概要
本研究は、社会的な問題にTRIZ/CrePS方法論を適用した第2報である。前報で、人類文化の「第1原理:自由」と「第2原理:愛」とに対立があり、それが人類文化の歴史を通じて未解決の「人類文化の主要矛盾」であり、その対立を調整する可能性を「倫理」に求めた。
本報は、社会階層の根底である「個人(と個人間)のレベル」での、「自由・愛・倫理」の関係を詳しく考察した。人間の内面は、感覚・感情と「欲・欲求」がベースにあり、「悪の心」と「良心善の心」の葛藤がある。「悪の心」に打ち勝ち、根源的な生きるエネルギーと「良心善の心」を育む指針が「倫理」である。「自由 vs 愛」のさまざまな矛盾は、「倫理」が不十分なときに深刻化する。「倫理」、特に、「人間としての本質的平等」を中心とする「基本的人権」の概念が、主要矛盾「自由 vs 愛」を解決する鍵である
内容説明
本研究は、社会的な問題にTRIZ/CrePS方法論を適用した第2報である。前報では、日本社会における貧困の問題を考察し、国民の意識の中にある「自己責任論」と「助け合い精神」との対立が問題の根底にあることを認識した。その対立が、「競争に勝ち、生き残る」ことを目指す「自由」の原理と、「他を助け守り、協調する」ことを目指す「愛」の原理との対立であること。さらに、人類文化において第1原理の「自由」と第2原理の「愛」とが矛盾を内包し、「自由 vs 愛」が「人類文化の主要矛盾」であり、人類文化の歴史を通じて未解決であること、を認識した。また、自由と愛の両者を動機づけ調整しうるものが「倫理」であると考えた。
本研究では前報の考察をさらに進め、社会システムの階層の一番根底にある、「個人(および個人間)のレベル」での、「自由・愛・倫理」の構造を考察した。考察の方法として、一人の人の成長を年令時期(乳児・幼児期、学童・少年期、青年期、壮年期、老年期)で特徴づけ、その内面と行動のパターンを「自由・愛・倫理」の観点から理解した。ついで、これらに顕われた内面と行動を特徴づけるキーワードを多数列挙し、「札寄せ」法でその関係を「見える化」して、「自由・愛・倫理」の内部構造、矛盾・対立の構造を文章として書き出していった。その結果、前報を補強・発展させ、以下の理解を新たに得た。
(a) 個人の内面において、人間として望ましいあり方の指針を「倫理」と呼び、それを「人類文化の第0原理」とした。内面には、感覚・感情をベースにして、さまざまな「欲・欲求」がある。それは一面では「悪の心」になるが、同時に、生きるエネルギーや自己実現などの基本欲求と「良心善の心」になる。この「悪の心」に打ち勝ち「良心善の心」を育てようとする指針が「倫理」である。「人間としての本質的平等」を中心とする「基本的人権」の概念が、「倫理」の一部を明文化している。
(b) 第1原理:「自由」は、「自分で判断し行動して、生きる」ことを目指す。主体的に「自分の幸福と利益」を求め、「競争に勝つ」ことを目指す(「競争」は自分の「自由」と他者の「自由」との対立の典型である)。このようにして得られた「新しいもの(思想、文化、システムなど)」が、人類文化を発展させると理解される。「(社会的)勝者」は、自分(たち)に都合のよい(社会)ルールを作り、敗者・弱者を「支配する」(例:子どものガキ大将)。一方、いままで抑圧されていた者たちが、「自由」を主張して変革・革新を起こす。
(c) 第2原理:「愛」は、人を「愛し、助け、守る」ことである。「一方向の愛」から「双方向の愛」に、そして「助け合い」、「協力・協調する」方向を目指す。社会に虐げられている人(弱者)がいると、助けて、社会を「変革」しようとする。しかし他方、外部から危険があると、外部に対抗して、内部(「身内」)を守ろうとし、内部を統制・束縛することがある。
(d) 「自由」が「自分の幸福・利益」を求めるのに対して、「愛」は「みんなの幸福・利益」を求め、両者はさまざまに対立する(「矛盾」を持つ)。
(e) 各人の「倫理」が不十分のとき(例えば、「悪の心」を動機に持つとき)、その人が主張する「自由」も「愛」も本質的に損なわれる。だから、人々に「倫理」が正しく理解され、実践されていることが、「自由」をも「愛」をも有意義なものにし、「自由 vs 愛」という「人類文化の主要矛盾」を少しでも解決する根本基盤である。
 発表スライド (学会発表版) PDF
発表スライド (学会発表版) PDF  (33枚、382 KB) (TRIZシンポ2017 Proceedings収録版 から推敲 2017. 9.19 作成)
(33枚、382 KB) (TRIZシンポ2017 Proceedings収録版 から推敲 2017. 9.19 作成)

(0) はじめに (趣旨とアウトライン)
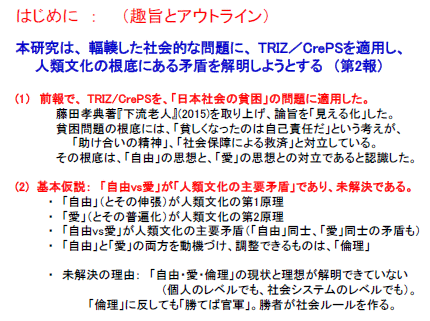
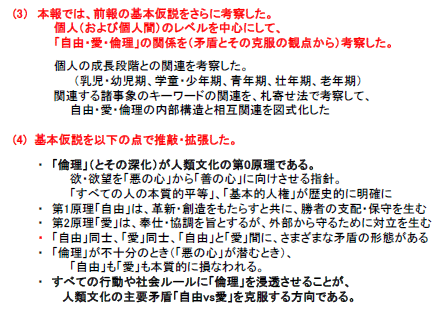
(1) 前報で考えたこと: 思考過程 と 基本仮説:「自由 vs 愛」が人類文化の主要矛盾
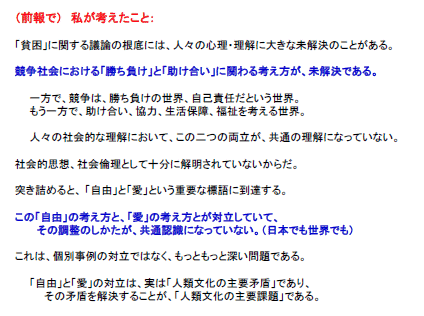
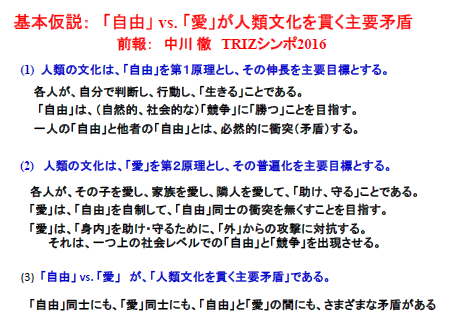
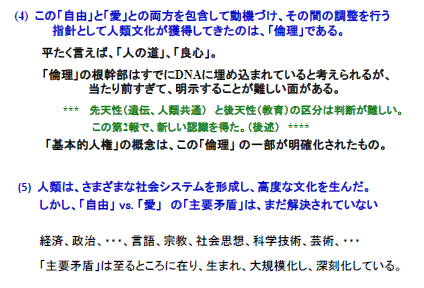
(2) 本報での考察1: 個人の成長段階に応じて、 「自由・愛・倫理」の関係を考える。
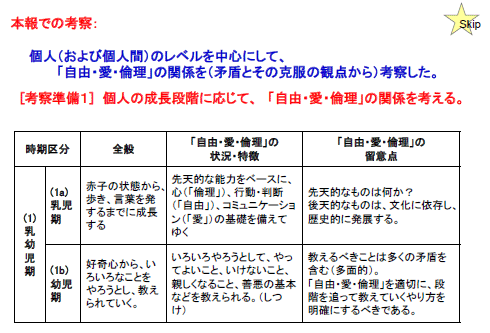
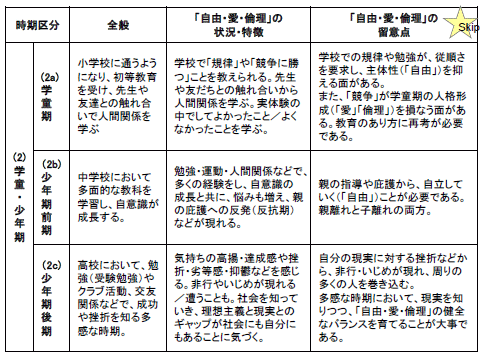
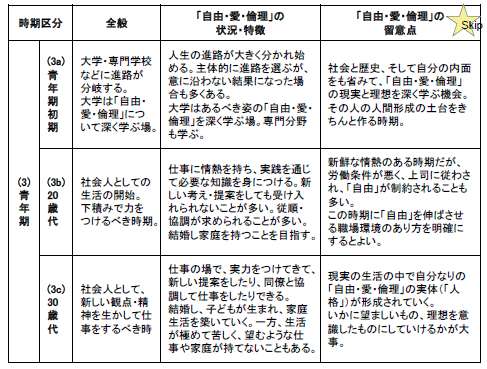
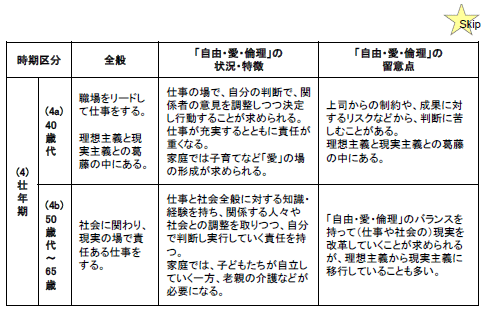
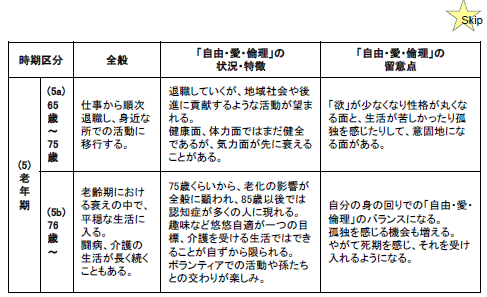
(3) 本報での考察2: 札寄せ法で 自由・愛・倫理の関係を「見える化」する
前報での図式
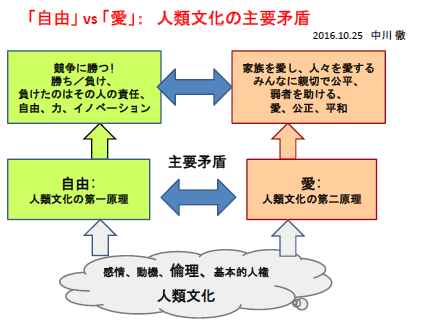
本報で得た図式(詳細版)
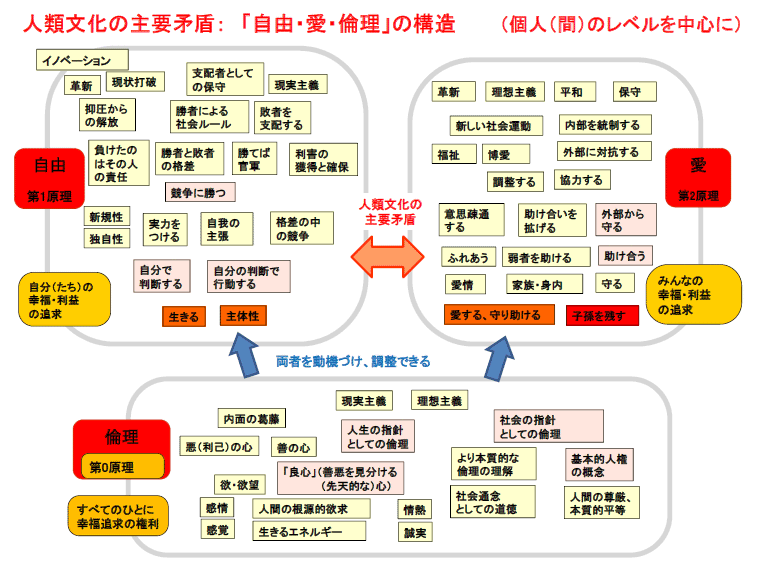
本報で得た図式(簡潔版)
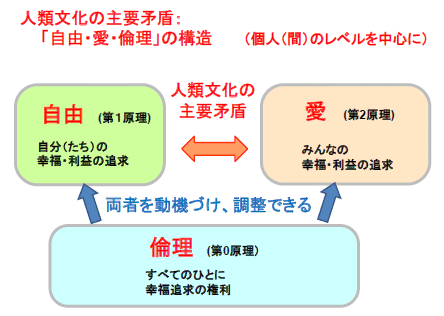
(4) 「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」 −− 基本仮説とその考察
1. 人類文化の第0原理: 「倫理」
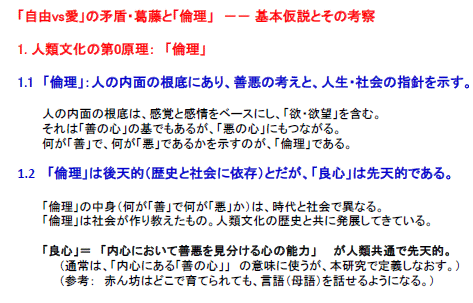
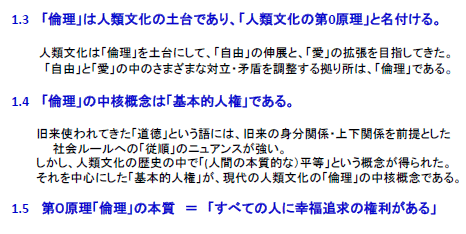
2. 人類文化の第1原理: 「自由」
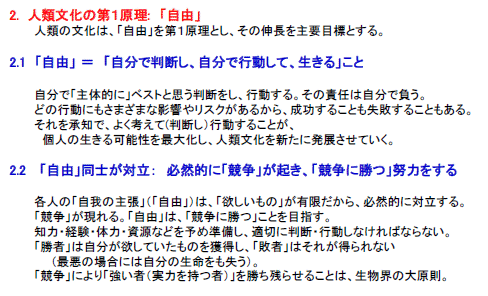
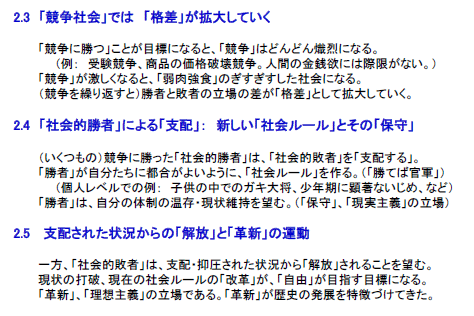
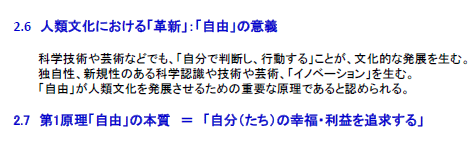
3. 人類文化の第2原理: 「愛」
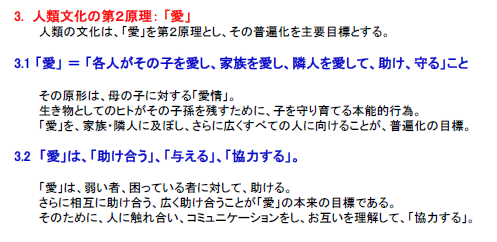
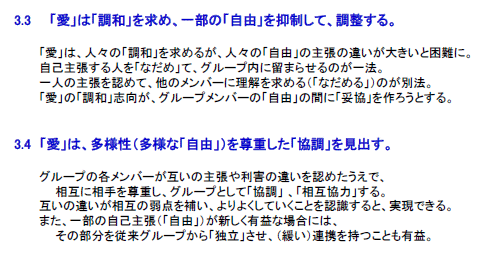
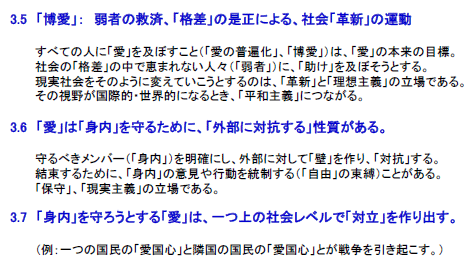
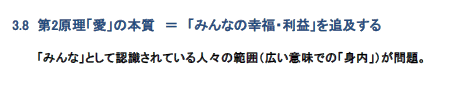
4. 「自由」と「愛」の対立・矛盾
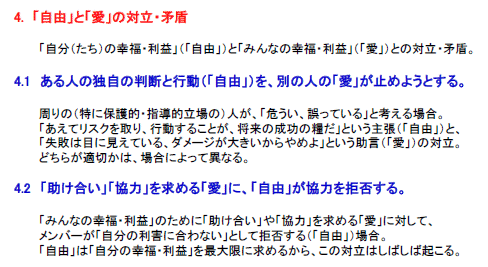
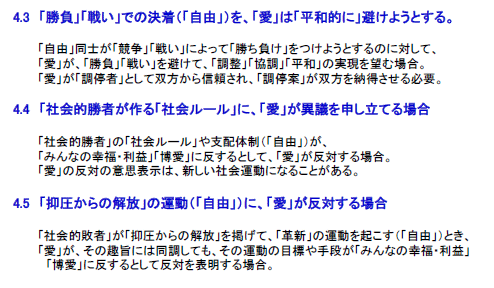
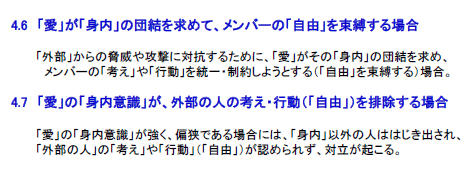
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割
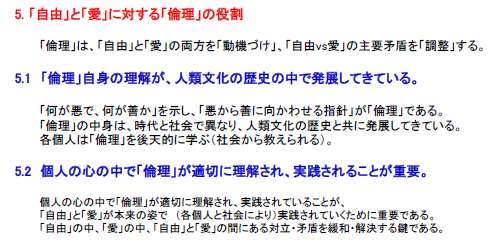
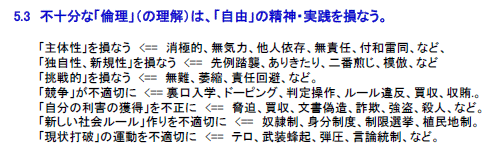
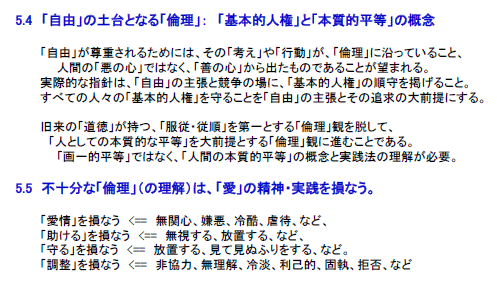
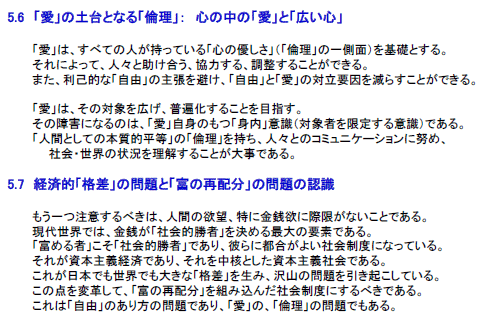
6.考察: 「人類文化の主要矛盾」の解決を困難にしている理由、 今後の課題
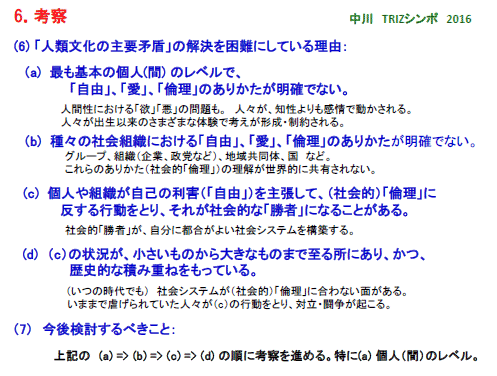
7. まとめ
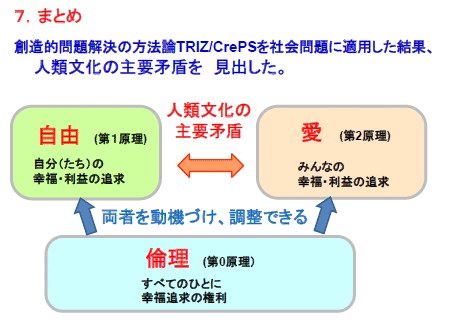
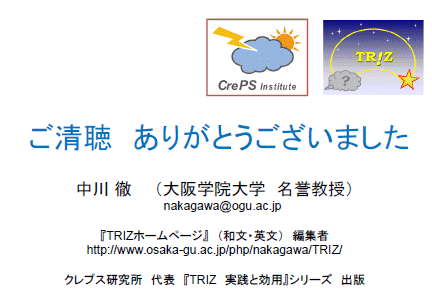
(A) 日本創造学会 第39回研究大会 2017 発表
 論文 (推敲版) PDF
論文 (推敲版) PDF  (8頁、491 KB) (Proceedings 掲載版(2017. 8. 1 提出) から推敲 (2017. 8.26))
(8頁、491 KB) (Proceedings 掲載版(2017. 8. 1 提出) から推敲 (2017. 8.26))
人類文化の主要矛盾「自由 vs 愛」を考察する
(2) 個人における「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」
'Liberty vs. Love': The Principal Contradiction of Human Culture
(2) The 'Liberty vs. Love' Contradiction and 'Ethics' at the Personal Level
中川 徹 大阪学院大学 名誉教授 & クレプス研究所 代表
Toru Nakagawa (Osaka Gakuin University & CrePS Institute)
概要
本研究は、社会的な問題に「創造的な問題解決の方法論TRIZ/CrePS」を適用した第2報である。前報で、人類文化の「第1原理:自由」と「第2原理:愛」とに対立があり、それが人類文化の歴史を通じて未解決の「人類文化の主要矛盾」であることを認識し、その対立を調整する可能性を「倫理」に求めた。本報は、社会階層の根底である「個人(と個人間)のレベル」での、「自由・愛・倫理」の構造を詳しく考察した。人間の内面は、感覚・感情と「欲・欲求」がベースにあり、「悪の心」と「善の心」の葛藤がある。「悪の心」に打ち勝ち、根源的な生きるエネルギーと「善の心」を育む指針が「倫理」である。「自由 vs 愛」のさまざまな矛盾は、「倫理」が不十分なときに深刻化する。「倫理」、特に、「人間としての本質的平等」を中心とする「基本的人権」の概念が、主要矛盾「自由 vs 愛」を解決する鍵である。
0. はじめに
本研究は、社会的な問題に「創造的な問題解決の方法論TRIZ/CrePS」 [1] を適用した第2報である。前報 [2] では、日本社会における貧困の問題を考察し、国民の意識の中にある「自己責任論」と「助け合い精神」との対立が問題の根底にあることを認識した。その対立が、「競争に勝ち、生き残る」ことを目指す「自由」の原理と、「他を助け守り、協調する」ことを目指す「愛」の原理との対立であること。さらに、人類文化において第1原理の「自由」と第2原理の「愛」とが矛盾を内包し、「自由 vs 愛」が「人類文化の主要矛盾」であり、人類文化の歴史を通じて未解決であること、を認識した。また、自由と愛の両者を動機づけ調整しうるものが「倫理」であると考えた。
本研究では前報の考察をさらに進め、社会システムの階層の一番根底にある、「個人(および個人間)のレベル」での、「自由・愛・倫理」の構造を考察した。考察の方法として、一人の人の成長を年令時期(乳児・幼児期、学童・少年期、青年期、壮年期、老年期)で特徴づけ、その内面と行動のパターンを「自由・愛・倫理」の観点から理解した。ついで、これらに顕われた内面と行動を特徴づけるキーワードを多数列挙し、「札寄せ」法でその関係を「見える化」して、「自由・愛・倫理」の内部構造、矛盾・対立の構造を考察した。さらに、その考察結果を文章として書き出し、前報を補強・発展させた新しい理解を得、「仮説」としてまとめた。
図1に「自由・愛・倫理」の構造の図示を示し、1節以下に得られた理解を整理して述べる。
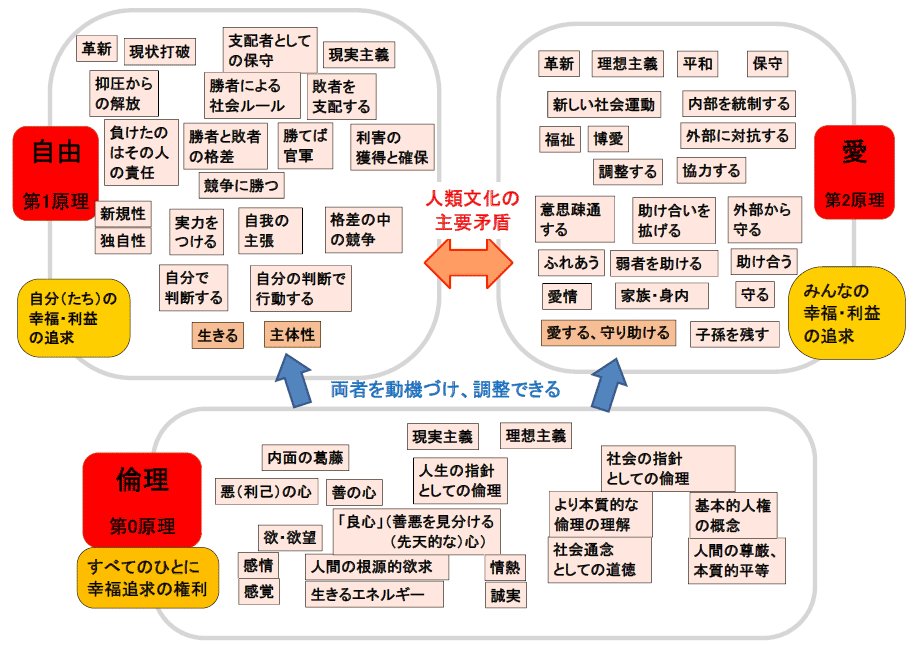
図1.人類文化の主要矛盾:「自由・愛・倫理」の構造 (個人(間)のレベルを中心に)
なお、本研究テーマでは、(古今東西無数の人びとの考察・著述がある)個別項目に立ち入ることをせず、全体的な構造の明確化に努める。
1. 人類文化の第0原理:「倫理」
1.1 人間の内面の根底と、人類文化の第0原理としての「倫理」
人間の内面の根底は、感覚と感情をベースにし、さらに生き物としてまた人間的な「欲・欲望」を含んでいる。それは、生きるエネルギー、特に人間としての根源的な欲求(幸せを求め、自己実現を求める欲求など)を内在し、誠実、情熱、優しさなど、人の「善の心」の基になっている。
しかし、人間の「欲・欲望」には、他を害しても自分が得しようとする「悪の心」につながる面がある。人間の内面にはこのように「善の心」と「悪の心」が同時に存在し、互いに矛盾し、葛藤している。この内面の葛藤において、何が「善」で、何が「悪」であるかを示すのが「倫理」である。それは人の人生の指針をなすと同時に、社会の指針の基礎でもある。この認識から、本研究で「倫理」を人類文化の第0原理と呼ぶ。
1.2 「良心」の先天性と「倫理」の後天性
何が「善」であり、何が「悪」であるかという内容(すなわち、「倫理」の中身)は、時代と社会によって異なるものであり、それぞれの時代の社会で作られ教え込まれてきた。そしてそれらが相互に影響を与えつつ、人類文化の歴史と共に発展してきた。では、人類文化で共通のもの、DNAに組み込まれ先天的なものはないのか?私は、「良心」がそれだ、と考える。「内心において善悪を見分ける(先天的な)心の能力」をここで「良心」と呼ぶ。(なお、このような先天的能力の仮定は、言語能力の場合を参考にしている。すなわち、赤ん坊は、生まれの遺伝背景によらず、どこで育てられても育てられた家族・地域の言葉を理解し話せるようになる。言語そのものは後天的に学ぶのだが、言語を理解し話せるようになる能力は先天的に備わっている。)「良心」を人類が共通に持っているという理解は、人類文化を考えるときの大きな拠り所となる。
1.3 人類文化における「倫理」の位置づけ
人類の文化は、この「倫理」を土台にして発展し、自分で判断し行動して最大限の自己実現を目指す「自由」の伸展と、他者を愛し助け守ってみんなの幸福を実現しようとする「愛」の拡張(普遍化)に向かって進んできた。しかし、「自由」と「愛」のそれぞれにもまた相互にも対立・矛盾があることが明確になっている。それらの矛盾を調整する(解決する)ための拠り所となるのは、土台にある第0原理の「倫理」であると考えられる。
1.4 「倫理」の中核概念としての「基本的人権」
「倫理」に近い日本語として「道徳」があるが、そこには(旧来の身分関係・主従関係を前提とした)社会ルールへの「従順」「服従」というニュアンスが強い。しかし、人類文化の歴史の中で「(人間の本質的な)平等」という概念が得られ、さらに明確化されて、現代では「基本的人権」が人類文化を調整する基本的な(明示された)「倫理」概念になっている。この意味で、古い「道徳」の「服従」思想を克服した「倫理」観が大事である。
「自由」と「愛」の両者を動機づけ、両者の矛盾を調整するのが「倫理」であるという認識は、「自由」と「愛」が、「基本的人権」で代表される「倫理」を尊重する(「基本的人権」を損なわない)ことを要請する。
1.5 第0原理「倫理」の本質:「すべての人に幸福追求の権利がある」
「倫理」を端的にいうと、「すべての人に「幸福追求の権利」がある」、という原理である。
2. 人類文化の第1原理:「自由」
人類の文化は、「自由」を第1原理とし、その伸長を主要目標とする。
2.1 「自由」は、「自分で判断し、自分で行動して、生きる」こと
第1原理の「自由」は、各人が「生きる」ために、「自分で判断し」、「自分で行動する」ことである。それを最大限に伸展させることを目指す。それは「主体性」と言ってもよい。
「自分で判断する」ことは、判断を他の人に依存しないことであり、自分が「生きる」ためには(「生き残る」ためには)、自分でその場その場でベストの判断をし、その責任を自分で負うことである。これは、新しい考え、独自性のある考えを生み出す可能性がある。そのような新しさが、人類文化を新たに発展させていくのだと、理解されている。
さらに、「自分の判断」をベースに、「自分で行動する」。自分でベストと考える行動をすることが、自分の自我を主張し獲得するための、つまり自分が「生きる」(「生き残る」)ためのベストのやり方だと、この第1原理では理解されている。もちろんどの行動にもさまざまな影響があり、リスクがあるから、成功することも失敗することもある。それを承知で、よく考えて(判断し)行動する、その結果に自分が責任を負う、というのが、「自由」の原理である。
2.2 「自由」同士の対立:「競争」の必然、「競争に勝つ」努力
自分の「自我の主張」(すなわち、「自由」の主張)は、多くの場合に他の人の「自我の主張」と対立する。人間が「欲しいもの」の対象(例えば、食料、住居、結婚相手、就職のポスト、など)は有限だから、そのような対立が必然的に起こる。その対立は、「競争」として現れる。
「自由」の原理は、そのような「競争に勝つ」ことを目指す。実際の人間社会では、競争者の間に有利・不利の差があることはしばしば起こる。その不利をも克服して「競争に勝つ」ことを目指すのである。競争の「勝者」は、自分が欲していたものを獲得し、「敗者」にはそれが得られない(最悪の場合には自分の生命をも失う)。
そこで、自分が適切に判断し、それを行動に移して、よい結果を得ることができるためには、(「競争」の場では特に)自分がしっかり判断・行動できるような力(実力)を備えなければならない。実現したいと思うこと(「自我主張」の内容)に応じて、知力も経験も体力も資源も(そのような実力の一部として)必要であろう。
2.3 「競争社会」と「格差」
「競争に勝つ」ことを目指す「自我」(「自由」)の主張が、むき出しで現れると、「競争」はどんどん熾烈になる。例えば、受験競争は受験者の平均レベルが上がるほど一層厳しくなるし、商品の販売競争・価格破壊競争でも同様であり、人間が富を求める金銭欲には際限がない。そして、「競争」が激しくなると、「弱肉強食」のぎすぎすした社会になる。勝者は次の競争でより有利になるから、勝者と敗者の立場の差が「格差」として社会的に拡大していく。
2.4 「社会的勝者」による「支配」:新しい「社会ルール」とその「保守」
社会的な(いくつもの)競争に勝った「社会的勝者」は、「社会的敗者」を「支配する」。これは社会システム(組織や制度)の場合に顕著である。「勝てば官軍」の諺があり、「勝者」の利害に応じて、「勝者」に都合がよいように、社会的ルールが作られていく。また、このことは個人同士のレベルでも起こる。子供の中でのガキ大将、少年期に顕著ないじめ、部活動での先輩と後輩、職場でのベテランと新人、家庭内暴力 (ドメスティックバイオレンス(DV))など、いろいろなところで見られる。このような「勝者」は、「支配者」として自分が作った体制(社会ルールなど)の温存・現状維持を望む。それは、「保守」の立場であり、(「理想主義」と対置した)「現実主義」の立場である。
2.5 支配された状況からの「解放」と「革新」
一方で、「社会的敗者」であった者には、支配された状況、抑圧された状況から「解放」されることが、自分(たち)の大きな利益である。そこで、現状を打破する、現在の社会ルールを「改革」することが、「自由」が目指す大きな目標になる。それは、「革新」の立場であり、一つの「理想主義」の立場である。このような「革新」が人類文化の歴史の発展を特徴づけてきた。
2.6 人類文化における「革新」:「自由」の意義
なお、このような社会的な革新でない場合にも、「自分で判断し、自分で行動する」ことが、 (科学技術や芸術など)文化的な革新を生み、発展を生むと理解されている。独自性、新規性のある科学認識や技術や芸術を生むからである。「イノベーション」は「自由」にとっての大きな目標である。この意味で、「自由」が人類文化を発展させるための重要な原理、必須の原理、とみなされる。そこで、「自由」を人類文化の第1原理と呼ぶ。
2.7 第1原理「自由」の本質:「自分(たち)の幸福・利益を追求する」
「自由」を端的にいうと、「自分(たち)の幸福・利益を追求する」原理である。
3. 人類文化の第2原理:「愛」
人類の文化は、「愛」を第2原理とし、その普遍化を主要目標とする。
3.1 「愛」は、「各人がその子を愛し、家族を愛し、隣人を愛して、助け、守る」こと
第2原理である「愛」の原形は、母の子に対する「愛情」である。それはもともと、生き物としてのヒトがその子孫を残すために、子を守り育てる本能的行為である。母は生まれてきたわが子に対して自然に(本能的に)可愛がり、母乳を与え、危険から守り、育てる。その愛は幼児・学童期はもちろん、子どもが自立して以後も続くのが普通である。子どもは、母および家族の愛を感じつつ成長するのが、望ましい姿である。
このような「愛」が、親から子に向かうだけでなく、家族に対し、隣人に対して向けられ、さらにいっそう広くすべての人に向けられ、かつ双方向になることことが、第2原理としての「愛」の普遍化の方向性である。
3.2 「愛」は「助け合う」、「与える」、「協力する」
「愛」には、「助ける」という面がある。(わが子だけでなく)弱い者、困っている者に対して、(少しでも余力がある者が)金銭や助言や助力を与えて助ける。さらに相互に助け合う、お互いの不足しているもの、困っていることを補いあう。その助け合いを家族だけでなく、隣人、友人などに広げていく。これが第2原理の「愛」の本来の方向である。
「愛」は、相手に「与える」こと、奉仕することが基本である。このような「愛」は、人と人とが触れ合う、コミュニケーションを取ることが前提になる。その中でお互いを理解して、一方向から双方向になり、「協力する」ことに発展していく。
3.3 「愛」は「調和」を求め、一部の「自由」を抑制する
「愛」には、自分の周りの人たちの「調和」を作るように、調整していこうとする働きがある。自分が、親のように振る舞い、助け、守り、奉仕することによって、その人々のグループ(「身内」)に調和ができるかもしれない。
しかし、関係する人々の人数が増え、多様性が増大して、それぞれが欲すること(「自由」の主張)が違ってくると、だんだん調整が難しくなる。一つのやり方は、自己主張する人を「なだめ」て、グループ内に留まらせることであるが、それは多少の不満を内包することになる。もうひとつのやり方は、自己主張する人の主張を基本的に認めて、他のグループメンバーに理解を求める(場合によっては「なだめる」)ことである。これらの場合には、「愛」による「調和」の志向が、グループ内の人々の「自由」の主張の間に「妥協」を作ろうとすることになり、(特に激しく主張する)一部の人の「自由」の追求と対立(矛盾)することになる。
3.4 多様性(多様な「自由」)を尊重した「協調」(「愛」)
もっと望ましいのは、グループの各メンバーが互いの主張や利害の違いを認めたうえで、相互に相手を尊重し、グループとして「協調」することが有益であると認識することである。特に、互いの違いが相互の足りないところを補い、互いによりよくしていくようにする(また、そう認識する)と非常に良い。これらは、多様性をベースにした上での相互協力であり、相互の「自由」に対する理解と「愛」が働いた望ましい姿である。
あるいはまた、一部の自己主張(「自由」)が新しく有益であるという場合には、その一部を従来のグループから「独立」(スピンアウト)させた上で、(緩い)連携を持つことが有益であろう。
3.5 もう一つの「愛」の原形:性愛・結婚
「愛」の原形には、母の子に対する愛情の他に、子孫を作る生殖のための性愛がある。これは生き物としての根源的な本能の一つだから、性欲も対象者選びも本能的・感情的な面が強い。排他性・支配欲が伴い、相手を巡って他者と強い競争関係になることも多い。良い伴侶を得て、結婚し、結婚生活を全うすることは、人生の大きな課題であり、社会的安定の基礎でもある。
3.6 「愛」は「身内」を守るために、「外部に対抗する」性質がある。
「愛」のもう一つの面として、(自分の子どもや家族に限らず)自分たちのメンバーを、外部の危険から「守ろう」とする働きがある。そのためには、守るべきメンバー(「身内」)を明確にし、外部に対して「壁」を作って、外部からの危険を防ぎ、さらに外部に「対抗」しようとする。そのときに「身内」の結束を強める目的で、「身内」の中での意見や行動を統制する(すなわち、「自由」を束縛する)ことがある。これは「保守」の立場であり、「現実主義」の立場である。
3.7 「身内」を守ろうとする「愛」は、一つ上の社会レベルで「対立」を作り出す。
さらに、上記の「身内」を一つの(社会)組織と考え、一つ上の社会レベルでの一つの活動単位と考えると、そのレベルで新しい組織間の対立(競争や戦い)が生じていることが分かる。最も分かりやすい例は、一つの国民の「愛国心」とその隣国の国民の「愛国心」とが数々の戦争を引き起こしている歴史である。
3.8 「博愛」:「格差」の是正と社会の「革新」
多くの人々の中に「格差」があり、不当に不利なあるいは恵まれない人々がいるときに、それらの人々に「愛」が及ぶようにしようというのは、「愛」の本来の考え方である。「愛」の対象をできるだけ広げること、すべての人に「愛」を及ぼすこと(「愛」の「普遍化」、「博愛」)は、第2原理「愛」の本来の方向である。現実社会をそのような方向に変えていこうとするのは、「革新」の立場であり、「理想主義」の立場である。「愛」を広げていこうとする視野が国際的・世界的になるとき、それは「平和」を希求する立場、「平和主義」につながる。
3.9 第2原理「愛」の本質:「みんなの幸福・利益を追及する」
端的にいうと、第2原理「愛」は、「みんなの幸福・利益を追及する」。ここで注意するべきは、「みんな」という言葉で認識されている人々の範囲である。これは広い意味での「身内」であり、それが「全世界のすべての人」を意味するのはずっと上のレベルである。
4.「自由」と「愛」の対立・矛盾
いままでに、「自由」について述べた中で「自由」の内部にある対立・矛盾に言及し、同様に、「愛」の説明の中で「愛」の内部にある対立・矛盾に言及した。本節ではさらに、「自由」と「愛」の間での対立・矛盾について述べよう。基本的には、「自由」が「自分(たち)の幸福・利益」を追求しようとするのに対して、「愛」は「みんなの幸福・利益」を追求しようとすることの、対立・矛盾である。
4.1 ある人の独自の判断と行動(「自由」)を、別の人の「愛」が止めようとする
最初の対立は、ある人の独自の判断と行動に対して、その周りの人(特に親や先生など)が危うい、誤っているなどとして、止めようとする場合である。周りの人が保護的・指導的立場にあり、経験豊かな場合に典型的に起きる。「あえてリスクを取り、行動することが、将来の成功の糧だ」というのが「自由」に基づく立場である。「失敗は目に見えている、失敗したときのダメージが大きいからやめよ」というのが「愛」に基づく立場である。どちらが適切かは、場合によって異なる。
4.2 「助け合い」「協力」を求める「愛」に、「自由」が協力を拒否する
対立の第二は、「愛」がその(「身内」の)メンバーに対して、(「みんなの幸福・利益」のために)「助け合い」や「協力」を求めた場合に、メンバーが「自分の利益に合わない」として拒否するときである。「自由」は「自分の幸福・利益」を最大限に求めるから、この対立はしばしば起こる。
4.3 「勝負」「戦い」での決着(「自由」)を、「愛」は「平和的に」避けたい
対立の第三は、「自由」が「競争」によって「勝ち負け」をつけようとする場合である。それは「自由」にとっては当然の方法である。一方「愛」は、無用な「競争」「勝負」「戦い」を避けて、何らかの方法で「調整」「協調」「調和」「平和」を実現しようとする。しかし、「愛」が具体的に提示し、競争・勝負に臨もうとする当事者たちを納得させることができる実際的な方法はそう多くない。「調停者」「裁定者」として当事者たちから信頼され、その「調停案」が当事者たちを納得させるものでなければならない。
4.4 「社会的勝者」が作る「社会ルール」に、「愛」が異議を申し立てる場合
対立の第四は、「社会的勝者」が自分たちに都合がよい新しい「社会ルール」を作り、支配者としてその体制を維持しようとする段階である。これは「自由」の立場での当然のやり方である。このとき「愛」は、その新しい「社会ルール」や支配の体制が、「みんなの幸福・利益」の観点から適切かどうかを問題にする。そして適切でないと判断すると、「みんなの幸福・利益」「博愛」の立場から反対の意思表示(新しい社会運動など)をすることになる。
4.5 「抑圧からの解放」の運動(「自由」)に、「愛」が反対する場合
対立の第五が起こり得るのは、「社会的敗者」が「抑圧からの解放」「現状打破」を掲げて、「革新」の運動を起こす場合である。このとき「愛」は、その運動が抑圧されていた人々を解放しようとしている点では同調する。しかしその運動が新たな(大きな)不幸を生じさせる恐れがあるときには、反対を表明するだろう。
4.6 「愛」が「身内」の団結を求めて、メンバーの「自由」を束縛する場合
対立の第六は、「外部」からの脅威や攻撃に対して対抗するために、「愛」がその「身内」の団結を求め、メンバーを束縛しようとする場合である。メンバーにとっては、その「考え」や「行動」を束縛され、「自由」を失うことになる。
4.7 「愛」の「身内意識」が、外部の人の考え・行動(「自由」)を排除する場合
対立の第七は、「愛」が認識している「身内」に対して、「外部の人」の処遇の問題である。「愛」の「身内意識」が強く、偏狭である場合には、「外部の人」ははじき出され、疎遠にされ、人間的な対立が起こるであろう。
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割
さてここで、「倫理」の理解に立ち戻って、その役割をさらに深く考えておこう。第1原理の「自由」と第2原理の「愛」との両方を「動機づけ」、また「自由 vs 愛」の主要矛盾を(解決するために)「調整する」のが「倫理」である、と考えている。その内容をさらに深く考察する。
5.1 「倫理」自身の理解が、人類文化の歴史の中で発展してきている
人間の内面(内奥)においては、「感情」と「欲・欲望」があるが、それは「悪の心」と「善の心」(「自己実現」などの人間的欲求を含む)の両方を生じ、その葛藤を持っている。この両面とその葛藤を認識したうえで、人間の根源的なあり方(あるべき姿)の指針を示すのが「倫理」である。「倫理」は「何が善で、何が悪であるか」を示し、「悪から善に向かわせる」指針である。
しかし、「何が善で、何が悪か」の中身は、時代により、社会によって異なる。人々はその善悪の考え方を後天的に社会から教えられて、基本的にはそれに従って(従わされて)きた。人類文化の歴史は、時代と社会で異なる多様な「倫理」を抱き込み、相互に影響しつつ進んでいる。それがある程度の方向性を持っていると考えられるのは、「内心で善悪を判別できる心の能力」としての「良心」を人類が先天的に持っているからであろう。この意味で、人類文化の歴史が、より望ましい「倫理」の理解へと進んでいるものと考えられる。
5.2 個人の心の中で「倫理」が適切に理解され、実践されることの重要性
個人個人の心の中で「倫理」が適切に理解され、それが実践されることが、人類文化の二つの主要原理「自由」と「愛」が本来の姿で実践され発展するために最も重要なことである。以下に、「自由」の中、「愛」の中、「自由」と「愛」の間にある対立・矛盾を解決するために、「倫理」がどのような役割を果たすかを考察しよう。
5.3 不十分な「倫理」(の理解)は、「自由」の精神を損なう
まず、不十分な「倫理」が、「自由」の精神を損なう例は、枚挙に暇がない。
すなわち、(「主体性」に反する)消極性、無気力、追従、他人依存、無責任、付和雷同、大衆迎合、など、(「独自性、新規性」に反する)先例踏襲、ありきたり、陳腐、二番煎じ、模倣、など、(「挑戦的」に反する)無難、萎縮、など。
また、「競争」に際して、不適切な「倫理」はいろいろな不正を働く。例えば、裏口入学、カンニング、試験問題漏洩、ドーピング、妨害、判定操作、ルール違反、買収、収賄、など。
「自分の利益の獲得」に際して、もっと大規模な不正もある。例えば、脅迫、買収、収賄、追い落とし、文書偽造、扇動、詐欺、強盗、殺人、など。
「社会的勝者」による「新しい社会ルール」作りにおいて、不適当なルール(制度)も(歴史的に見れば)いろいろある。例えば、奴隷制、君主制、身分制度、家父長制、制限選挙(普通選挙でないもの)、植民地制、など。
「現状打破」の運動においても不適当な「倫理」理解が現れることがある。例えば、運動する側の武装蜂起、テロ、など、それに抵抗する側の言論統制、弾圧、など。
5.4 「自由」の土台となる「倫理」:「基本的人権」と「本質的平等」の概念
「自由」が第1原理として尊重されるためには、人の内面において、「倫理」が正しく理解され、本来の人間的欲求(自己実現など)を追及する「自由」であり、人間の「悪の心」の欲求を追及する「自由」であってはならない。
これを保証するための具体的な指針は、「自由」の主張と競争の場に、(明文化された「倫理」というべき)「基本的人権」の順守を掲げることであろう。すなわち、すべての人々の「基本的人権」を守ることを「自由」の主張とその追求の大前提にすることである。
なお、これに関連して、旧来の「道徳」が身分社会を前提にして「服従・従順」を第一とする「倫理」であるのを脱却して、「人としての本質的な平等」を大前提とする「基本的人権」を主とした「倫理」観に進むべきである。さらに、「平等」概念にも明確化が必要であり、「画一的平等」とは異なる「本質的平等」の概念と具体的な扱い方の理解を普及させることが大事である。
5.5 不十分な「倫理」は、「愛」の精神を損なう
同様に、不十分な「倫理」は、「愛」の精神を損なう。
すなわち、(「愛情」に反して)無関心、嫌悪、冷酷、虐待、など、(「助ける」に反して)無視する、放置する、など、(「守る」に反して)、見捨てる、など。
また、「愛」がグループ内の人々の意思を「調整」しようとするのに対して、不十分な「倫理」の反応には、固執、拒否、非協力、利己主義、無理解、無関心、冷淡、などがあるだろう。
5.6 「愛」の土台となる「倫理」:心の中の「愛」と「広い心」
第2原理の「愛」がその本来的な役割を果たすためには、それに関わる人々が「倫理」を適切に身につけている必要がある。「愛し、助け、守る」ことは、本来人間の根源的な性質(感情、欲求)であり、すべての人がその心の優しさとして、持っているものと期待される。それがあれば、グループ内で(そしてすべての人々と)助け合い、協力し、調整することができる。さらに、利己的な「自由」の主張を避け、「自由」と「愛」との対立の大きな要因を減らすことができる。
「愛」は、その対象を広げる、普遍化することを目指す。その障害になるのは、「愛」自身のもつ「身内」意識である。家族だけでなく、地域の人々、同国の人、世界中の人種も言葉も違う人々に広がっていく必要がある。(そうでないと、「愛国心」同士が戦争を起こす。)このためには、「人間としての本質的平等」の「倫理」を持ち、また世界の状況を知り、世界の人々とのコミュニケーションに努めることが大事である。
5.7 経済的「格差」の問題と「富の再配分」の問題の認識
もう一つ言及するべきは、人間の欲望、特に金銭欲に際限がないことである。現代世界では、金銭が「社会的勝者」を決める最大の要素であり、「富める者」こそ「社会的勝者」であり、彼らに都合がよい社会制度になっている。それが資本主義経済であり、それを中核とした資本主義社会である。これが日本でも世界でも大きな格差を生み、沢山の問題を引き起こしている。この点を変革して、「富の再配分」をもっと明確に組み込んだ社会制度が望まれる。これは「自由」のあり方の問題であり、「愛」の問題、「倫理」の問題でもある。
6.まとめ
第0原理の「倫理」は、まず個人の内面に関わり、「欲」や「悪の心」との葛藤で、「善の心」に導くことを目標とする。また、すべての人が守るべきものとして、(「(人としての基本的な)平等」を中核とする)「基本的人権」の概念が明確になった。
第1原理の「自由」は、自分の判断で行動し、競争に勝つことを目指す。それが文化的、社会的な革新をもたらせる。一方、競争の社会的勝者が自分たちに都合の良い社会ルールを作り、支配者として保守の体制を作る。競争に際し、また社会ルールの作成に際して、「基本的人権」の導入が大事である。
第2原理の「愛」は、人を愛し、助け、守ることである。その優しさの心は、本来、人の「倫理」の一部である。助け合いは社会の革新を目指す。ただ「愛」には「身内を守る」ために外部と対抗する性質があり、偏狭になる危険もある。「愛」の普遍化と、「基本的人権」の概念の適用が大事である。
個人のレベルでの「自由・愛・倫理」のあり方を正しく認識し、世界で共有していくことが、人類社会、人類文化を発展させる基礎として、大変重要である。
本研究は、TRIZ/CrePSの方法論、特にそのシステム思考と矛盾考察の考え方を用いて、輻輳した社会問題の根底に横たわる、人類文化の思想的な根本問題を考察し、以上に述べた基本仮説を導いた。今後、個人のレベルより一階層上の、グループや組織のレベルでの「自由・愛・倫理」の構造の考察に進みたい。
参考文献
[1] 創造的な問題解決のための一般的な方法論CrePS: TRIZを越えて:なに?なぜ?いかに?、中川徹、TRIZCON 2016、2016年3月3-5日、米国; 和訳: 『TRIZホームページ』(THPJ), 2016. 6.20 
[2] 社会の貧困の問題にTRIZ/CrePSでアプローチする:人々の議論の根底に、人類文化の主要矛盾「自由vs. 愛」を見出した、中川徹、日本TRIZシンポジウム2016 発表、2016年9月1日。THPJ、2016.9.9 
『TRIZホームページ』、中川徹編集、URL: http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/ 
 発表スライド (学会発表版) PDF
発表スライド (学会発表版) PDF  (27枚、494 KB) (創造学会研究大会2017 2017. 9. 8 作成)
(27枚、494 KB) (創造学会研究大会2017 2017. 9. 8 作成)
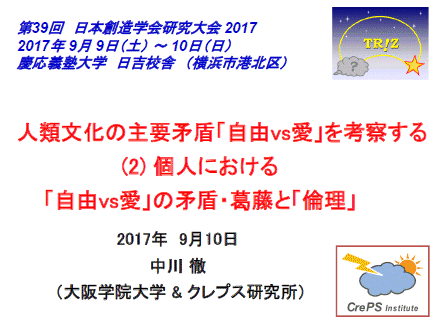
(0) はじめに (趣旨とアウトライン)
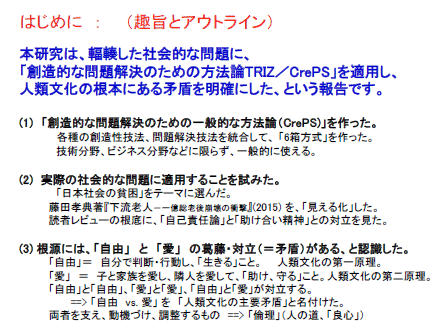
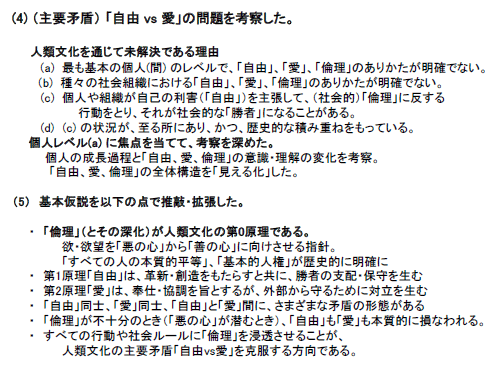
(1) 前報 (TRIZシンポ2016)までの説明
創造的な問題解決の方法論 TRIZ/CrePS
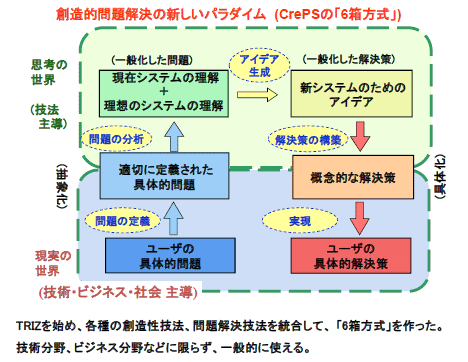
社会的問題に適用する: 高齢者の貧困問題、その「見える化」、読者書評の分析
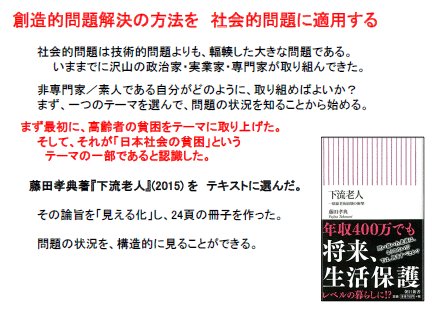
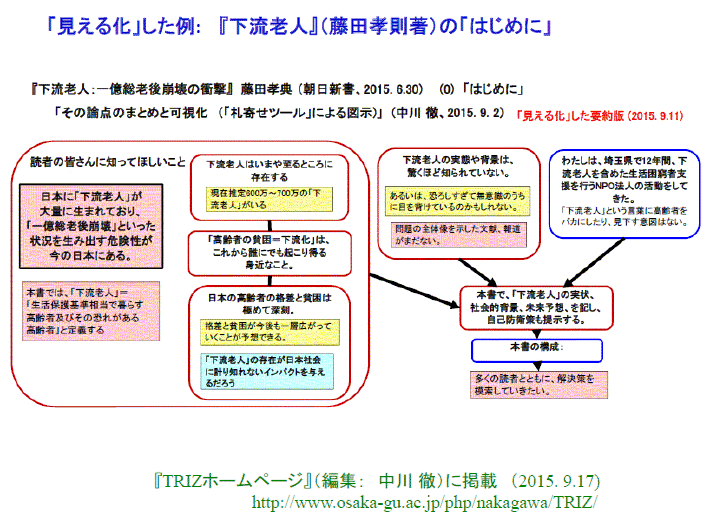
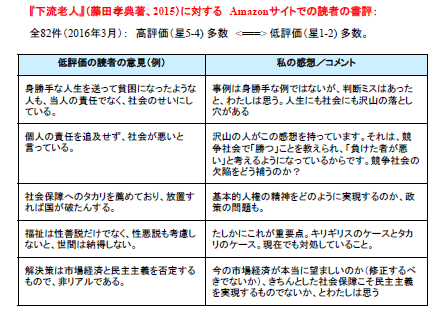
問題の本質を捉える
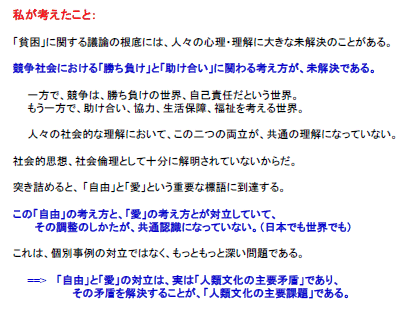
(3) 前報で得た基本仮説: 「自由」 vs. 「愛」が人類文化を貫く主要矛盾
基本仮説: 「自由」 vs. 「愛」が人類文化を貫く主要矛盾
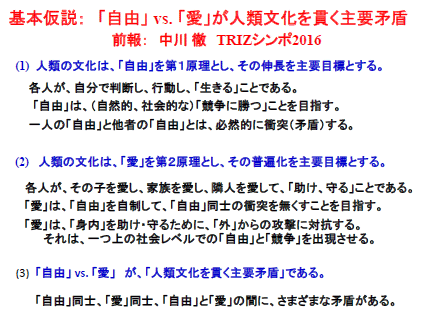
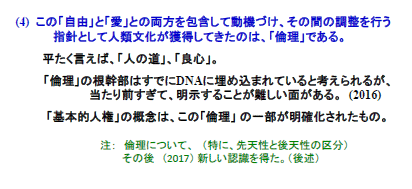
「自由」 vs. 「愛」 の図式表現
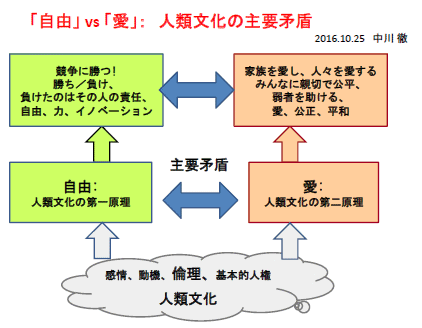
主要矛盾の解決を困難にしている要因
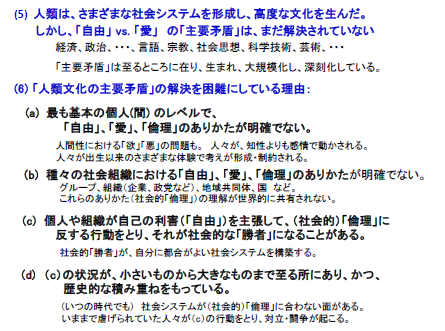
(4) 本報での考察のやり方
個人の成長段階に応じて、 「自由・愛・倫理」の関係を考える。
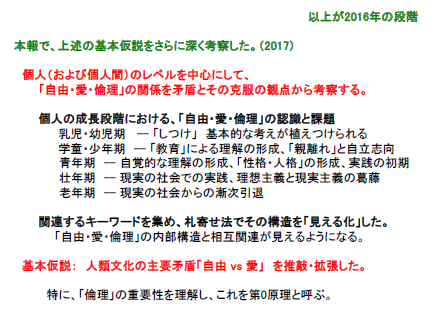
札寄せ法で 自由・愛・倫理の関係を「見える化」する: 本報で得た図式(詳細版)
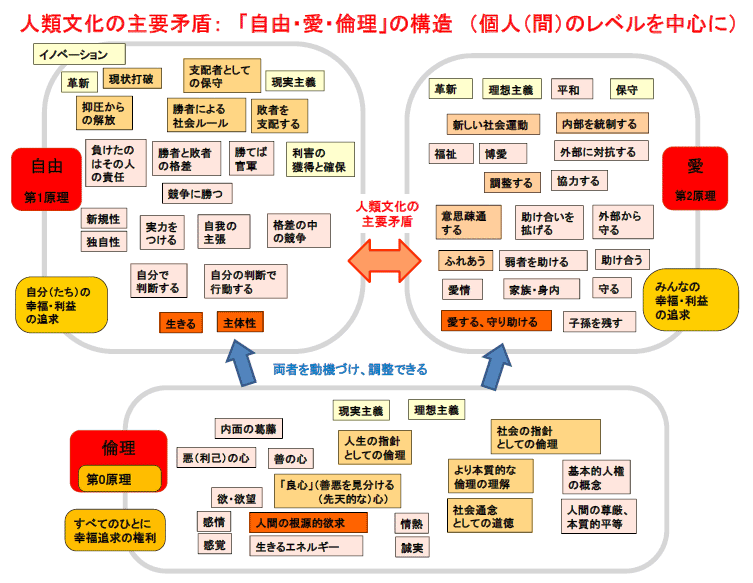
(5) 「自由 vs 愛」の矛盾・葛藤と「倫理」 −− 基本仮説とその考察
1. 人類文化の第0原理: 「倫理」
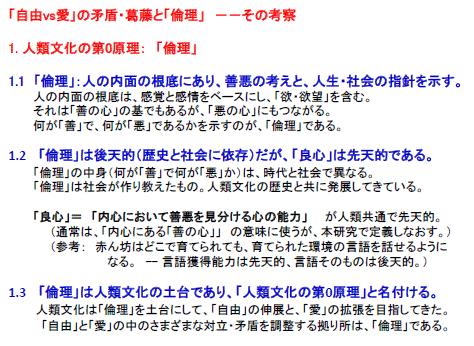
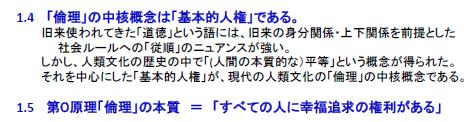
2. 人類文化の第1原理: 「自由」
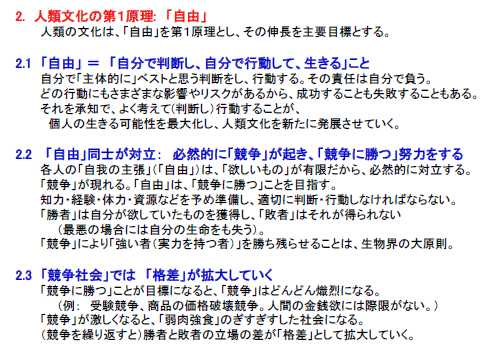
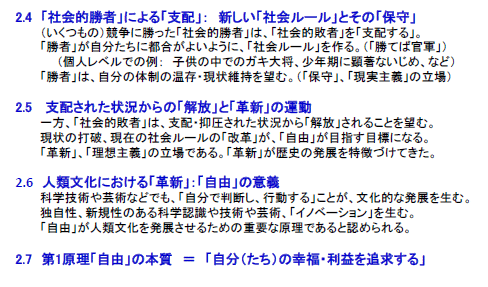
3. 人類文化の第2原理: 「愛」
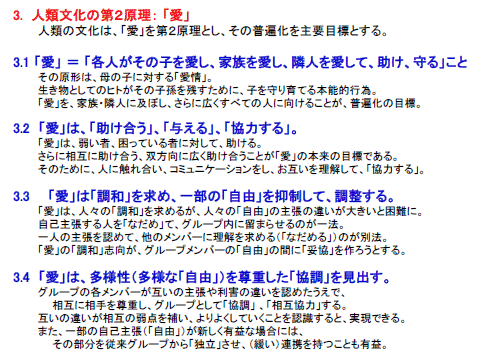
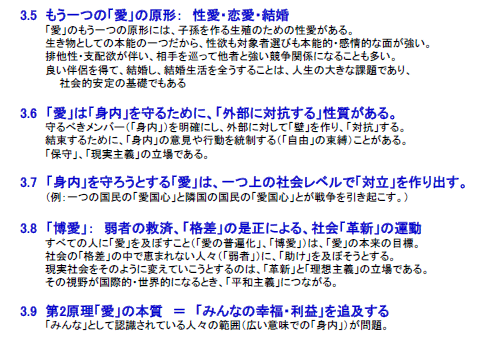
4. 「自由」と「愛」の対立・矛盾
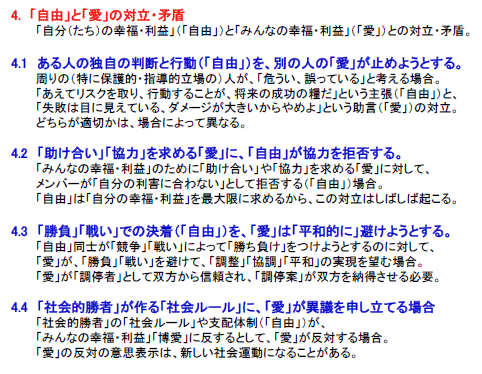
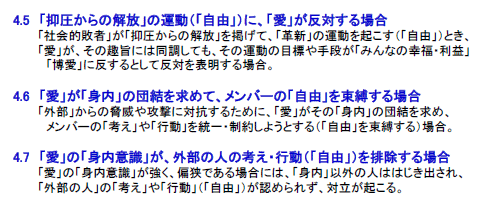
5. 「自由」と「愛」に対する「倫理」の役割
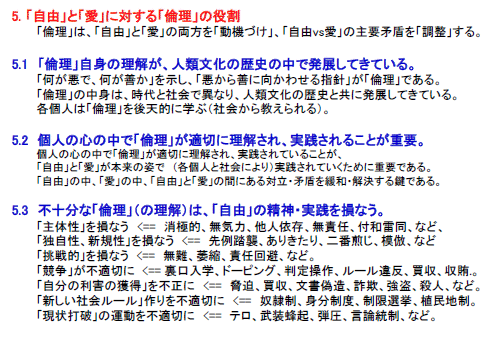
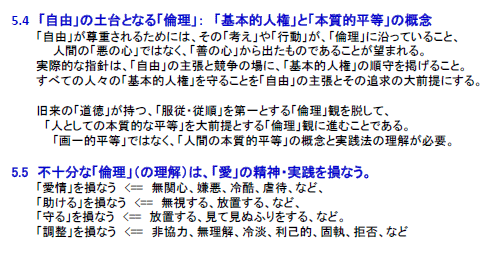
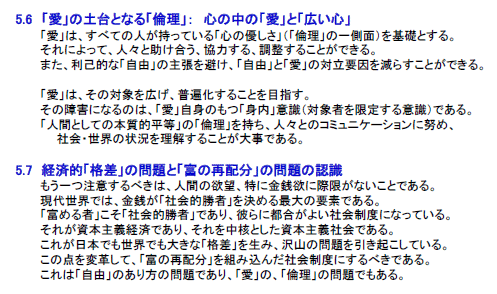
(6) まとめ
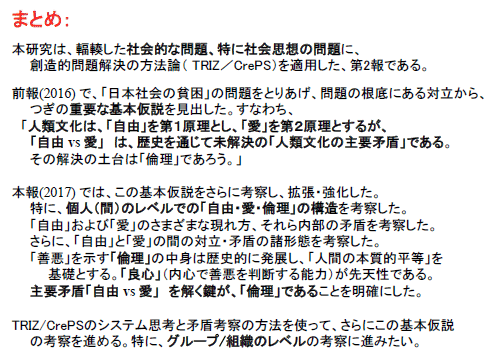
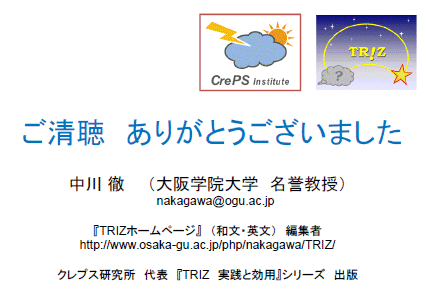
最終更新日: 2018. 8.14 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp