読者の声 (2016年 8月〜9月)
高山直彦、渋谷 政昭; 山本 毅雄; 諏訪 頼一 (司法書士);中川 徹
掲載: 2016. 9.29
読者の声 (2016年 8月〜9月) |
|
|
|
| 責任編集: 中川 徹(大阪学院大学) | |
掲載: 2016. 9.29 |
Press the button for going back to the English top page.
![]() 編集ノート (中川 徹、2016年 9月27日)
編集ノート (中川 徹、2016年 9月27日)
読者の皆様から折に触れていただいた感想・ご意見を、まとめて掲載させていただいているページです。
簡単な表形式で紹介させていただきます。
| 2016. 7.31 | --------------------- | 『TRIZホームページ』更新 ------------------ |
| 2016. 8. 1 | 高山 直彦 | 「創造的な研究の方法とは?」について − James Young と Darrell Mann |
| 2016. 8.9; 2016. 9.27; 9.28 |
渋谷 政昭; 中川 徹 | 統計科学の発展(コンピュータを使った抽象化と具体化) |
| 2016. 8.28 | --------------------- | 『TRIZホームページ』更新 ------------------ |
| 2016. 8.22 | 山本 毅雄; 中川 徹 | 財政破綻の問題 |
| 2016. 9. 9 | --------------------- | 『TRIZホームページ』更新 ------------------ |
| 2016.9.12 | 諏訪 頼一; 中川 徹 |
下流老人について思うこと (厚生年金不加入の問題、ほか) |
| 本ページの先頭 | ホームページ更新(2016. 7.31) | 渋谷 政昭 | ホームページ更新(2016. 8.28) | 山本 毅雄 | 諏訪 頼一 |
![]()
『TRIZホームページ』更新(2016. 7.31 付け)
「読者の声(6月〜7月)」(読者11人+中川)
。
フォーラム: 「学術界における「創造的な研究の方法」とは? 「創造的な問題解決の一般的方法論(CrePS)」は寄与しうるのか?」(問題提起: 某先生、応答: 中川 徹)。
「 救命延命医療から緩和医療へ」(島田宗洋)。
「札寄せ用具の開発の意図、操作法、使い方、使用実践例、図的思考の有効性(片平 彰裕、中川 徹);第1部: 札寄せ用具の開発の意図、操作法、使い方(片平 彰裕); 第2部: 「札寄せ用具」の使用実践例: 片平が行っている札寄せ法 (片平 彰裕)
。
高山 直彦 さん ==> 中川 徹 2016. 8. 1
いつも、興味深い記事、ありがとうございます。
問題提起:学術界における「創造的な研究の方法」とは?
について、一言言わせてください。 (私は、最先端ではありませんが、指導している立場として言わせてください)
創造的な発想を研究開発のみならずクレーム対応やCDにいたるまで利用すべきものと 考え、如何に発想すれば良いかを直接ではありませんが、間接的に説明している立場です。
下図 は、[マインドマップの形式で] James Youngの本をまとめたものです。(詳細はPDF)
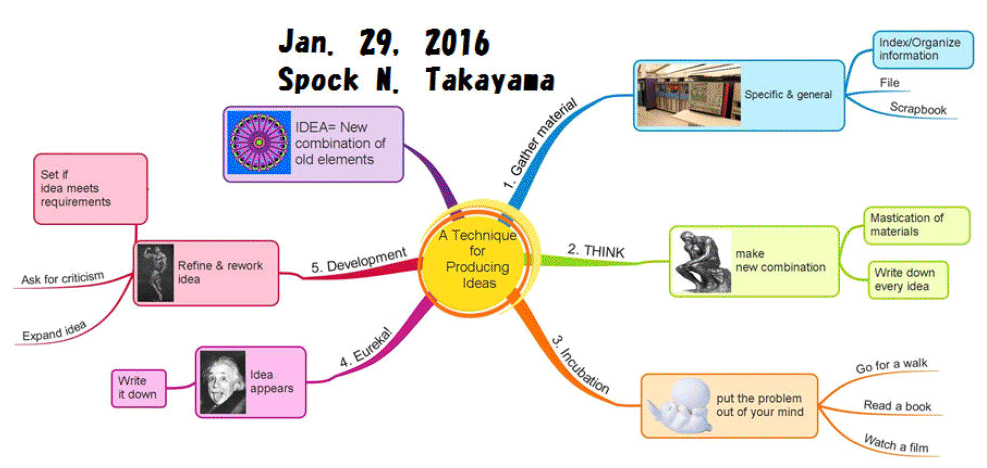
また、下図は、 中川先生訳を参考にDarrell Mannの本をまとめたものです。(詳細はPDF )
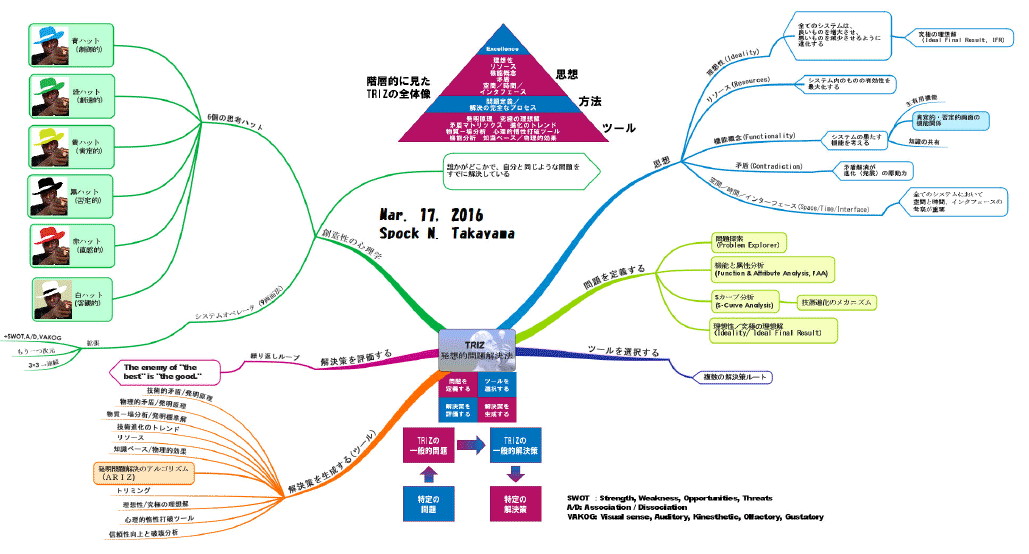
この両者を比較していった時、共通点とも思えるものがあるのではないでしょうか。
James Young Darrell Mann 1. Gather material 問題を定義する 2. Think ツールを選択する、ツールによる試行錯誤(守) 3. Incubation 解決策を生成する ツールによる試行錯誤(破) 4. Eureka! 解決策を生成する ツール参考にに解決策を得る(離) 5. Development 解決策を評価する 発想の流れは、このJames Youngの話に集約され、「Eureka!」の部分で、皆悩んでいるのではと思います。 この「発想の瞬間」をどのようにもたらすかがポイントではないでしょうか。
このように考えると、「発想の瞬間」をTRIZはもたらさないようにも思います。 (この点が解明されて、人工知能で行えるようになると、我々の大半は仕事を失うかもしれません)
渋谷 政昭 さん ==> 中川 徹 2016. 8. 9
すっかりご無沙汰しております。TRIZ, CrePS の資料をいただきながら、お礼も書かず失礼したままです。
最近は体力知力が衰え、年賀状も失礼するようになりました。新しい情報を受容する能力がなく、過去の紙くずを処理することが、日常の仕事です。
ただ一言。私の学生以来の関心事である統計科学は CrePS の抽象化具体化を、実データについて、簡単なモデルから出発しかなり複雑なまで、成功させていると考えます。コンピュータの進歩に支えられ、たとえばゲノム解析、金融工学、脳科学、などのデータ解析が行われています。いかなる概念も数学オブジェクトとして抽象化可能であり、それを実証するために必要なデータの量も確認できます。逆にデータが得られないときの意思決定の限界も明解になります。
我々が出会った機会がコンピュータによる数値解析でしたが、その進歩の影響は想像以上です。
中川 徹 ==> 渋谷 政昭 さん 2016. 9.27
8月にメールをいただいており、ありがとうございます。また、いままで返事を差し上げておりませず、大変失礼しました。
「ただ一言」として書いてくださっている観点は、大事なことと思います。
ただ、私にとっては、少し衝撃的でもありました。私は、統計的なデータ解析を学びましたし、ゲノム解析も、人工知能も、ニューラルネットも、ビッグデータ解析も、特許データの意味解析なども、学んできました。それらのコンピュータ解析ができることの凄さは知ってきています。
ただ、それらによってコンピュータが出してくる結果を、人間が理解して作り上げていくモデルと同等のものと 考えることに、私は抵抗を感じています。以前に、東大の「知の構造化センター」主催のシンポジウムで同センターの主要活動としてビッグデータ解析が報告されたときに、私は、「ビッグデータ解析で本当に知の構造化ができるのだろうか?もっと人間に分かる論理での、知の構造化とその(構造化したモデルの)表現が必要なのではないだろうか?」 と思いました。
最近の天気予報で示される画像データは二三年前に比べても驚くばかりの詳細さと分かりやすさです。衛星データや気象庁のスパコンでの膨大で高速なシミュレーションの結果であり、そのバックに素晴らしい科学技術の進歩・蓄積があることは、一般人にもわかります。それでも、気象予報士の(ある意味で初歩的な)解説があるから、一般の人に今後の天気の移り変わりが分かり、台風への備えができる。解説されているのは、人間に分かる形になっている簡単なモデルであると思います。
このような抵抗感を持つのは、私が直接にコンピュータを使った方法に(かなり長いこと)関わって来なかったために、時代に遅れているのでしょう。 「コンピュータを使った統計科学の方法が、CrePSでいう抽象化と具体化をずいぶんの程度に実現している」という観点は、今後心に留めていきたいと思います。
またその一方で、コンピュータを使う方法でできていないことで、「知の構造化」あるいは「モデルづくり」「本質の理解」といったことの大事なことがあるように思います。
遅々とした小さな活動ですが、CrePS(創造的な問題解決の一般的方法論)の考え方を発展・普及させていきたいと思っています。
渋谷 政昭 さん ==> 中川 徹 2016.9.28
詳しいお返事ありがとうございました。 ちょうど Windows 10 デスク・トップ への移行が一段落したところなので、今回はすぐお返事できます。
>> 『TRIZホームページ』の「読者の声」のページに掲載 << はどうぞご自由に。お返事について、私の考えていることとの「食い違い」について、また一言だけ。
人間が試行錯誤を繰り返して作りあげたモデルと、コンピュータ/AI が作るモデルの 有効性は、状況によると思います。 工業製品の大量生産工程のモデルでは前者が有効でしょうが、音声認識・手書き文字 認識では、諸文法理論に基づくものよりは、実データを多量に収集して、頻度だけで 選択するものが有効のようです。
もっとも、「科学をコンピュータは理解するが、プログラミングは人間のアートであ る」という人もいます。人間の理解能力には限界があり、解説者の説明で納得・誤解・曲解して、そのために また新しい理解・理論が生まれることになります。複雑な金融市場の動きを、日経指 数と対ドル交換価格だけで説明・理解するようなものでしょう。
![]()
『TRIZホームページ』更新(2016. 8.28 付け)
「「日本社会の貧困」を可視化しながら考える [E] 経済と財政 [1] 吉川洋教授講演「財政再建と日本経済」の可視化とまとめ」 (中川 徹)
中川 徹 ==> 山本 毅雄 さん 2016. 8.22
先日は、『下流老人』の本の「見える化」資料に関連して、財政破綻の問題が一番大きいとの、貴重なコメントをいただきありがとうございました。ずっと気にかかっておりました。
最近、学士会会報918号に吉川洋先生(当時、東大教授)の夕食会講演要旨「財政再建と日本経済」を見つけました。 経済の専門でない私にも、分かりやすく、説得力のある文章で、素晴らしいと思いました。
そこで、「見える化」作業をいたしました。第1稿(詳細版) 5頁もの、第2稿(簡略配布版) 2頁もの。 ここに添付させていただきます。ご感想を再度いただけないでしょうか?
山本 毅雄 さん ==> 中川 徹 2016. 8.22
頂いた資料、簡略版
は拝読、なるほどと教えられる点がいくつかありました。詳細版はまだ よく見てないので、読んでからコメントしたいと思います。
財政破綻問題について補足:
・ 石破茂氏が自由の身になって、わりといいこと言ってますね。彼は地方創生バラマキ一本 かと思いきや存外、現政府の財政・金融に危機感を持っているようです。本当はもっともっ と多くの人がそうでなくては困るのですが。
・ 藤巻健史氏は、維新になっちゃって時に頭に来ることも言いますが、昔から財政破綻にこ だわっていて面白い人です。でも結局、彼自身は日本が破綻しても自分は全く困らない上流 階級だからなあ。 https://www.fujimaki-japan.com/takeshi/2031z
・ 第二次大戦後の超インフレは、みな「戦争に負けたんだから仕方がない」と思っちゃったみたいですが、そうではなく、既に戦争を始める前に決っていたのではないかと、以前から 思っていました。最近ちょっと調べてみたところ、鎮目雅人という経済学者が、1932年ごろ の高橋財政期に、既に日本の財政運営が維持可能でなくなっていた、と言っています(鎮目 「世界恐慌と経済政策」(日本経済新聞出版)、 https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2009/rev09j01.htm/)
・ もちろん、終戦前後に貨幣を大増刷して戦争物資の支払いをし、軍需産業を助けたことが、 直接のきっかけにはなったようですが。まあ日本に限らず、英国もヨーロッパ諸国も第2次大戦後の経済は厳しかったみたいですが、あの時は米国が日本を含む西側諸国を支えてくれたので、まだなんとかなったのではないでしょうか。それでも、「塗炭の苦しみ」という言葉がぴったりの人々がほんとうに多かった。今度もし日本が破綻したら、長年にわたる自業自得の政策の結果なので、他の国々がどれだけ助けてくれるのか、また助ける余裕があるのか、が問題でしょう。
・ 私など、子供のころ引揚で生活に苦労したつもりでおりましたが、今思えば両親揃ってい て、狭いながらも田畑もあり、腹をへらして倒れそうだったのもほんの一二年と、いろいろ恵まれた戦後だったと思います。もっと長いこと(甚だしきは子・孫代々)もっとひどく苦労した人たちが、身近にもいくらもおります。
![]()
『TRIZホームページ』更新(2016. 9. 9付け)
「社会の貧困の問題にTRIZ/CrePSでアプローチする: 人々の議論の根底に、人類文化の主要矛盾「自由vs. 愛」を見出した」 (中川 徹、TRIZシンポジウム2016)
。
「新版矛盾マトリックスMatrix2010のA2サイズシート2枚組」の単品廉価販売をStores.jpサイトで行います (クレプス研究所 中川 徹)
諏訪 頼一 さん ==> 中川 徹 2016. 9.12
ご無沙汰しています。6月には下流老人に関する中川さんのご研究をお送り頂き、有り難うございました。 私も、その後この朝日新書の「下流老人」を読み、下流老人問題は、なにやら他人事とは思えず、中川さんの論考にも、なんとか私なりのコメントを作りたいと思っていたところなのですが、 なにしろ中川さんの「自由」と「愛」の論考は、私などには難解でございました。
そこで私なりの下流老人問題を述べるに当たり、身近な具体例のなかで、なんとか私の愚見を申し述べるのがいいと思い、中川さんのお手紙への返事と言う形で、別紙添付のものをつくり上げ、メールさせていただく次第です。
中川 徹 ==> 諏訪 頼一 さん 2016. 9.12
丁寧なメールをいただき、ありがとうございます。
『下流老人』の本のA4 1頁の要約
(諏訪頼一)は分かりやすいですね。
また、4頁にわたって書いていただきました、感想や提案などもよく分かります。具体的な事例をもとに、いくつもの論点から考察・提案いただいていて、私にも参考になりますし、その他の読者のかたにも参考になることと思います。
私自身は実社会の具体的な事例に触れる機会が多く ありませんので、具体例で考えたり、具体例を話したりすることが不得手です。 諏訪さんは実務の中で出会われることもあるでしょうから、それだけ分かりやすく説得力がありますね。
お願いですが、諏訪さんの今回書かれたものを、私の 『TRIZホームページ』にぜひ掲載させていただけないでしょうか?
===> 諏訪さんの快諾を得て、独立ページにしました。
「「下流老人」について思うこと」(諏訪頼一)(2016. 9.29)
| 本ページの先頭 | ホームページ更新(2016. 7.31) | 渋谷 政昭 | ホームページ更新(2016. 8.28) | 山本 毅雄 | 諏訪 頼一 |
総合目次  |
(A) Editorial | (B) 参考文献・関連文献 | リンク集 | ニュース・活動 | ソ フトツール | (C) 論文・技術報告・解説 | 教材・講義ノート | (D) フォーラム | Generla Index |
| ホー ムページ |
新着情報 |
子ども・中高生ページ | 学生・社会人 ページ |
技術者入門 ページ |
実践者 ページ |
サイト内検索 | Home Page |
最終更新日 : 2016. 9.29 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp