論文集解題、論文 9編
| 高原利生論文集(第3集): 『差異解消の理論 (3) 弁証法論理と生き方』 (2013-2015) | |
|
|
| 高原利生 、2015年10月18日 | |
| 掲載:2015.11.13 著者の許可を得て掲載。無断転載禁止。 |
Press thebutton for going back to the English top page.
編集ノート (中川徹、2015年11月 9日)
このページは、高原利生さんが 2013年~2015年の3年間に発表されたTRIZ関連の論文9編をすべてまとめて、高原さん自身による解題を掲載して、各論文 (HTMLページ/PDF版) へのリンクを張ったものです。これは、第1集(2003-2007年、論文14編)、第2集(2008-2012年、論文13編)に引き続く、高原利生論文集第3集です。
私は2007年秋に、第3回TRIZシンポジウムの高原さんの論文を読んで、その内容の深さと論理の明快さに驚きました。そこで、高原さんが独自に作り、発表してこられた5年間の論文をまとめて、 高原利生論文集(第1集): 『差異解消の理論』 (2003-2007)

として収録させていただきました。
「差異解消」というのは高原さんの造語で、「ありたいこと、したいこと」と「現実」との違いを「差異 (Difference)」と呼び (「矛盾」よりも広い概念です)、この違いを認識して解消を目指すことが人間の活動の根幹にあり、それが目標設定、問題認識、設計、問題解決などさまざまな段階と活動形式を取ると考えています。
それを一般的・理論的に捉えるために、オブジェクトとその関係という基礎概念(とその表現)の確立に高原さんが格闘しています。「オブジェクト」は、通常の「もの」だけでなく、「認識できるものすべて」に拡張され、プロセスも、事実も、思考も含みます。また、「関係」は、静的な属性、二つの「もの」の関係・作用・機能などはもちろん、時間的な変化(反応なども)を含み、一般化された「オブジェクト」同士の一般化された「関係」をいう概念として「運動」という言葉を導入しています。また、一つの「オブジェクト」が何を指すのかその範囲(どれまで、どこまで、いつまで)を明確に意識することが大事であり、その範囲のことを「粒度」と呼んでいます。また、論理構成には、本質を深く考え、漏れなく網羅したうえでの考察(「根源的網羅思考」)が大事であるとしています。
高原論文集第2集:『差異解消の理論 (続)』 (2008-2012)

を、作ったのは、2013年です。この前年の2月に髙原さんは心臓弁膜症の手術をされ、ペースメーカーを入れられました。その手術の前日にいただいた4年間の発表論文と、手術後1年間に著作された論文(計13編)をまとめたものです。
高原さんは論考をさらに進めて、「差異解消」、「矛盾解決」などのいろいろなケースとその方法を整理・記述していっています。その中で、「差異解消」が、これまでに意識していた「変化」「変更」(狭義の「差異解消」)だけでなく、「両立」(例えば、対立と調和という二者の両立、あるいはその二者の矛盾状態)を含むことに気づいています。また、「差異解消」が、人間の文化の発展をもたらせた原動力であり、それが「技術」だけでなく、「制度」(人間関係、人間間の共有意識、文化、社会など全般)を作り上げてきたことに注目しています。その原動力を生む個人でのあり方を考え、「TRIZという生き方」を考察・提案しています。さらに、「差異解消」の基本論理として、弁証法の見直しを進めているのです。
今年(2015年)の1月に私は3年余ぶりに高原さんに会うことができ、その後の学会発表論文4編と原稿1編を受け取りました。そのうちの代表的なものとして、FIT2013の論文
を4月に掲載しました。高原さんの新しい原稿は緻密で膨大なもので、何度かやりとりをして、8月には三部作(合計 55頁)の「研究ノート」の形で最終稿を受け取りました。その三部作は、高原さんの理論の全体を丁寧に記述したものです。「分かっていることよりも分かっていないことの方が多い。何が分かっていないかを書くことが大事。」という考えで、あえて「研究ノート」という形式をとったものです。本ホームページは、学術的な形式よりも、実際の知識の開発と普及を迅速に行うことを趣旨にしておりますから、高原さんの理論の発展を記録しフォローするために、これを喜んで採用しました。この三部作を頂点にしているのが、今回の論文集第3集です。
テーマは、(広義の)「差異解消」のための基礎概念から、その方法の体系的な考察、そしてその応用という広範囲にわたっています。その考察の中心は、高原の「根源的網羅思考」をベースにした、「差異解消」の方法であり、その思考法を突き詰めていく中で、従来よりも拡張した「弁証法論理」を提唱しています。また、「差異解消」の原動力は、個人にあると考え、個人の中の世界観(価値観)、態度、認識のしかた、などを論じており、それらを人の「生き方」として考察しているのです。技術と制度の考え方、差異解消の方法の詳細な論理、そして人間の生き方、などのすべてが一つの枠組みの中で論じられている、驚くばかりの構想を持った新しく大きな「思想」です。
なお、その中で、中川の「TRIZのエッセンス(英語による50語の表現)」と「6箱方式」について、評価し採り入れてもらっているのは、嬉しいことです。(きっと近い将来に、「USITオペレータ体系」も高原理論の中の重要な要素になることと期待しています。)
全体的な考え方の流れと構成は、高原利生さん自身による「論文解題」、論文一覧表からリンクされた各論文(特に最新の三部作)の紹介部や目次をご覧ください。三部作は実に丁寧に体系的に高原さんの現在の理解を記述してありますが、読者の皆さんがそのような(論理)体系の用語を受容し、内容を理解するには、いままでのいくつかの高原論文を読み解いてみることが必要でしょう。それをするに値する重要な思想が構築されつつあると、私は確信しています。
本ページはつぎのように構成しています。
編集ノート (中川 徹) と 高原論文の一覧表 (リンクつき) [本『TRIZホームページ』での掲載記事へのリンクも]
高原利生: 「2013年~2015年の論文解題」 (HTMLページ、リンクつき)
高原利生論文(2013~2015年)の全論文(9編)のPDF版、およびそのうちの重要5論文のHTMLページ(各別ページ)へのリンク。
高原利生 論文集第3集 論文一覧 (2013年~2015年) (発表順) (すべて単著)
著者による論文集解題(3)
高原利生論文集(第3集):
『差異解消の理論 (3) 弁証法論理と生き方』 (2013-2015)
2013年-2015年の論文解題
高原利生 (2015年10月18日)
高原の2013年から2015年までの発表論文の位置づけと個々の論文の解題を以下に示す。
高原の2003年から2007年の論文集 (第1集
)、2008年から2012年の論文集 (第2集
) に続き、今回もこのような論文集の形で、『TRIZホームページ』に公開する機会を作っていただいた大阪学院大学中川徹名誉教授に感謝申し上げる。
1. 論文の位置づけ
2003年から2007年までの検討内容は、基本概念(オブジェクト,それを組み合わせたオブジェクト世界,オブジェクト変更、オブジェクトの属性,粒度,機能)を明らかにし、差異解消の方法、表示方法を追求したことであった。粒度とは、最初は、単に、オブジェクトの空間的時間的範囲としていたが、後に属性を加えた。
2008年から2012年までの検討内容は、(広義の)差異解消の理論になっている。(広義の)差異解消が(狭義の)差異解消(通常の意味の「変更」「変化」)と両立であることは大きな発見であった。
自然の運動、人間の行動、思考の全体は、内容的には、(広義の)差異解消である。これをもたらすのは、運動である。ここでの運動は、従来、アルトシュラーによって矛盾として扱われていた。アルトシュラーの矛盾は、マルクス、エンゲルスの矛盾の拡張になっている。全ての運動を、動的な構造の面から見たのが矛盾であった。
粒度が定まると、矛盾は定まる。粒度を管理するのが、根源的網羅思考である。
2013年からは、矛盾、根源的網羅思考を構成要素とする弁証法論理、それが「生き方」と「生きる」ことを実現すること、それが最小概念で実現されること、その「生き方」以外へも適用できることを検討している。
次図で、上右が2003- 2007年の主テーマ、上の左半分が2008- 2012年の主テーマと論文番号である。
下右が2013年以降の主テーマである。
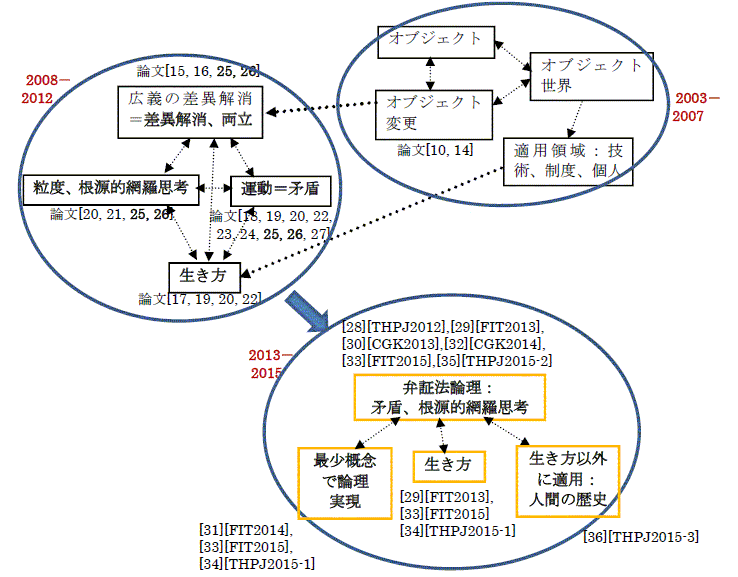
最初にお断りしておかないといけない。この「解題」は、全て、書き終えてかなりの時間を経て、改めて自分のしたことを見直し、それぞれが全体の中でどういう位置にあったのかを振り返って書いている。自分で、したことは、こうだったのかと思い直す作業であった。これは、論文集1も 論文集2も同じである。 最初からこう分かっていればもっといいものになったかもしれない。有意義な作業であった。 こういう作業をする機会を与えていただいたことにも、中川徹先生に感謝申し上げる。
発表は,情報科学技術フォーラム(FIT)という情報関係二学会共催のフォーラム,電気・情報関連学会の中国支部連合大会である。
中川徹先生のTRIZホームページには、ノートという形で公表をさせていただいている。[34] [THPJ2015-1] “粒度、矛盾、網羅による弁証法論理ノート: ノート2015-1” 等でも書いているが、書くものは全て未完のノ-トであるのが良いと考えており、学会発表の形式にとらわれないTRIZホームページでのノートという形式が、理想の発表形式であると考えている。
論文名の表記を、[2003年以来の発表順の通し番号] [発表の場の略称 発表年] 著者名, “論文名”, 発表の場, 発表年. の順に行う。
発表の場の略称は、
FIT:情報科学技術フォーラム Forum on Information Technology(情報処理学会と電子情報通信学会の情報処理に関係するソサイエティが共催する年に一度のフォーラム。毎年、三日間、数十の会場に分かれて1000件ほどの発表がある。たまたま2013年は鳥取大学、2015年は愛媛大学で開かれ、岡山に近かった。)
CGK:電気・情報関連学会中国支部連合大会(電気学会、照明学会、電子情報通信学会、情報処理学会などの中国支部が、毎年、合同で行う発表会)
THPJ:中川徹先生の『TRIZホームページ』
である。
2. 解題
情報科学技術フォーラム FITで発表
[29] [FIT2013]
高原, “世界構造の中の方法と粒度についてのノート”, FIT2013, 2013.
(『TRIZホームページ』 掲載: 2015. 4.12)
高原_FIT2013D-001_2013 和文論文 8ページ

高原_FIT2013S_2013 和文スライド 11ページ地球との共存という大きな世界の課題解決から発明,発見や人の日常生活に至る様々な目的を達成したい。
その目的は、人間の生きて行く行動で実現される。人間の「態度」と「方法」→「認識と行動」→「世界」というモデルがある。「生きる」ことは、このうち、「態度」と「方法」という「生き方」および「認識と行動」という実際の「生きる」行為に分けられる。態度と方法の一般的構造を明らかにした。
認識と行動を規定する理想の態度と方法も、態度と方法を規定するものも、ともに矛盾を単位とする弁証法と、粒度を管理する根源的網羅思考の相互作用であることを、初めて示した。
本稿を書いている間、論理が自動的に動いて文章ができていき、思いもかけぬ結論が作られる体験を何度かした。そのことを本文にも書いた。
これらが、今後の展開につながって行く。
さらに、宇宙論理学その他の展開も必要なことに気付いた考察であった。[31] [FIT2014]
高原, “適正な粒度の矛盾による仮説設定についてのノート”, FIT2014, 2014.高原_FIT2014D-008_20140630 和文論文2ページ
弁証法論理は、形式論理と異なり、変化性と多様な関係を扱う。その利用には、粒度確定が必要だが、それは網羅と依存関係にあるため、粒度と網羅を管理する根源的網羅思考が必要となる。
まず粒度がある。粒度は、扱うものの空間的時間的範囲、属性の範囲である。粒度の定まった粒も、慣例に従い単に粒度という。粒度の前提で、論理は粒度間の関係である。粒度が先なので粒度を間違うと論理は間違う。価値、事実、方法の適正な粒度が、漏れなく網羅された中から確定されると、うまく目的が実現できる。
本稿は目的実現方法の考察である。
結果として、パース Peirceの仮説設定を、矛盾設定に置き換えたことになった。
個々のものや運動は網羅できないが,その種類や型が網羅可能であること、オブジェクト、粒度、矛盾(=運動)の構造のとらえ直しがこれを可能にした。1. 仮説設定=矛盾設定の全体像が明らかになった。全体は、根源的網羅思考と矛盾が、認識と事実変更、演繹と帰納を統合する方法の枠組みであった。
2. 全ての認識と変更方法の構造は、機能上の差異解消と両立という違いがあり、粒度と構造の同時変更という点では全て形式上、同じであった。
これらは、発想法、教育内容等の見直しのために必要なだけでなく、価値実現の思考と議論の新しいあり方を拓く。網羅されてないものの中に正しいものがあるかもしれない。
[33] [FIT2015]
高原, “弁証法論理の構造と中川の「6箱方式」”, FIT2015, 2015.高原_FIT2015_20150629 和文論文 8ページ
高原_FIT2015Slides_2015 和文スライド 8ページ今回のFITでは、初めて「情報システム」のセッションで論文発表を行った。今までは全て「データベース」のセッションでの発表だった。以下に登録された「抄録」を示す。
抄録: 粒度、オブジェクト、矛盾、論理的網羅という最小の基本概念で、以下を行う方法を提示した。
弁証法論理の構造の中心である矛盾は、粒度とオブジェクトの矛盾、粒度内部の矛盾、機能と構造の矛盾等のオブジェクト間の矛盾の三種であることを明らかにした。認識と事実変更に共通の方法として、事実の矛盾と解の矛盾がある。認識は事実の矛盾を解くこと、変更は解の矛盾を解き実現することである。これら全てが上の矛盾の要素に分解できた。認識と変更の脳内の観念の運動は同じ原理によっていることが明らかになった。結果として、中川徹の2005年の6箱方式の根拠を述べ粒度の重要性を追加しその展開をしたことになった。
認識と変更実現の重要度緊急度判断基準を提案した。この抄録の中で、最小の基本概念として、粒度、オブジェクト、矛盾、論理的網羅をあげている。実際には、矛盾(=運動の構造)は、粒度、オブジェクト(存在と関係)、論理的網羅から作られるので、最小の基本概念は、正確には、粒度、オブジェクト(存在と関係)、論理的網羅である。これらから、労働、生活に必要な全てが作られる。
粒度には、ギザギザの程度、粒の大きさの程度という二つの意味がある。ここでは、後者の意味で、空間的大きさ、時間的長さ、扱う属性という意味に使い、粒度の定まった「粒」も慣例に従い粒度と言う。粒、粒度の関係が論理や方法である。普通、意識されない。これを意識することが人生を変える。
そして形式論理がコンピューターに実装して実現されているように、弁証法論理も、同様に、コンピューターに実装して実現される道を拓く。
実際に発表したスライドの発表では時間が限られるので、「最小概念」で求めるものが得られる点に絞った。
(なお、正式の発表論文は、PDFのものであるが、これには、軽微なミスプリがある。) [注(中川): 本サイトには、高原の修正Word版からPDFを作成し直して掲載した。]
電気・情報関連学会中国支部連合大会で発表
[30] [CGK2013]
高原, “根源的網羅思考の機能”, 電気・情報関連学会中国支部連合大会, 2013.高原_中国連大CGK2013_p327_28-8_20130802 和文論文 2ページ
高原_中国連大CGK2013_2013 スライド 8ページ本来、固定観念を見直し続け、複雑さと変化性を扱う有用な形式が矛盾、弁証法であるはずだった。しかし、矛盾、弁証法の粒度や思考の単位を決める粒度管理のための根源的網羅思考が不十分だった。その機能見直しを続ける。
次の四つを明らかにした。
1) 同じ粒度での網羅による新しい発見、変更が得られる。
2) ある粒度があれば、その粒度での網羅が相互作用の中で行え、次に粒度を変えてさらに網羅を行う。この中で、新しい粒度での網羅による関係の発見、変更が得られる。
このサイクルの中で、根源的網羅思考は、人が産まれて以降、次第に物事を認識し学んでいく手段、次第に物事の本質的認識を進めていく手段、新たな発見や価値実現の具体化展開手段になる。3) 弁証法と根源的網羅思考の相互作用による有用さ。
粒度確定後、弁証法による変更または変更の可能性が生じ、それは、他のオブジェクトと相互作用を起こし、さらに、粒度の網羅、確定があり、新たな認識、変更、変更の可能性が生じる。根源的網羅思考の運動の型は、1) 2) 3) で網羅されている。この中に、特殊なオブジェクトである価値について次の項目がある。
4) 価値と事実の相互作用による質的に新しい価値、目的創造。
通常は、無意識に価値に規定されて目標が決まり、現実との差異の解消を行っていく。これと逆に、根源的網羅思考単独の思考サイクルの中で、事実とそれに関係する全てを網羅した認識から努力すれば可能な価値、目的が見えてくる。これが、実用上、最も重要である。[32] [CGK2014]
高原, “不確定な矛盾の生成”, 電気・情報関連学会中国支部連合大会, 2014.高原_中国連大CGK2014_p167_26-14 和文論文 2ページ
高原_中国連大CGK2014_2014 和文スライド 12ページ論理,方法である弁証法の単位は、矛盾の生成と運動である。矛盾の運動については解の型を含め、分かっている。残る課題は、他人と、内容が不確定なことを始める場合の矛盾の生成の検討である。
2012年にもこの検討を行っている。([24] [IEICE2012] 高原, “物々交換誕生の論理 ― 矛盾モデル拡張による弁証法論理再構築のための ―”, 2012年電子情報通信学会総合大会, 2012.)
本稿は、物々交換開始の論理を、他の意見も参考に再検討したものである。
この結果により、以前の定義をやや修正した。
TRIZホームページに発表したもの
[28] [THP2012]
高原, “技術と制度における運動と矛盾についてのノート”, TRIZホームページ, 2013.(『TRIZホームページ』掲載: 2013. 8. 4)
英文: ”A Note on Movement and Contradiction in Technology and Institution",
(『TRIZホームページ』掲載: 2013. 8. 4)
弁証法は、もともとギリシャの対話の術であり、自己内対話である思考の方法でもある。
今の弁証法は、残念なことに、ヘーゲルの「正反合」か、マルクスの自律矛盾 [MAKINO] か、エンゲルスの「三つの法則」になってしまった。これらは、狭い範囲、一面、粒度でしか正しくない。アルトシュラーのTRIZの弁証法は、これらを含む大きな論理を持っている。
弁証法の中核をなすのが、矛盾である。
理想の思考の必要条件は、価値を前提に、第一にオブジェクトの「正しい」粒度、第二にその粒度での網羅の全体性、第三にオブジェクト間の論理として矛盾の論理である。本稿は、二章で、従来の矛盾で扱えない運動の例として、物々交換の誕生から教訓を引き出し、次いで三章で、粒度と網羅の管理、四章以降で、その粒度と網羅からの、運動、矛盾の定義の根拠について述べ、この矛盾は、運動の構造に等しく世界の最小近似モデルであることを示す。一値の矛盾と二値の矛盾を説明した。今まで触れてきた一体型矛盾について触れていない。(矛盾の定義は、後に少し変えている)以下の三篇は、全体がA4で50ページを超えるものになったので、三つに分けた。章は全体の通し番号になっているが、個々に別々でも読めるようにした。そのため篇毎に繰り返しがある。
[34] [THP2015-1]
高原, “粒度、矛盾、網羅による弁証法論理ノート:ノート2015-1”, TRIZホームページ, 2015.(『TRIZホームページ』掲載: 2015.11.10)
生き方は、1. 普通、無意識の、価値に規定される事実に対する態度、2. 普通、無意識の、事実を認識し変更する単位である粒度特定、3. やや意識的なオブジェクトについての論理,方法の三つの全体である。まず、1. 価値に依存する態度、2. 粒度決定を、意識的に行うことが必要である。これが 3. 論理,方法を作る。
粒度、オブジェクト、論理的網羅という最小の基本概念で、矛盾を単位とする弁証法と粒度管理をする根源的網羅思考の全体を作り、新しい弁証法論理とした。生き方と生きることを、最小の基本概念で、形式的に構成する方向が定まった。
これらにより、[FIT2013]で述べた方法が豊かになった。
1. [FIT2013]の課題「根源的網羅思考について、本質的な粒度の曖昧さ処理法、粒度の正確な確定の論理」が本稿で明確になった。
2. 矛盾は、粒度とオブジェクトの矛盾、粒度内部の矛盾、機能と構造の矛盾等のオブジェクト間の矛盾の三つであることを明らかにし、弁証法論理の構造を修正した。
3. 認識と事実変更に共通の方法として、事実の矛盾と解の矛盾があること、認識は事実の矛盾を解くこと、変更は解の矛盾を解き実現することであることを述べた。「問題」を二つに分割したことで一つの「問題」を小さくした。さらに、これら全てが上の矛盾の要素に分解できるらしいことが分かった。認識と変更の脳内の観念の運動は同じ原理によっており、その原理内容の概要の方向が明らかになった。
こうして、従来、無意識だった粒度と論理的網羅を意識的に追求し、矛盾を分割してその解を求めることを提案した。
[35] [THP2015-2]
高原, “中川徹の6箱方式へのコメント:ノート2015-2”, TRIZホームページ, 2015.(『TRIZホームページ』掲載: 2015.11.10)
中川徹の「TRIZのエッセンス」は、技術に限定された表現になっているが全ての領域に拡張できる。中川徹の6箱方式の矛盾による根拠を述べ、粒度の重要性をコメントで追加した。この二つが弁証法論理のエッセンスであると考える。
本文にも書いたことだが、[34] “粒度、矛盾、網羅による弁証法論理ノート: ノート2015-1”で、粒度、オブジェクト、論理的網羅という最小の基本概念で、新しい弁証法論理を作ろうとして、その一部が、気が付いたら、中川徹の6箱方式と同じになっていた。6箱方式は2005年に発表されたもので、当時、読んで「当たり前」だと誤解していたことを中川先生にお詫びしなければならない。
本稿に、多少、新しい内容がある。
中川徹の6箱方式が、認識と事実変更に共通の方法であり、事実の矛盾と解の矛盾という矛盾の統一的原理的理解による単純な方法であり、それゆえ豊かであること示した。
但しこれは、中川徹の6箱方式についての高原のその根拠の理解とコメントに過ぎず、中川徹の6箱方式そのものではない。
中川徹の6箱方式は、本稿で触れた以上に豊富な内容がある。本稿は、中川徹の6箱方式を、やや単純化してとらえ過ぎているところがある。事実の矛盾を、機能について単純化して限定し、解の矛盾を解くのを、機能と構造の矛盾を解くことに限定しているところなどである。
発明原理のうち、「追加」の三つ(オブジェクトの追加、分割、既存の二項または分割した二項の運動の生成)、「新しい機能」の三つ(転用、汎用性、セルフサービス)、「新しい構造」の二つ(入れ子、仲介(媒介、間接化))を根本的発明原理とした。(「追加」の二つ(40の発明原理に、「追加」の二つ(オブジェクトの追加、既存の二項または分割した二項の運動の生成)、「新しい機能」の一つ(転用)を、追加している)
[36] [THP2015-3]
高原, “弁証法論理の応用展開ノート:ノート2015-3”, TRIZホームページ, 2015.(『TRIZホームページ』掲載: 2015.11.10)
生き方は、
1. 普通、無意識の、世界観と価値に規定される事実に対する態度、
2. 普通、無意識の、事実を認識し変更する単位である粒度特定、
3. やや意識的なオブジェクトについての論理,方法
の三つの全体である。
まず、1.世界観と価値に依存する態度、2. 粒度決定を、意識的に行うことが必要である。これが3. 論理,方法を作る。前二稿で、生き方と生きることの中心である認識と変更を、最小の基本概念から構成する方向で定めた。
本稿では、
1.認識と変更の内部の一部の検討と、
2.この応用として、世界の運動と歴史を同様に同じ論理で見ること
を試みた。
1.認識と変更の内部の一部の検討には、演繹、帰納、仮説設定という命題の変更方法などがある。 まだ不十分だが、論理自動化には必要な検討である。
2.この応用として、人類の歴史とその中の価値の果たす役割を述べた。
| 本ページの先頭 | 論文一覧表(第3集) | 論文集解題 (高原) | 論文集解題 (高原) (PDF) |
高原 論文集 (第1集) |
高原 論文集 (第2集) |
英文ページ |
|
| [28] THPJ2012 技術と制度 |
[29] FIT2013 世界構造 |
[34][THPJ2015-1] 弁証法論理 |
[35][THPJ2015-2] 6箱方式へのコメント |
[36][THPJ2015-3] 弁証法論理の応用展開 |
|
総合目次  |
(A) Editorial | (B) 参考文献・関連文献 | リンク集 | ニュース・活動 | ソ フトツール | (C) 論文・技術報告・解説 | 教材・講義ノート | (D) フォーラム | Generla Index |
||
| ホー ムページ |
新着情報 |
子ども・中高生ページ | 学生・社会人 ページ |
技術者入門 ページ |
実践者 ページ |
CrePS体系資料 | USITマニュアル/適用事例集 | サイト内検索 | Home Page |
最終更新日 : 2022. 1.12. 連絡先: 中川 徹 nakagawa@ogu.ac.jp